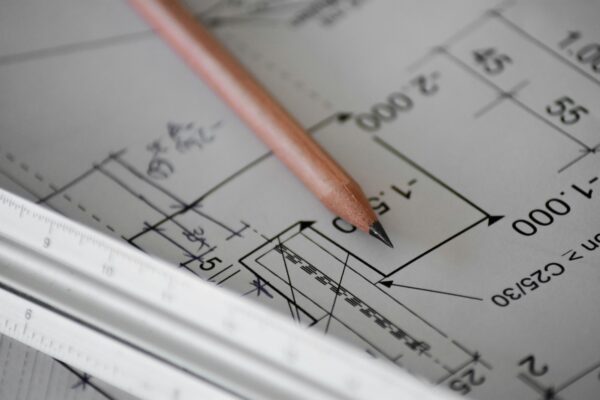そもそもサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?

事業として取り組む前に、まずはサ高住の定義や法的側面、市場の将来性といった基本を正確に押さえておきましょう。
サ高住の定義
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは、「高齢者住まい法」に基づき、主に自立あるいは軽度の要介護状態の高齢者を対象としたバリアフリー構造の賃貸住宅です。
法律により、少なくとも「安否確認」と「生活相談」の2つのサービスの提供が義務付けられています。これにより、入居者はプライバシーを保ちながらも、安心して日々の生活を送れます。あくまで「住宅」であるため、一般的な介護施設に比べて入居者の自由度が高いのが大きな特徴です。
サ高住と有料老人ホームの違い
サ高住としばしば比較対象となるのが、有料老人ホームです。両者は根拠法や契約形態、サービスの提供形態が異なります。
| サ高住 | 有料老人ホーム | |
| 根拠法 | 高齢者住まい法 | 老人福祉法 |
| 契約形態 | 賃貸借契約 | 利用権契約 |
| 主な対象者 | 自立〜軽度要介護者 | 自立〜重度要介護者まで幅広い |
| サービス | 安否確認・生活相談が必須。 介護サービスは基本的に外部事業者を利用する。 | 以下のいずれか(複数可)を提供している。 ①食事の提供 ②介護(入浴・排泄・食事)の提供 ③洗濯・掃除等の家事の供与 ④健康管理 |
特に大きな違いは契約形態です。サ高住が一般的な賃貸住宅と同じ「賃貸借契約」であるのに対し、有料老人ホームの多くは、その施設を利用する権利を購入する「利用権契約」です。
また、サ高住であっても、食事や介護、健康管理などのサービスを一体的に提供する場合は、老人福祉法上の「有料老人ホーム」にも該当します。
【出典】厚生労働省「有料老人ホームの現状と課題・論点について」
高齢化によりサ高住の需要が高まっている
日本の高齢化は加速しており、サ高住の需要も年々高まっています。国土交通省のデータによると、サ高住の登録棟数は年々増加傾向にあり、令和7年5月末時点で全国に8,323棟が登録されています。
今後、団塊の世代が75歳以上となる「2025年問題」や、国民の3人に1人が65歳以上となる「2035年問題」を控え、高齢者向け住宅のニーズはさらに拡大することが確実です。社会的な必要性が高まっている今、サ高住経営への参入は、非常に有望な事業機会といえます。
【出典】サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム「サービス付き高齢者向け住宅の登録状況(R7.5末時点)」
サ高住における4つの経営方式

福祉会社がサ高住事業に参入する際の経営方式は、土地や建物を誰が所有し、誰が運営するかによって、主に4つのパターンに分類されます。
一括借り上げ方式(サブリース)
地主(土地オーナー)が建設したサ高住の建物を、事業者様が建物ごと丸ごと借り上げて経営する方式です。
事業者様は土地や建物を所有する必要がなく、建築にかかる初期投資を大幅に抑えられます。介護事業のノウハウを活かして、スピーディーに事業を拡大したい場合に適した方式です。
ただし、地主様へ支払う建物賃料が固定費として発生します。
委託方式
建物の所有者である地主様が経営主体となり、事業者様は運営の実務を業務委託契約に基づいて請け負う方式です。
事業者様は、入居者募集や管理、介護サービスの提供といった運営業務の対価として、地主様から委託料(手数料)を受け取ります。
事業者様の収入は、施設の稼働率や収益に連動する成果報酬型になることが多く、空室リスクを地主様と分かち合う形になります。
稼働率が高ければ高い収益を期待できる一方、低ければ収入も減少するため、経営手腕が直接収益に反映される、ハイリスク・ハイリターンなモデルといえるでしょう。
テナント方式
地主様が所有・運営するサ高住の建物内で、事業者様が独立した事業者として、介護サービスなどを提供する方式です。
事業者様は、介護サービスの拠点となる事務所やデイサービススペースなどを地主様から借り、その対価として毎月固定の「テナント料」を支払います。
支出がテナント料として固定され、空室リスクを直接負わないため、安定した事業運営がしやすいのがメリットです。リスクを抑えて堅実に事業を行いたい場合に適しています。
自営方式
事業者様が土地と建物の両方を所有し、経営も自ら行う方式です。全ての収益が自社のものになるため、最も高いリターンを期待できます。
しかし、土地の取得費用から建築費用、運営費用まで、全ての資金を自社で用意する必要があり、事業リスクも最大となります。
すでに土地を所有している場合や、資金力に余裕がある場合に検討される方式です。
サ高住経営における収支モデル

ここでは、事業者が土地と建物を所有して運営する「自営方式」を基本とした、一般的な収支モデルをご紹介します。サ高住経営の収益性を判断するためには、収入と支出の内訳を正確に把握することが不可欠です。
| 収入 | 支出 |
| 家賃収入(賃料・共益費) | 人件費 |
| サービス費(安否確認・生活相談費など) | 給食材料費 |
| 食費 | 水道光熱費 |
| 水道光熱費 | 備品代 |
| 入居金償却売上 | 保守・修繕費 |
| 介護保険収入(介護サービス提供時) | 賃借料 |
| その他サービス費 など | 委託料 |
| 減価償却費 など |
上記の表は一例です。前述した経営方式によってかかる支出や入ってくる収入の内訳が異なる場合があります。
サ高住経営の収支シュミレーション
具体的な収支のイメージを持つために、一般的なコストに基づいた簡単なシミュレーションをしてみましょう。ここでは、土地の取得から始める自営方式を想定します。
| 項目 | 金額の目安(一例) | 備考 |
| 初期投資合計 | 約3億円 | |
| 土地取得費 | 約7,000万円 | 300坪の土地を1坪あたり約25万円で購入した場合 |
| 建築費用 | 約2億1,000万円 | 延床面積や仕様により変動 |
| 備品・設備費用 | 約1,500万円 | 介護用ベッド、什器など |
| 家賃設定 | 10万円/月を想定 | 1戸あたり(共益費・サービス費込み) |
【年間収入の計算】10万円/月×30戸×12ヶ月=3,600万円
この年間収入を基に、初期投資に対する大まかな利回り(表面利回り)を計算すると、以下のようになります。
「3,600万円(年間収入)÷3億円(初期投資)=12%」
これはあくまで満室を想定した表面的な利回りです。実際には、ここから人件費や水道光熱費、修繕費などの運営コストを差し引いたものが、事業の利益(営業利益)となります。
サ高住経営は、他の賃貸経営に比べて運営コストがかかる点を十分に考慮する必要があります。
サ高住の人員配置基準

サ高住を運営するには、法律で定められた人員配置基準を満たす必要があります。提供するサービス内容によって「一般型」と「介護型」に分かれます。
| 一般型 | 介護型(特定施設入居者生活介護) | |
管理者 | 1名 | 1名(兼務可) |
生活相談員 | 1名以上 | 要介護者等:生活相談員=100:1の割合 |
介護職員・看護職員 | 配置義務なし | 要支援者:介護・看護職員=10:1の割合 要介護者:介護・看護職員=3:1の割合 |
| 機能訓練指導員 | 配置義務なし | 1名(兼務可) |
| 計画作成担当者 | 配置義務なし | 介護支援専門員1名(兼務可) |
一般型は、日中に以下のいずれかの資格を持つスタッフがが少なくとも1人常駐し、生活相談や安否確認サービスを提供します。
| 社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員 医師 看護師 介護福祉士 社会福祉士 介護支援専門員 介護職員初任者研修課程修了者 |
一方、介護付有料老人ホームの指定を受けた介護型は、24時間体制での手厚い介護を提供するため、より多くの専門スタッフの配置が義務付けられています。
サ高住経営に適した土地とは?

サ高住事業の成功は、土地選びで大きく左右されます。入居者が快適に暮らせ、スタッフが働きやすい環境であることが重要です。
まず広さですが、20戸程度の施設であれば約200坪、30戸程度であれば約300坪の土地が一つの目安となります。入居者のご家族やスタッフが利用するための駐車スペースも、戸数に応じて確保する必要があります。
立地については、必ずしも駅前の好立地である必要はありません。バス停から徒歩5分圏内など、公共交通機関でのアクセスが確保されていれば十分需要が見込めます。
むしろ、大通りから一本入った閑静な住宅街の方が、高齢者が落ち着いて暮らせる環境として好まれる傾向があります。
サ高住経営を行う3つのメリット

サ高住経営には、事業者様にとって以下のメリットが得られます。
| 社会貢献になる 補助金を受け取る 固定資産税と不動産取得税が軽減される |
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
社会貢献になる
サ高住の提供は、高齢者が尊厳を保ち、安心して暮らせる社会の実現に直接貢献する事業です。
地域の福祉インフラを支え、多くの人から感謝される点は、事業を行う上での大きなやりがいとなります。
企業の社会的責任(CSR)を果たすという観点からも、非常に価値のある事業といえます。
補助金を受け取る
サ高住の建設や改修には、国から手厚い補助金制度が用意されています。建物の建設費の一部が補助されることで、事業者様の初期投資の負担を大幅に軽減可能です。
この補助金制度を活用することで、資金計画に余裕が生まれ、より質の高い施設づくりや、安定した事業運営につながります。
サ高住の補助金を受けるまでの流れについては以下の記事で解説しているので、併せてご覧ください。
【関連記事】
サ高住の建設費用は約2億円!補助金制度と収支シミュレーションを完全解説
固定資産税と不動産取得税が軽減される
サ高住事業は、税制面でも優遇措置が設けられています。一定の要件を満たせば、建物にかかる固定資産税や、土地・建物を取得した際の不動産取得税を軽減可能です。
これらの税負担が軽くなれば、長期的な事業のキャッシュフローを改善し、経営の安定化に大きく影響します。
【参考】国土交通省「サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要」
上記資料は令和7年3月末までに不動産取得した場合の話ですが、不動産取得した際に情報が新しくなっている可能性があるため、都度確認するようにしましょう。
サ高住経営を行う2つのデメリット

メリットだけでなく、事業を行う上でのデメリットも正しく認識しておく必要があります。
| 入居者トラブルの対策を立てる必要がある 事件・事故が起こるリスクも考慮する必要がある |
それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
入居者トラブルの対策を立てる必要がある
サ高住は共同生活の場であるため、入居者同士の人間関係のトラブルが発生する可能性があります。
また、提供するサービス内容について、入居者やそのご家族からクレームを受けることも考えられます。
こうしたトラブルを未然に防ぐため、明確な利用ルールを定め、入居時に丁寧に説明することが重要です。
また、問題が発生した際に迅速かつ公正に対応できる体制を整えておく必要があります。
事件・事故が起こるリスクも考慮する必要がある
入居者は高齢であるため、施設内での転倒による怪我や、急な体調不良、あるいは孤独死といった事件・事故が発生するリスクは常にあります。
これらのリスクに備え、緊急時の対応マニュアルを整備し、全スタッフで共有しておくことが不可欠です。
また、万が一の事態に備えて、損害賠償保険に加入しておくことも重要です。日頃からの見守り体制を強化し、事故を未然に防ぐ努力が求められます。

今回の記事では、福祉会社がサ高住経営に参入する上で知っておくべき、経営方式や収支モデル、メリット・デメリットなどを詳しく解説しました。
サ高住経営は、高い社会貢献性と安定した収益性を両立できる、魅力的な事業です。
しかし、その成功には、綿密な事業計画と、介護・建築の両面にわたる専門的な知識が不可欠です。
「事業計画や資金調達に不安がある」
「市場調査や土地探しからサポートしてほしい」
上記のようなお悩みをお抱えの方は、一度福祉施設での土地活用や建設に強い専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談すれば、より具体的な事業計画の立案や、資金シミュレーション、市場調査などをサポートしてもらえます。
サ高住の経営について必要な知識を身につけ、安心して事業をスタートさせられるようにしましょう。