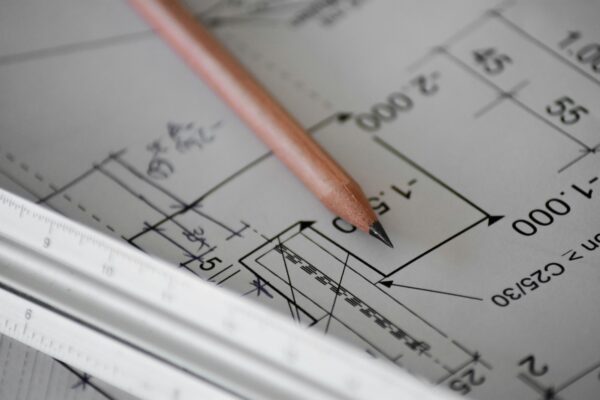ケアハウスを開業する方法とは?

ケアハウスの開業を検討する上で、まずその法的な位置づけと、事業に参入するための前提条件を正確に理解しておく必要があります。
ケアハウスは元々民間企業の参入は難しかった
ケアハウスの運営は、社会福祉法において「第一種社会福祉事業」に分類されます。これは、利用者の生活に与える影響が大きく、極めて高い公共性と安定性が求められる事業であることを意味します。
| 第一種社会福祉事業 | 第二種社会福祉事業 | |
| 概要 | 入所型の施設運営など、利用者の保護の必要性が高い事業 | 在宅サービスなど、比較的小規模で始めやすい事業 |
| 主な事業例 | 特別養護老人ホーム、ケアハウス、児童養護施設、障害者支援施設など | 訪問介護、デイサービス、保育所、障害福祉サービス事業など |
| 主な運営主体 | 国、地方公共団体、社会福祉法人 | 制限なし(株式会社、NPO法人なども可能) |
法律上、第一種社会福祉事業を経営できるのは、原則として国、地方公共団体、または非営利団体である社会福祉法人のみです。そのため、株式会社などの民間企業が単独でケアハウスを開業するのは、従来は不可能でした。
しかし、現在では都道府県知事の許可を得れば民間企業もケアハウスの運営に参画する道が開かれています。
ただし、その場合でも「経営するために必要な経済的基礎があること」「経営者が社会的信望を有している」などの厳しい要件が課せられ、参入へのハードルは依然として高いのが現状です。
【出典】厚生労働省「「ケアハウスへの株式会社参入の許可に係る技術的助言の見直し」に関する意見の募集について」について」
ケアハウス開業には法人化が必須
ケアハウスのような社会福祉事業を運営する場合、個人事業主として開業はできません。必ず「法人格」を取得する必要があります。
営利を目的とする場合は「株式会社」や「合同会社」といった会社設立が必要です。
一方で、非営利での運営を目指す場合は「NPO法人」や「一般社団法人」といった選択肢があります。
特に、非営利で地域貢献を主眼とするケアハウスの理念に鑑みれば、NPO法人や一般社団法人の設立も有力な選択肢となるでしょう。
いずれにせよ、まだ法人格をもっていない場合は、まず法人を設立する手続きから始める必要があります。
ケアハウスの種類

ケアハウスは、提供するサービスの内容によって「一般型」と「介護型」の2種類に分けられます。
どちらのタイプを選ぶかによって、ターゲットとなる入居者層や必要な人員体制が大きく異なります。
一般型ケアハウスは、食事の提供や緊急時の対応といった生活支援サービスが中心です。入居者は、身の回りのことは基本的に自分でできる、比較的自立度の高い60歳以上の高齢者が対象となります。
介護が必要になった場合は、外部の訪問介護やデイサービスといった在宅介護サービスを個別に契約して利用します。
一方、介護型ケアハウスは、一般型のサービスに加え、施設内で介護保険サービスを受けられるのが特徴です。施設のスタッフによって、食事や入浴、排泄などの身体介護が提供されます。
そのため、要介護認定を受けた方が主な対象となり、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けて運営されます。
【出典】厚生労働省「養護老人ホーム・軽費老人ホームについて」
ケアハウスの収支モデル

ケアハウスの経営を考える上で、収入と支出の構造を理解しておくのは基本です。公的な施設であるため、その収支モデルには特徴があります。
事業収入
ケアハウスの主な収入源は、入居者から徴収する利用料です。この利用料は、大きく以下の3つに分かれています。
| 生活費収入 | 食費や日常生活に必要な諸雑費 |
| 事務費収入 | 職員の人件費および施設管理費 |
| 管理費収入 | 家賃 |
これらの料金は、国の基準に基づいて一部上限が定められており、さらに入居者の前年の収入に応じて段階的に減額される仕組みになっています。
介護型の場合は、これらの利用料に加え、提供した介護サービスに対する介護報酬が収入の柱となります。
【出典】J-Net21「業種別開業ガイド ケアハウス」
事業支出
主な支出項目は、人件費、施設の維持管理費、そして入居者に提供する食事の材料費などです。特に、人件費は支出の中で最も大きな割合を占めます。
その他、水道光熱費や消耗品費、建物を賃借している場合は家賃、借入金があればその返済なども経常的に発生する支出となります。
ケアハウスの経営は、定められた収入の範囲内で、これらの支出をいかに効率的に管理できるかが鍵を握っているのです。
【出典】J-Net21「業種別開業ガイド ケアハウス」
ケアハウスを開業するための指定基準

ケアハウスを開業・運営するには、国が定める「指定基準」を満たす必要があります。基準は、主に「設備基準」「人員基準」「運営基準」の3つに大別されます。
設備基準
入居者が安全で快適な生活を送れるよう、建物の構造や設備に関する基準が細かく定められています。
例えば、居室については、入居者一人当たりの床面積は10.65㎡以上(約6.5畳)とされています。
また、共用スペースとして食堂や機能訓練室、浴室などを設ける必要があり、廊下の幅や手すりの設置など、バリアフリーに関する規定も厳格です。
これらの基準を満たした建物を確保することが、開業の前提条件となります。
【出典】e-GOV法令検索「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」
人員基準
質の高いサービスを提供するため、配置すべき職員の種類と人数が定められています。施設全体の責任者である「施設長(管理者)」を1名配置するのが基本です。
それに加え、入居者の生活相談に応じる「生活相談員」、食事の献立を作成する「栄養士」、そして施設の運営を支える「事務員」や「調理師」などの配置が必要です。
介護型の場合は、さらに看護職員や介護職員、機能訓練指導員、ケアマネジャーといった専門職を、入居者の数に応じた人数配置しなければなりません。
運営基準
日々のサービス提供や施設運営に関するルールも定められています。
例えば、入居契約時には、サービス内容や料金について重要事項を文書で説明する義務があります。
また、入居者の心身の状況を常に把握し、適切なサービスを提供するための個別計画を作成することも必要です。
その他にも、衛生管理や防災対策、苦情解決の体制整備など、入居者の尊厳を守り、安全な生活を確保するための運営体制を構築することが求められます。
【出典】厚生労働省「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」
ケアハウス開業における資金調達方法

ケアハウスの開業には、多額の初期投資と運転資金が必要です。ここでは、主な資金調達の方法を3つご紹介します。
日本政策金融公庫を活用する
政府系金融機関である「日本政策金融公庫」は、中小企業や小規模事業者、そして創業を支援するための融資制度を多数用意しています。
民間銀行に比べて、新規開業に対する融資に積極的であり、実績が少ない事業者でも借り入れしやすいのが特徴です。
特に「新規開業・スタートアップ資金」や、女性・若者・シニア向けの「女性、若者/シニア起業家支援資金」など、さまざまな融資メニューがあります。
無担保・無保証で利用できる制度もあるため、開業時にはまず相談を検討したい金融機関です。
各自治体の制度融資を活用する
「制度融資」とは、地方自治体、金融機関、そして信用保証協会の3者が連携して、中小企業などの資金調達を支援する仕組みです。
事業者が金融機関に融資を申し込む際に、信用保証協会が公的な保証人となることで、融資が受けやすくなります。
また、自治体が利子の一部を負担(利子補給)してくれる場合もあり、日本政策金融公庫よりもさらに有利な条件で借り入れできる可能性があります。
制度の内容は各都道府県や市区町村によって異なるため、事業所の所在地を管轄する自治体の窓口で確認しましょう。
助成金を活用する
「助成金」は、国や自治体が特定の政策目的(雇用の安定、労働環境の改善など)を達成するために支給するお金で、融資と違って返済の必要がないのが最大のメリットです。
介護事業に関連する助成金としては「人材確保等支援助成金」や、ハローワークなどを通じて新たに労働者を雇い入れた場合に利用できる「特定求職者雇用開発助成金」などがあります。
受給には一定の要件を満たす必要がありますが、活用できれば大きな助けとなるでしょう。
ケアハウスを開業しても将来性はあるのか

ケアハウスの経営環境は、決して楽観視できません。
独立行政法人福祉医療機構の調査によると、物価高騰や人件費の上昇を背景に、ケアハウスは赤字施設の割合が上昇傾向にあると報告されています。
収入の上限が定められている中で、コストが増加し、収益性が圧迫されているのが現状です。
しかし、その一方で、日本の高齢化は今後も進み続けます。
団塊の世代が後期高齢者となる2025年問題、さらにその先の2035年問題を見据えると、高齢者向け住宅の需要そのものがなくなることは考えにくいです。
特に、低料金で入居できるケアハウスは、公的なセーフティーネットとして、今後も重要な役割を担い続けるでしょう。
厳しい経営環境であるからこそ、効率的な運営ノウハウや、他の施設との差別化を図る質の高いサービスを提供できれば、地域に必要とされ、安定した経営を続けることは十分に可能です。
【出典】独立行政法人福祉医療機構「2021 年度 軽費老人ホーム(ケアハウス)の経営状況について」
まとめ

今回の記事では、ケアハウスの開業について、その方法や必要な基準、資金調達、そして事業の将来性などを解説しました。
ケアハウスの開業は、社会福祉事業としての高い公共性から、民間企業にとっては参入障壁が高い一方、地域社会に深く貢献できる非常にやりがいのある事業です。
その成功には、綿密な事業計画と、福祉・建築の両面にわたる専門的な知識が欠かせません。
もし、ケアハウスの開業を通じて、地域福祉への貢献を実現したいとお考えでしたら、一度介護施設の開業に強い専門家に相談することをおすすめします。