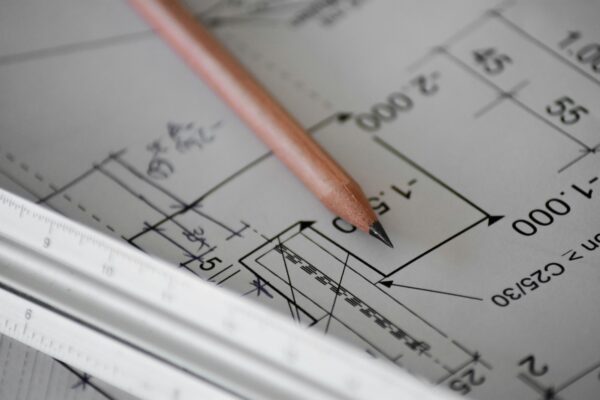サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは?他施設との違い

土地活用の方法として検討する前に、まずはサ高住がどのような施設なのか、類似する他の施設と何が違うのかを正確に把握しておきましょう。
サ高住とは
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは、主に自立〜軽度の要介護状態の高齢者を対象とした、バリアフリー対応の賃貸住宅です。
最大の特徴は「安否確認」と「生活相談」サービスの提供が義務付けられている点で、これにより高齢者が安心して自立した生活を送れるようサポートします。あくまで「住宅」であるため、入居者は比較的自由度の高い暮らしを送れます。
【出典】厚生労働省「サービス付き高齢者向け住宅について」
サ高住と有料老人ホームとの違い
サ高住とよく比較されるのが「有料老人ホーム」です。両者は契約形態やサービスの範囲に違いがあります。
| サ高住(サービス付き高齢者向け住宅) | 有料老人ホーム | |
| 契約形態 | 賃貸借契約(建物の賃貸) | 利用権契約(施設の利用) |
| 主な対象者 | 自立〜軽度の要介護者 | 自立〜要介護者まで幅広い |
| 提供サービス | 【必須】安否確認、生活相談 【任意】食事、介護など | 食事、介護、健康管理など施設によりさまざま |
| 自由度 | 比較的高い(外出が自由) | 比較的低い(施設ごとのルール) |
※サ高住の賃貸借契約の中には「終身建物賃貸借契約」と呼ばれる、高齢者の方が亡くなるまで住み続けられて、入居者が亡くなった時点で契約が終了する形態など一部例外も存在します。
有料老人ホームは、主に民間企業が運営する高齢者向けの住まいで、提供するサービス内容によって以下の3種類に大別されます。
| 介護付有料老人ホーム | 施設のスタッフが食事や入浴などの介護サービスを提供する。 |
| 住宅型有料老人ホーム | 食事や掃除などの生活支援が中心。介護が必要な場合は、外部の介護サービス事業者を利用しながらホームでの生活を継続可能。 |
| 健康型有料老人ホーム | 自立して生活できる高齢者が対象。介護が必要になった場合は退去(転居)が必要。 |
なお、サ高住であっても、食事や介護などのサービスを提供している場合は有料老人ホームに含まれます。
ただし、サ高住として都道府県に登録していれば、有料老人ホームとしての届け出は不要とされています。
【出典】
徳島県「有料老人ホーム」
厚生労働省「有料老人ホームの現状と課題・論点について」
愛知県の高齢化事情
サ高住の需要は、その地域の高齢者人口と密接に関わっています。ここでは、愛知県全体のデータと、特徴が異なる2つの市を例に見ていきましょう。
一つは、県庁所在地であり、高齢者の絶対数が多い大都市「名古屋市」。もう一つは、名古屋市の近郊に位置しており、県平均を上回る高い高齢化率が課題となっている「瀬戸市」です。それぞれ詳しく解説します。
愛知県の高齢化の推移
内閣府のデータによると、令和4年時点での愛知県の総人口749万5,000人に対し、65歳以上の高齢者人口は192万人で、高齢化率は25.6%に達しています。
これは日本の総人口における高齢化率(29.0%)よりは低いものの、今後も上昇が続く見込みです。令和27年(2045年)には、愛知県の高齢化率は33.1%に達すると予測されており、高齢者向け住宅の需要がますます高まることが予想されます。
【出典】
内閣府「令和5年版高齢社会白書」
内閣府「第1章 高齢化の状況(第1節 4)
名古屋市の高齢者の現状と推移
愛知県の中心である名古屋市も、高齢化が進んでいます。令和5年時点で、総人口232万6,683人に対し、65歳以上の人口は59万2,940人、高齢化率は25.5%です。
名古屋市の推計によると、高齢者人口は今後も増加を続け、令和22年(2040年)には69万4,000人に達すると見込まれています。
サ高住の件数についても、国土交通省の「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」によると、2025年6月時点で名古屋市に登録されているサ高住の件数が118件(4,509戸)です。
家賃に関しては、月額5万円〜24.1万円と幅広く、家賃が高いサ高住については医療法人が運営しており、看取りサービスまで対応可能な物件もあります。
そのため、高齢者の方が終の棲家として安心して過ごせる環境が整っているといえます。
【出典】
名古屋市「第2章 高齢者の現状と将来推計」
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム
瀬戸市の高齢者の現状と推移
瀬戸市の状況を見てみましょう。瀬戸市の人口は令和5(2023)年10月1日時点では12万7,568人となっており、ゆるやかに減少傾向にあります。

【出典】瀬戸市役所「第2章 高齢者の現状と将来推計」
一方で瀬戸市の令和5(2023)年の高齢者人口は3万8,352人となっており、高齢化率は30.1%です。
また、国土交通省の「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」によると、2025年6月時点で瀬戸市に登録されているサ高住は6件(154戸)で、家賃は月額7.6万円〜15.2万円の範囲にあります。
結果として、瀬戸市の高齢者人口に対して施設の数がまだ多くないことがうかがえます。地域によっては、まだまだサ高住の供給が追いついていない状況があり、土地活用のチャンスが眠っている可能性があります。
サ高住を誘致するなら「定期借地契約」がおすすめ

地主様がサ高住事業者に土地を貸し出す際に、最も重要なのが「借地契約」の種類です。契約の種類を間違えると「貸した土地が半永久的に返ってこない」という事態にもなりかねません。
土地を貸す契約には、大きく分けて「普通借地権」と「定期借地権」があります。サ高住の誘致では、契約期間が満了すれば必ず土地が返還される「定期借地権」を結ぶのが一般的であり、地主様にとって安心な方法です。
| 普通借地権 | 定期借地権 | |
| 契約の更新 | 原則更新される(借主保護が強い) | 更新されない |
| 契約期間 | 30年以上 | 契約の種類による(一般定期借地権は50年以上) |
| 契約満了後 | 正当な事由がなければ地主は更新を拒否できない | 原則、更地で土地が返還される |
| 建物の買取 | 建物買取請求権が行使された場合、地主は建物を時価で買い取る義務がある | 建物譲渡特約付借地権のみ買い取りが前提 |
【出典】国土交通省「定期借地権の解説」
定期借地権にはいくつか種類がありますが、サ高住は「居住用」の建物であるため、店舗や工場などを対象とする「事業用定期借地権」は利用できません。
そのため、「一般定期借地権」で契約するのが主流となります。
サ高住に向いている立地

サ高住を成功させるには、立地選びが非常に重要です。高齢の入居者が自立した生活を送りやすく、ご家族や介護スタッフがアクセスしやすい場所が求められます。
| スーパーや病院、公共施設などが近くにある |
| 駅やバス停から徒歩圏内である |
| 閑静な住宅街で、落ち着いて暮らせる環境 |
| 車の往来が激しすぎず、安全に外出できる |
また、原則として建物の建築が制限される「市街化調整区域」でも、サ高住のような公益性の高い施設は、一定の基準を満たせば例外的に建築が許可される場合があります。
愛知県でも同様の取り扱いがあり、郊外の土地でも活用できる可能性があります。
【出典】愛知県「市街化調整区域において「サービス付き高齢者向け住宅」の建設を計画される場合の取り扱い」
サ高住を誘致するメリット

土地活用としてサ高住を選ぶことには、地主様にとって多くのメリットがあります。安定した収益性に加え、社会的な貢献も期待できる、非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。
需要が高い
愛知県では2045年に高齢化率が33.1%に達すると予測されており、高齢者向け住宅の需要は今後も着実に高まり続けます。
一般的な賃貸住宅とは異なり、景気の波や一時的な人口移動の影響を受けにくく、構造的な社会ニーズに支えられている点が大きな強みです。
この確かな需要は、サ高住を運営する事業者の経営安定に直結します。事業者の経営が安定すれば、地主様が受け取る地代の支払いも滞るリスクが低くなります。
社会貢献につながる
サ高住の誘致は、単なる土地活用に留まらず、地域の福祉を支える大きな社会的意義をもちます。
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられる場所を提供することは、ご本人やそのご家族に大きな安心感をもたらします。
所有している土地が、地域住民の生活を支える施設として生まれ変わり、感謝される存在になることは、地主様にとって金銭的なリターン以上の誇りとやりがいになるでしょう。
長期的な収入源を得られる
運営事業者と50年以上の「一般定期借地権」で契約すれば、地主様は長期間、安定した地代収入を確保できます。アパート経営のように空室や家賃滞納、建物の修繕といった運営リスクを自ら負う必要はありません。
契約期間中は、事業者の経営状況にかかわらず、毎月決まった地代が安定的に入ってくるため、将来の生活設計が非常に立てやすくなります。
まさに老後の私的年金のように、手間をかけずに確実なキャッシュフローを生み出す資産となり、ご自身の安心な暮らしや、次世代への円満な資産承継を支えます。
サ高住を誘致するデメリット

多くのメリットがある一方で、地主様にとってのデメリットも理解しておく必要があります。
最大のデメリットは、契約期間中は他の用途に土地を使えないことです。
定期借地契約は、長期の安定収入を約束してくれる反面、土地を50年以上にわたって拘束します。
契約期間の途中で「もっと収益性の高い事業を始めたくなった」「子どもが家を建てたいと言い出した」といった事情が生じても、契約を解除して土地を返してもらうことは原則できません。
ご自身のライフプランや、将来の資産承継まで見据えたうえで、長期的に土地を貸し出すという判断を慎重に行う必要があります。
まとめ

今回の記事では、サ高住の基本的な知識から、愛知県の高齢者事情、メリット・デメリットまでを解説しました。
高齢化が進む愛知県において、サ高住の需要は今後ますます高まることが予想されます。安定した収益と社会貢献を両立できる魅力的な選択肢ですが、サ高住としての土地活用を成功させるためには専門知識が欠かせません。
ご自身の土地の可能性を最大限に引き出すためにも、まずは土地活用の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。