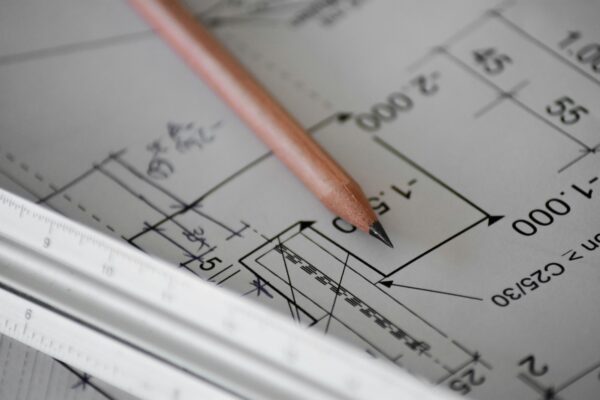医療施設として土地活用を行う3つのビジネスモデル

土地活用として医療施設の誘致を考える際、その事業形態は主に3つのモデルに分けられます。ご自身の資金力や、事業にどの程度関わりたいかに合わせて、最適な方法を選択するのが大切です。
土地だけを貸す
地主様にとって最もリスクが少なく、手軽に始められるのが、土地だけを医療法人や開業医に貸し出す方法です。
この場合、建物の建築や運営はすべて借主である医療機関側が行います。地主様は、初期投資を一切行うことなく、毎月安定した地代収入を得られます。
契約形態としては、契約期間が満了すれば必ず土地が更地で返還される「事業用定期借地権」を結ぶのが一般的です。事業用定期借地権であれば、10年以上50年未満の期間を設定して、土地を貸し出せます。
これにより「貸した土地が半永久的に返ってこない」という事態を防ぐことが可能です。運営の手間やリスクを負わずに、長期安定収入を確保したい方に適した方法です。
【出典】国土交通省「定期借地権の解説」
自己資金で建物を建てて貸す
地主様がご自身の資金でクリニックなどの建物を建設し、その建物を医療機関に貸し出す方法です。「建て貸し」ともよばれます。
土地だけを貸す場合に比べて、格段に高い収益が期待できますが、数千万円から億単位の建築資金を自分で用意する必要があり、事業リスクも自ら負う形になります。資金力に余裕があり、より高いリターンを目指したいと考える方に適した、ハイリスク・ハイリターンなモデルです。
建設協力金方式を活用する
自己資金での建築が難しい場合に有効なのが、建設協力金方式です。
これは、入居予定の医療機関から「建設協力金」として建築資金の一部または全部を預かり、地主様がその資金を使って建物を建設する方式です。預かった協力金は、契約期間中、地主様が医療機関へ支払う賃料から相殺する形で、分割して返済していきます。
この方法なら、地主様は初期の自己資金負担を大幅に抑えながら、建て貸し事業を始められます。
土地活用する際の医療施設の種類

「医療施設」と一口にいっても、その規模や役割によって種類が分かれます。土地の広さや立地によって、誘致できる施設の種類も変わってきます。
病院
医療法において、20床以上の入院用ベッドを持つ施設が「病院」と定義されています。
【出典】厚生労働省「医療法 第一条の五」
内科や外科、産婦人科など複数の診療科を備えている場合が多く、大規模な土地と広い駐車スペースが欠かせません。
運営主体も医療法人のような比較的大規模な組織になるため、安定した賃貸契約が期待できます。都市郊外の広い土地などでの活用が考えられるでしょう。
診療所(クリニック)
入院用ベッドがない、または19床以下の施設が「診療所」と定義されます。
【出典】厚生労働省「医療法 第一条の五」
建築基準法上の名称は「診療所」ですが、「〇〇クリニック」「〇〇医院」といった名称は法律で制限されていないため、自由に名乗れます。
個人の医師が開業するケースが多く、病院に比べて小規模な土地でも十分に開設可能です。住宅街や駅の近くなど、地域住民が気軽に立ち寄れる場所での需要が高いのが特徴です。
介護福祉施設
厳密には医療施設とは異なりますが、医療との連携が密接な「介護福祉施設」も、土地活用の有力な選択肢です。
例えば、「特別養護老人ホーム(特養)」には、入所者に対して健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数の医師の配置や、一定以上の人数の介護職員または看護職員、栄養士などの資格を持ったスタッフの配置が義務付けられています。
【出典】厚生労働省「介護老人福祉施設(参考資料)」
また、リハビリを主目的とする「介護老人保健施設(老健)」には、入居者100人に対して1人の医師(常勤)に加え、理学療法士や栄養士などの専門スタッフの配置も定められています。
【出典】厚生労働省「介護老人保健施設の人員」
これらの施設は、医療ニーズの高い高齢者を支える重要な社会インフラであり、安定した需要が見込まれるでしょう。
医療施設として土地活用を進めるメリット

医療施設としての土地活用は、アパート経営など他の土地活用と比較して、独自のメリットが存在します。
長期的に安定した収入が見込める
医療施設は、地域住民の健康を支える公共性の高いインフラです。
そのため、一度開業すると、景気の変動や流行に左右されることなく、長期間にわたってその場所で運営が続けられる傾向にあります。
アパートやマンションのように、入居者の入れ替わりによる空室リスクの心配が少なく、20年、30年といった長期の賃貸契約を結びやすいのが大きなメリットです。
これにより、地主様は極めて安定した収入を長期的に確保できます。
社会貢献につながる
地域に必要とされるクリニックや病院を誘致する行為は、単なる収益事業に留まらず、地域住民の健康と安心な暮らしを守るといった、大きな社会貢献につながります。
「自分の土地が、地域の役に立っている」事実は、地主様にとって金銭的なリターン以上の誇りと満足感をもたらしてくれるでしょう。地域社会との良好な関係を築き、次世代に価値ある資産として土地を残せます。
税金対策できる
医療施設としての土地活用は、税金面でもメリットがあります。ご自身で建物を建てて貸し出す場合、その土地は「貸家建付地」として扱われ、相続税評価額が更地の場合より低く評価されます。
また、建物の建築費は、法定耐用年数に応じて毎年「減価償却費」として経費計上が可能です。
そのため、不動産所得を圧縮でき、所得税や住民税の節税につながるのです。
医療施設として土地活用を進めるデメリット

多くのメリットがある一方で、医療施設ならではの注意点やデメリットも理解しておく必要があります。
施設の転用が難しい
医療施設は、診察室や処置室、レントゲン室など、特殊な間取りや設備を前提に設計されています。
また、バリアフリー対応や換気設備など、法的に求められる仕様も特殊です。
万が一、医療機関が撤退してしまった場合、その建物を他の用途に転用するのは、大規模な改修が必要となり、非常に多くのコストがかかります。
次のテナントも同業の医療機関を見つけるのが最も効率的ですが、必ず見つかるとは限らない点はリスクとして認識しておきましょう。
ビジネスモデルによっては多額の初期費用がかかる
土地だけを貸す場合は問題ありませんが、「建て貸し」を行う場合は、多額の建築資金が必要になります。
医療施設の建築は、専門的な設計や設備が求められるため、一般的な賃貸住宅に比べて建築コストが割高になる傾向があります。
特に、耐久性の高い鉄筋コンクリート造が中心となるため、初期投資は数千万円から数億円規模になる可能性も考慮しなくてはなりません。
ただし、前述の「建設協力金方式」を活用すれば、自己負担を抑える対応も可能です。
届け出に手間がかかる
地主様がどのビジネスモデルを選ぶかによって、必要な手続きの手間が変わります。
土地だけを貸す場合は、開業に関する「診療所開設届」などの手続きは、すべて借主である医療機関が行います。地主様が直接行政手続きに関わる場面はほとんどありません。
しかし、ご自身で建物を建てて貸す場合は、建物の所有者として「建築確認申請」を行う必要があります。
特に、入院用ベッドを持つ医療施設は「特殊建築物」に該当するため、耐火性能などに関する審査が通常より厳しくなる場合があります。
医療施設としての土地活用に向いている土地の条件

すべての土地が、医療施設の活用に向いているわけではありません。成功の可能性を高めるには、いくつかの条件を満たしているのが望ましいです。
適切な用途地域であること
土地には、建築できる建物の種類を定めた「用途地域」があります。医療施設の場合、その種類によって建てられる地域が異なります。
| 施設の種類 | 建築可能な主な用途地域 |
| 診療所(クリニック) | すべての用途地域で建築可能 |
| 病院 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域を除く地域 |
| 老人ホームなど | 工業専用地域を除く地域 |
【出典】東京都都市整備局「用途地域による建築物の用途制限の概要」
特に、病院や老人ホームは建築できない地域があるため、土地活用を検討する際は、まずご自身の土地の用途地域を確認するのが欠かせません。
人から認知されやすく交通のアクセスがよい土地
患者様が場所をすぐに見つけられるよう、人目に触れやすい立地であることが望ましいです。幹線道路沿いや、多くの人が利用するスーパーマーケットの近く、駅前などは理想的な立地といえるでしょう。
また、患者様は車や公共交通機関を利用して来院します。
そのため、駐車場を確保できる十分な広さがあるか、最寄りの駅やバス停から歩ける距離にあるか、といった交通アクセスの良さも重要なポイントになります。
住宅の近くにある土地
多くの人は、体調が悪いとき、自宅から近い医療機関を選びます。
そのため、周辺に住宅街が広がっている土地は、安定した患者数が見込める優良な立地です。
ただし、注意したいのが競合の存在です。すぐ近くに同じ診療科のクリニックがすでにある場合、患者の取り合いになり、経営が安定しない可能性があります。
事前に周辺の医療機関の状況を調査し、地域に不足している診療科は何か、といった市場調査を行うのが成功の鍵を握ります。
まとめ:医療施設としての土地活用を成功させるための重要なこと

今回の記事では、医療施設としての土地活用について、ビジネスモデルやメリット・デメリット、向いている土地の条件などを詳しく解説しました。
医療施設の誘致は、長期的に安定した収益と高い社会貢献性を両立できる、非常に魅力のある選択肢です。
しかし一方で施設の転用の難しさや初期費用、手続きの複雑さについても考えなくてはいけません。
成功のためには、適切な用途地域で交通アクセスが良く、住宅街に近い立地であることが重要です。
事前の市場調査で競合状況を把握し、地域に不足している診療科を見極めることが、安定した経営と地域貢献の両立につながる鍵となります。