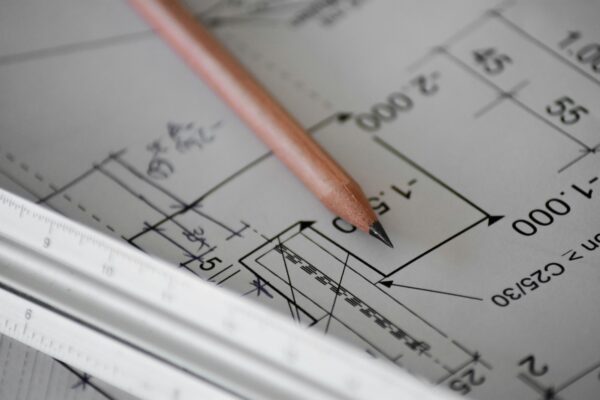介護難民とは?

近年、ニュースなどで「介護難民」という言葉を耳にする機会が増えました。
これは、介護が必要であるにもかかわらず、家庭や介護施設で適切なサービスを受けられずにいる高齢者の方々を指す言葉です。
日本の高齢化は急速に進んでおり、特に団塊の世代が75歳以上となる「2025年問題」が目下の課題となっています。
さらに2035年には、85歳以上の人口が1,000万人を超えるといわれ、介護サービスの需要はますます増大していく見込みです。
厚生労働省の推計によると、この需要に応えるためには、2040年度には約272万人の介護職員が必要とされています。
しかし、令和4年時点での介護職員数は約215万人と、すでに大きなギャップが生じており、今後この差はさらに広がると予測されています。
この需給のアンバランスが、介護を受けたくても受けられない「介護難民」を生み出す根本的な原因となっているのです。
【出典】
厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」
介護施設が不足しているといわれる原因

介護施設不足なのは、単に建物の数が足りないという単純な話ではありません。その背景には、以下の原因が考えられます。
| 介護職員が定着しない |
| 少子化も影響している |
| 介護施設の財政問題 |
それぞれの原因について詳しく解説します。
介護職員が定着しない
介護施設が不足する最も大きな原因は、介護を担う「人」が足りない点にあります。介護の仕事は、利用者の日々の生活と尊い命を支える、専門性と社会貢献性の高い職業です。
しかしその一方で、「きつい・汚い・危険」を指す3Kのイメージや、心身への負担が大きい業務内容に見合わない賃金水準といった課題を抱えています。
近年、国を挙げ待遇改善の取り組みにより、全体の離職率は改善傾向にあります。
公益財団法人介護労働安定センターの調査では、介護職員の離職率は2010年度の17.8%だったのが、2019年度には15.4%まで減っており、徐々に減少しつつあるのです。
さらに、2023年度には13.1%まで減少していることが分かっています。
しかし、同調査では離職者の約64%が勤続3年未満の職員であるというデータも示されており、経験の浅い若手人材が定着せずに辞めてしまう構造的な問題が解決していない状況がうかがえます。
結果として、施設は十分な人員を確保できず、ベッドに空きがあっても新たな入居者を受け入れられない事態に陥っているのです。
【出典】
厚生労働省「介護労働の現状と介護雇用管理改善等計画について」
公益財団法人介護労働安定センター「令和5年度「介護労働実態調査」結果の概要について」
少子化も影響している
日本の社会構造そのものの変化、すなわち「少子高齢化」も、介護施設不足に深刻な影響を与えています。
内閣府が公表した令和6年版高齢社会白書によれば、日本の生産年齢人口(15歳〜64歳)は1995年の8,716万人をピークに減り続け、2023年には7,395万人まで落ち込みました。
出生数についても、2000年に約119万人だったのに対して、2023年には約72万人まで減少しています。
これは社会全体の働き手が減少しているのを意味しているのです。
その一方で、65歳以上の高齢者人口は増加の一途をたどっています。
介護サービスの担い手となる若い世代が減り、介護を必要とする高齢者が増え続ける人口構造の歪みは、他産業との人材獲得競争を激化させ、介護業界の人手不足をより一層深刻なものにしています。
働き手の確保という点で、介護施設は極めて厳しい状況に置かれているといえるでしょう。
【出典】
内閣府「令和6年版高齢社会白書」
e-Stat「人口動態調査 人口動態統計 確定数 出生」
介護施設の財政問題
多くの介護施設は、国が定める公定価格である「介護報酬」を主な収入源としています。
しかし、国の財政が逼迫する中で介護報酬は抑制傾向にあり、事業所の収益性は常に厳しい状況です。
さらに近年では、世界的な物価高騰が介護施設の経営を直撃しています。光熱費や食料品、介護用品といった運営に欠かせないあらゆるコストが市場価格に応じて上昇するにもかかわらず、収入の柱である介護報酬は数年に一度の改定まで価格が固定されています。
この収益構造の硬直性が、多くの施設の経営を圧迫しているのです。
結果として、事業者は新たな施設の開設に踏み切れず、場合によっては既存施設の閉鎖を選択せざるを得ない状況に追い込まれています。
土地活用による介護施設不足の解消

深刻な介護施設不足の問題に対し、活用されていない土地、いわゆる「遊休地」を介護施設として活用する動きが、社会的な解決策として大きな注目を集めています。
地主様にとっては、ご自身の資産を社会貢献と安定収益の両立につなげる、またとない機会といえるでしょう。
介護施設で土地活用を始める5つのメリット
介護施設として土地活用を始めると、以下の5つのメリットが得られます。
◯安定した収入を得られる
◯社会貢献につながる
◯条件の悪い土地でも活用できる
◯建築する場合でも補助金が得られる可能性がある
◯固定資産税や相続税などの節税効果がある
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
安定した収入を得られる
介護施設は、地域住民の生活に欠かせない社会インフラです。
そのため、一度開設されると景気の変動や一時的な流行に左右される心配が少なく、長期にわたって安定した運営が期待できます。
地主様が土地を介護事業者に貸し出す場合、一般的に20年以上の長期契約を結ぶため、アパート経営のように入居者の入れ替わりや空室リスクに悩まされる心配は比較的少ないです。
毎月決まった地代収入を長期的に確保できるため、ご自身の将来設計も非常に立てやすくなります。
社会貢献につながる
日本では2025年問題や2035年問題により、今後も高齢者人口が増加するのが予想されます。
そのため、ご自身の土地を提供し、地域に新たな介護施設が誕生するのを手伝うのは、介護を必要とする高齢者やそのご家族の安心な暮らしを支える、非常に価値のある社会貢献活動といえます。
ただ所有しているだけだった土地が、地域社会から感謝される存在に生まれ変わるのは、金銭的なリターンだけでは得られない、大きな満足感につながるでしょう。
条件の悪い土地でも活用できる
アパートやマンション経営では、駅からの距離や周辺の商業施設の有無といった利便性が収益性を大きく左右します。
しかし、介護施設の場合は、必ずしも駅前の好立地である必要はありません。
入居者の生活は施設内で完結する場合が多く、むしろ郊外の静かで自然豊かな環境が、療養の場として付加価値になる場合もあります。
また、ご家族の面会や職員の通勤は車が中心となるため、駐車スペースが確保できれば問題ありません。他の活用が難しい土地でも、介護施設としてなら十分に活かせる可能性があるのです。
建築する場合でも補助金が得られる可能性がある
介護施設は公共性が高いことから、国や自治体が施設の整備を後押しするための補助金制度を設けている場合があります。
特に、ご自身で建物を建てて介護事業者に貸し出す「建て貸し」を選択する場合、この補助金制度を活用すれば、建築にかかる初期投資の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
お住まいの自治体でどのような補助金制度があるか、一度確認してみるとよいでしょう。
固定資産税や相続税などの節税効果がある
土地の上に介護施設などの建物を建てると、日々の固定資産税と、将来の相続税の両方で大きな節税効果が期待できます。
まず固定資産税については、土地の上に住宅系の建物が建つと「住宅用地の特例」が適用できる可能性があります。
これにより、土地の課税標準額を最大6分の1まで軽減可能です。
ただし、全ての介護施設で適用されるわけではなく、介護施設が「居住の用」に供されている場合に限ります。
例えば、デイサービスのような通所介護型の施設では適用されません。
また、特別養護老人ホームや有料老人ホームのように、居住用になっていたとしても、自治体によって適用可否の解釈が異なる可能性に留意してください。
次に相続税ですが、こちらも二段階で評価額が下がります。
人に貸している建物(貸家)と、その土地(貸家建付地)は、自分で使っている場合に比べて評価額が低くなります。
具体的には、建物の評価額は約30%減、土地の評価額も借地権割合に応じて15%〜20%程度低くなるのが一般的です。
さらに、その上で「小規模宅地等の特例」が適用できます。
介護施設のような貸付事業に使われている土地は「貸付事業用宅地等」に該当し、200㎡までの部分について、評価額をそこからさらに50%減額可能です。
これらの特例を組み合わせることで、相続税の負担を大幅に圧縮し、円満な資産承継につなげられます。
【出典】国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
介護施設で土地活用を始めるデメリット
多くのメリットがある一方で、介護施設としての土地活用には、事前に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。主に以下の4つの点が挙げられます。
| 参入に多額の資金を必要とする |
| 建物や用地の転用性が低い |
| アパートなどの不動産賃貸業と比べると収益性が低い |
| 事業者撤退のリスクがある |
土地活用で介護施設を選択した場合は、しっかり収益を伸ばしていくとなると、自身で介護施設を建てて事業者に貸す「建て貸し」や自身で経営に携わる選択をする必要があります。
その場合は数千万円〜数億円単位で建築コストが発生するため、ハードルが高いのも事実です。
詳しいデメリットについては以下の記事で解説しているので、併せてご覧ください。
【関連記事】
介護施設の土地活用とは?メリット・デメリットや経営方式を解説
介護施設不足を解消するためにタカオで土地活用を始めてみませんか?

今回の記事では、日本が直面する介護施設不足の現状とその原因、そしてその解決策として、土地活用がいかに有効であるかを解説しました。
深刻な人手不足や社会構造の変化により、介護施設不足は今後ますます深刻化すると予測されています。この社会的な課題を解決する上で、活用されていない土地は大きな可能性を秘めています。
介護施設としての土地活用は、地主様にとって単に土地を収益化するだけでなく、地域社会に貢献し、次世代に誇れる資産を残すための、非常に意義深い選択肢です。
もし、ご自身の土地活用を通じて、介護施設不足の解消に貢献したいとお考えでしたら、ぜひ一度、介護施設の建設や開業支援に強みを持つ株式会社タカオにご相談ください。