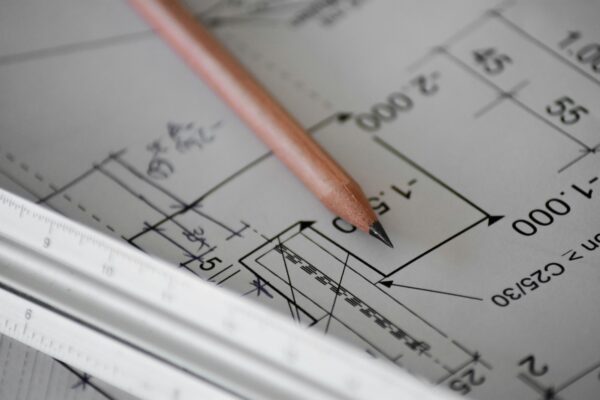コンテナ(トランクルーム)経営とは?

コンテナ経営とは、所有する土地にコンテナを設置し、収納スペースとして貸し出して賃料収入を得る土地活用方法です。屋外にコンテナを設置するため「屋外型トランクルーム」ともよばれます。
少ない初期費用で始められ、管理の手間も比較的少ないため、土地活用初心者の方にも人気のビジネスです。近年、住宅の収納スペース不足や、法人の在庫・書類保管場所としての需要が高まっています。
実際に、トランクルームの市場は拡大傾向にあります。日本経済新聞によると、屋内型トランクルーム大手、キュラーズ(東京・品川)の調査では、トランクルームの市場規模は2023年に約776億円となり、調査開始した2008年の3倍近くに成長しているとのことです。
今後も市場の拡大が予想されており、コンテナ経営は将来性のある土地活用方法といえるでしょう。
【出典】日本経済新聞「トランクルーム膨張、今後5年で4割増 ビル1棟改装も」
コンテナ経営の形式

コンテナ経営と一括りにいっても、その形式は大きく分けて「屋外型」と「屋内型」の2種類があります。
どちらも収納スペースを貸し出すという点では同じですが、設置方法や特徴が異なります。それぞれの違いを理解し、ご自身の土地や目的に合った形式を選びましょう。
屋外型
屋外型は、所有する土地にコンテナを設置して貸し出す、一般的な形式です。更地の状態から始められ、工事もコンテナの設置が主となるため、短期間で事業を開始できます。
利用者は、家電、アウトドア用品、バイクなど、普段使わない家具や季節品、趣味の道具などさまざまな保管用途で利用できます。
ただし、コンテナ内は外気の影響を受けやすく、温度や湿度の管理が難しい点がデメリットです。
そのため、温度の変化で質が変わるワインや、湿度で傷みやすい書籍、美術品などの保管には向いていません。
屋内型
屋内型は、ビルやマンションのフロアを区切って収納スペースとして貸し出す形式です。こちらは「トランクルーム」の名称で呼ばれるのが一般的です。
屋外型とは異なり、空調設備が整っている場合が多く、温度や湿度を一定に保てます。そのため、衣類や書類、美術品といったデリケートな物品の保管に適しています。
セキュリティ面でも、建物の入口と各部屋の二重ロックが可能なため、屋外型より強固な対策ができます。
ただし、建物を建設するか、既存の建物を改装する必要があるため、屋外型よりも初期費用は高くなるでしょう。
コンテナ経営における3つの運営方式

コンテナ経営を始めるにあたり、運営方式をどうするか決める必要があります。運営方式は主に「事業用定期借地方式」「リースバック方式」「業務委託方式」の3つです。
ご自身の状況や、経営にどこまで関わりたいかに合わせて、最適な方式を選びましょう。それぞれの特徴を解説します。
事業用定期借地方式
事業用定期借地方式は、土地オーナーがトランクルーム運営会社に土地を貸し、運営会社が地代を支払う方式です。
土地オーナーは土地を貸すだけで、コンテナの設置から利用者の募集、管理まで、すべての運営を運営会社が行います。土地オーナーは、毎月決まった地代を受け取るだけです。
そのため、手間をかけずに安定した収入を得たい方に向いています。コンテナ経営の知識がなくても始められる点が最大のメリットです。
ただし、収益は固定の地代のみとなるため、他の方式に比べて大きなリターンは期待できません。
リースバック方式
リースバック方式は、土地オーナー自身がコンテナを購入・設置し、そのコンテナをトランクルーム運営会社に一括で貸し出す方式です。
コンテナの購入費用はオーナーが負担しますが、利用者の募集や管理、トラブル対応は運営会社に任せられます。
事業用定期借地方式よりも高い収益が期待でき、かつ運営の手間を省ける、バランスの取れた方式といえるでしょう。
業務委託方式
業務委託方式は、土地オーナーが経営の主体となり、利用者の募集や集金、清掃といった管理業務の一部を運営会社に委託する方式です。コンテナの設置から経営までをオーナー自身が行います。
3つの方式のなかで、最も収益性が高いのが特徴です。稼働率が高ければ、その分大きなリターンが見込めます。
一方で、経営がうまくいかなかった場合のリスクはすべてオーナーが負うことになるため注意しましょう。経営に関する知識やノウハウが求められるため、上級者向けの方式です。
コンテナ経営のメリット

コンテナ経営が土地活用として注目されるのは、他の活用方法にはないメリットがあるからです。
特に、アパートやマンション経営と比較した場合、その手軽さや安定性が目立ちます。ここでは、コンテナ経営を始めるうえで知っておきたい主なメリットを3つ紹介します。
土地の立地に左右されにくい
コンテナ経営は、アパートや駐車場経営ほど土地の立地条件に厳しくありません。駅からの距離や日当たりといった、住宅地としての人気に影響される要素が少ないからです。
利用者は車で荷物を運ぶ場合が多いため、むしろ幹線道路沿いや車でアクセスしやすい場所が好まれます。住宅地としては条件の悪い土地でも、コンテナ経営なら十分に収益化が可能です。
また、形のいびつな土地や狭い土地でも、コンテナのサイズや配置を工夫することで始められます。
住宅経営などと比べて初期費用が安い
アパートやマンションを建てる場合、数千万円から数億円の初期費用がかかります。一方、コンテナ経営は、コンテナの購入・設置費用や土地の整備費用が主な出費です。
そのため、数百万円程度から始められる場合が多く、初期投資を大幅に抑えられます。
金融機関からの借入額も少なくて済むため、返済リスクを低減できます。少ない資金で始めたい方や、初めて土地活用に挑戦する方にとって、大きなメリットといえるでしょう。
長期で安定した収入が得られる
コンテナの利用者は、一度契約すると長期間利用する傾向にあります。一度収納した荷物を頻繁に出し入れするケースは少なく、住居のように気軽に引っ越すことはまれだからです。
そのため、空室リスクが低く、長期にわたって安定した賃料収入が期待できます。住宅経営のように、景気の変動や周辺環境の変化による影響を受けにくいのも強みです。
着実に収益を積み重ねていきたい方にとって、魅力的な土地活用方法です。
コンテナ経営は儲からないって本当?リスクについて解説

「コンテナ経営は儲からない」という話を聞いたことがあるかもしれません。手軽に始められる一方で、もちろんリスクも存在します。
メリットだけでなく、デメリットやリスクを正しく理解しておくことが、成功への第一歩です。ここでは、コンテナ経営の収益に関する主なリスクを2つ解説します。
収益化までに時間がかかる場合がある
コンテナ経営は、アパート経営のように、完成すればすぐ満室になるわけではありません。事業を開始してから、地域の住民に認知され、利用者が徐々に増えていくのが一般的です。
そのため、満室稼働にいたるまでには数か月から1年程度の期間を要する場合があります。最初のうちは収入が安定せず、赤字になる可能性も考慮しておきましょう。
収益化までの期間を見越して、余裕をもった資金計画を立てることが失敗しないためには不可欠です。
住宅経営よりも収益性が低い
コンテナ経営は、初期費用が安い分、アパートやマンション経営と比べると収益性は低くなります。同じ面積の土地で比較した場合、得られる賃料収入は住宅経営のほうが高くなるのが一般的です。
大きな利益を追求するというよりは、少ない投資で着実に収益を得る「ミドルリスク・ミドルリターン」の土地活用と考えるのがよいでしょう。高い利回りを求める方には、物足りなく感じるかもしれません。
コンテナ経営で失敗しないための4つのポイント

コンテナ経営を成功させるためには、事前の準備と計画が何よりも重要です。メリット・デメリットを理解したうえで、失敗するリスクをいかに減らしていくかが鍵となります。
ここでは、コンテナ経営で失敗しないために押さえておきたい4つのポイントを解説します。
市場調査を行いニーズ把握する
コンテナ経営を始める前には、必ず市場調査を行いましょう。周辺に競合となるトランクルームがどれくらいあるか、料金設定はいくらかなどを調べます。
また、どのような人が住んでいる地域なのかも重要です。
例えば、ファミリー層が多い地域では季節用品やレジャー用品の保管場所として、単身者が多い地域では引っ越し時の一時的な荷物置き場としての需要が見込めます。
地域の特性を理解し、本当にコンテナの需要があるのかを見極めることが成功の第一歩です。
用途地域を把握しておく
コンテナ経営は、土地がどの場所にあっても始められるわけではありません。土地には都市計画法によって「用途地域」が定められており、地域によってはコンテナ経営ができない可能性があります。
原則として、以下の用途地域ではコンテナの設置ができません。
◯第一種低層住居専用地域
◯第二種低層住居専用地域
◯第一種中高層住居専用地域
ただし、コンテナ経営の契約形態や事業の実態について、自治体がどのように判断するかは注意が必要です。多くのコンテナ経営は、あくまでも収納スペースを貸し出す「倉庫業を含まない倉庫」として運営しています。
しかし、たとえ倉庫業ではない形態でも、自治体によっては事業の実態から「倉庫業に準ずる施設」とみなされ、第二種中高層住居専用地域では運営が認められないケースがあります。
まずは、所有している土地がどの用途地域に該当するのか、事前に役所の都市計画課などで確認しましょう。
また、都市計画法の規定で、市街化調整区域内でも原則コンテナを倉庫として設置することは原則認められていません。
【出典】
東京都都市整備局「コンテナを利用した倉庫等の建築基準法上の取扱いについて」
愛媛県「【注意喚起】コンテナを利用した建築物の注意点のお知らせ」
盗難・破損・災害のリスク管理を徹底する
コンテナ経営では、利用者の大切な荷物を預かるため、徹底したリスク管理が求められます。
特に屋外型の場合、盗難のリスクは避けられません。防犯カメラやセンサーライトの設置、夜間の照明など、セキュリティ対策は万全に行いましょう。
また、台風や地震といった自然災害によるコンテナの破損や、荷物への損害も考えられます。
万が一の事態に備えて、施設賠償責任保険や火災保険に加入しておくことが重要です。セキュリティや安全対策を怠ると、利用者の信頼を失い、経営に大きな打撃を与えます。
土地活用の専門家に相談する
コンテナ経営は手軽に始められますが、成功するためには専門的な知識やノウハウが必要です。市場調査や用途地域の確認、リスク管理など、自分一人で全てを判断するのは簡単ではありません。
そこで頼りになるのが、土地活用の専門家です。専門家は、所有している土地がコンテナ経営に適しているのか、どのくらいの収益が見込めるのかといった具体的なアドバイスを提供してくれます。
まとめ

コンテナ経営は、少ない初期費用で始められ、長期的に安定した収入が期待できる魅力的な土地活用方法です。
しかし、成功するためには事前の調査や専門的な知識が不可欠です。
「自分の土地でコンテナ経営は可能なのか」「どの運営方式が自分にあっているのかわからない」など、少しでも不安や疑問をお持ちでしたら、ぜひ一度、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。