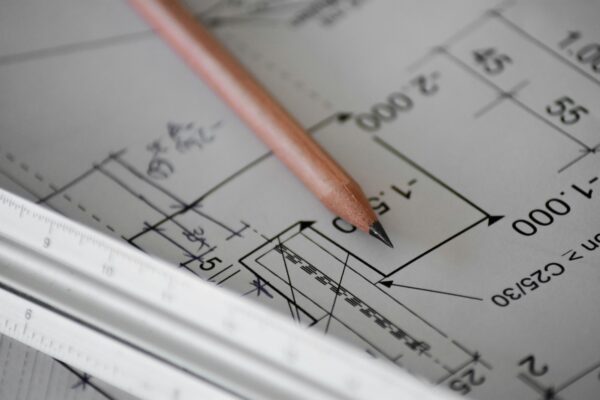福祉施設の種類とは

「福祉施設」と一口にいっても、その対象者や根拠となる法律によって、さまざまな種類に分類されます。事業計画を立てる第一歩として、どのような施設があるのかを理解しましょう。
福祉施設は「第一種社会福祉事業」「第二種社会福祉事業」に分けられており、具体的には以下のような種類が存在します。
| 老人福祉施設 | 特別養護老人ホームやデイサービスセンターなど、高齢者の生活を支援する施設です。(根拠法:老人福祉法) |
| 障害者支援施設 | 障害のある方の自立した生活や社会参加を支援する施設です。(根拠法:障害者総合支援法) |
| 保護施設 | 生活に困窮する方々を保護し、自立を助けるための施設です。(根拠法:生活保護法) |
| 婦人保護施設 | さまざまな事情により支援を必要とする女性を保護する施設です。(根拠法:売春防止法) |
| 児童福祉施設 | 助産施設や乳児院、保育所、児童養護施設など、子どもの健全な育成を支える施設全般を指します。(根拠法:児童福祉法) |
特別養護老人ホームのような入所施設は第一種、デイサービスのような通所施設は第二種に分類され、それぞれ運営できる主体が法律で定められているのです。
また、有料老人ホームやグループホームのように、上記の社会福祉施設の枠組みとは別に、個別の法律に基づいて運営される福祉関連施設も数多く存在します。
どの施設を建設するかによって、適用される法律や基準、参入要件が大きく異なるため、最初の事業選択が極めて重要になります。
福祉施設建設における必要設備

福祉施設を建設する際には、利用者の安全と快適な生活を確保するため、法律で定められた設備基準を満たす必要があります。
ここでは、特に多くの施設で共通して求められる基本的な基準について解説します。
部屋の広さ
利用者が多くの時間を過ごす居室には、最低限の面積基準が設けられています。
例えば、居室は原則として個室とし、一居室の面積は7.43㎡以上とすること、となっています。
※地域の事情により難しい場合は居室の床面積が1人あたり4.95㎡以上のスペース確保が必要
ただし、社会福祉施設の種類によっては、基準が異なる可能性もあるため注意が必要です。以下は、厚生労働省の参考資料から抜粋したものです。
【出典】厚生労働省「社会福祉住居施設の設備基準」
建設物の採光の基準
利用者の健康的な生活を維持するため、採光に関する基準も重要です。
建築基準法では、居室には採光のための窓、その他の開口部を設け、採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して一定の割合以上確保するよう定められています。
具体的には、住宅の居室であれば床面積の7分の1以上、その他の建築物であれば5分の1から10分の1以上が基準です。
福祉施設においても、施設の種類や居室の用途に応じて、これらの基準を参考に、十分な自然光を取り入れられる設計が求められます。
【出典】
e-GOV法令検索「建築基準法 第二十八条(居室の採光及び換気)」
厚生労働省「社会福祉住居施設の設備基準」
その他の基準
上記以外にも、福祉施設の建設においては、安全性を確保するためのさまざまな基準が存在します。
| 耐火・防火設備 | 火災発生時の被害を最小限に抑えるため、建物の構造や規模に応じて、耐火建築物や準耐火建築物とすることや、スプリンクラー、自動火災報知機の設置が義務付けられています。 |
| 廊下の幅 | 車椅子での移動や災害時のスムーズな避難を考慮して、廊下の幅にも基準が設けられており、例えば、両側に居室がある中廊下の場合、幅2.7m以上が求められる場合があります。 |
| バリアフリー設備 | 手すりの設置や段差の解消はもちろん、多目的トイレの設置など、高齢者や障害のある方が安全に利用できるための配慮が欠かせません。 |
【出典】内閣府ホームページ「要介護高齢者の「生活の場」整備促進」
申請する建築用途に注意
福祉施設を建設する際、建築確認申請を行う上で「建築用途」を正しく設定するのは非常に重要です。
建築基準法では、建物をその使い方によって分類しており、福祉施設の多くは「特殊建築物」に該当します。
特殊建築物は、不特定多数の人が利用するため、一般の住宅よりも厳しい安全基準や避難規定が適用されます。
どの用途で申請するかによって、クリアすべき法規制が異なるため、設計段階で行政の担当部署や専門家と綿密に協議し、適切な建築用途を確認しておく作業が欠かせません。
福祉施設の建設における構造別メリット・デメリット

福祉施設の建物をどの構造で建てるかは、コストだけでなく、耐久性や設計の自由度、将来のメンテナンスにも大きく影響します。主な4つの構造の特徴を理解し、事業計画に合った選択をしましょう。
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄骨の骨組みの周りに鉄筋を配置し、コンクリートを打ち込んで一体化させた構造です。鉄骨造と鉄筋コンクリート造の長所を組み合わせた、高性能な構造といえます。
メリットは、法定耐用年数が47年と長く、耐久性が非常に高い点です。
さらに、柱や梁を比較的小さく設計できるため、居住空間を広く確保しやすい利点もあります。
一方、デメリットは、高性能な分、材料費が高額になり、工事期間も長くなる傾向にある点です。
また、他の構造に比べて設計上の制約があり、自由なデザインが難しい場合もあります。
鉄筋コンクリート造
鉄筋の型枠にコンクリートを流し込んで作る、非常に強固な構造です。熱に弱い鉄筋と、引張力に弱いコンクリートの短所を互いに補い合っています。
メリットは、法定耐用年数が47年と長く、耐久性・耐震性・気密性・耐火性といったあらゆる面で優れている点です。
デメリットは、建築コストが高額になる点です。また、建物自体の重量が重くなるため、地盤の補強工事が必要になる場合が多く、将来の解体費用も高くなる傾向にあります。
鉄骨造
柱や梁などの骨組みに鉄骨を使用する構造です。鉄骨の厚みが6mm以上の「重量鉄骨造」は、3階建て以上の施設や大型店舗などに用いられます。
メリットは、柱が少なくても強度を保てるため、広々とした空間を確保しやすい点です。また、耐久性や耐震性も高いのが特徴です。
一方、デメリットは、建物を支えるために強固な地盤が必要で、地盤補強工事に費用がかかる場合がある点や、軽量鉄骨造に比べて建築費用が高くなる点です。
木造
建物の主要な構造部分に木材を使用した、日本の戸建て住宅やアパートで最も一般的な構造です。福祉施設でも、小規模な施設やグループホームなどで多く採用されています。
メリットは、材料費が比較的安価で、建築コストを抑えやすい点です。また、軽量でありながら高い耐震性能を持ち、通気性にも優れています。
一方、デメリットは、法定耐用年数が22年と他の構造に比べて短い点と、シロアリなどの害虫被害を受ける可能性があるため、定期的な対策やメンテナンスが欠かせない点です。
福祉施設の建設コスト

福祉施設の建設コストは、年々増加傾向にあります。主な要因としては建築資材や人件費の高騰が関わっており、2020年のコロナ禍や2022年のウクライナショックもコスト増に拍車をかけています。
福祉施設、特に介護施設の建設コストについては以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。
【関連記事】介護施設の建築費はいくらかかる?コストや業者選定方法を徹底開設
福祉施設建設の資金調達方法
福祉施設の建設には多額の資金が必要です。自己資金だけで賄うのは困難な場合が多く、外部からの資金調達を計画的に行う必要があります。
福祉施設を建設する際の主な資金調達方法を3つご紹介するので、参考にしてください。
日本政策金融公庫の活用
政府系の金融機関である「日本政策金融公庫」は、民間銀行に比べて、新規事業や中小企業への融資に積極的です。
特に、社会貢献性の高い福祉事業は、融資審査において有利に働く可能性があります。「新規開業・スタートアップ支援資金」などの制度を利用すれば、比較的低い金利で、長期の返済計画を組める場合があります。
【出典】日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
銀行の融資を受ける
民間の銀行や信用金庫からの融資も、一般的な資金調達の方法です。
取引実績のある金融機関に相談するのがスムーズですが、複数の金融機関に事業計画を提示し、より有利な条件を引き出す姿勢も重要です。
融資を受けるには、事業の将来性や収益性を具体的に示した、精度の高い事業計画書が欠かせません。
国の補助金を活用
福祉施設の整備に対しては、国が補助金制度を設けています。例えば、厚生労働省が所管する「社会福祉施設整備補助金」は、社会福祉法人等が行う特定の施設の整備費に対して、その費用の一部を国と都道府県が補助する制度です。
ただし、補助の対象は原則として社会福祉法人等に限定されており、株式会社などの民間事業者が直接利用するのは難しい場合があります。
しかし、民間事業者が設置する社会福祉施設については、独立行政法人福祉医療機構において、社会福祉事業施設等の設置や整備に関して、資金の融資を行っている場合があるため、チェックしてみるのがおすすめです。
【出典】厚生労働省「社会福祉施設の整備・運営」
まとめ:福祉施設建設のご相談は信頼出来るパートナーに!

今回の記事では、福祉施設の建設を検討している事業者様に向けて、施設の基本的な種類や、建設時に遵守すべき基準、資金調達の方法などを解説しました。
福祉施設の建設は、利用者の安全と快適な生活を支えるための、専門性の高い事業です。
福祉施設の開業を成功させるには、福祉と建築、両方の分野に精通した信頼できるパートナーの存在が欠かせません。
もし、福祉施設の建設に関するお悩みや、具体的な計画についての相談はその道のプロに相談するのが一番です。また、その地域に土地勘のある人であることも重要です。
自分でしっかりと調べることも非常に重要ですが、具体的な計画に移す前に専門家の意見も取り入れるようにしましょう。