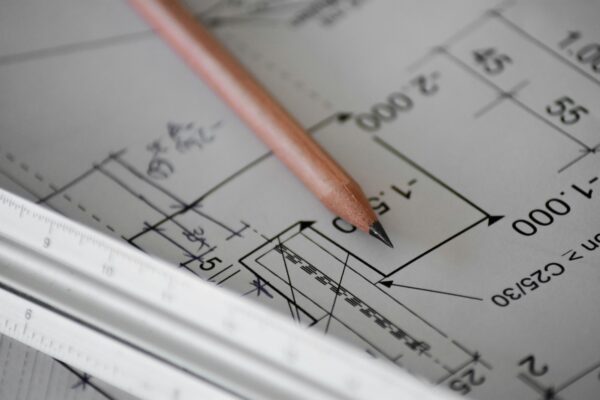土地が売れない6つの理由

「どうして自分の土地は売れないのだろう」と悩む前に、まずはその原因を探ることが大切です。土地が売れない背景には、主に6つの理由が考えられます。
土地の立地条件が悪い
土地の価値を大きく左右するのが「立地」です。買い手の多くは、その土地に家を建てて住むことを想定しているため、生活の利便性が低い土地は敬遠されがちになります。
例えば、以下の条件に当てはまる土地は、一般的に「立地が悪い」と判断されやすいです。
| 最寄り駅やバス停から遠い |
| 近隣にスーパーやコンビニ、病院などの生活施設がない |
| 日当たりや風通しが悪い |
| 周辺の治安に不安がある |
これらの条件は、日々の暮らしの快適さに直結するため、買い手が見つかりにくくなる大きな理由となります。
土地の価格が高い
土地が売れない最もシンプルな理由として、そもそも販売価格が周辺の相場と比べて高すぎる可能性が挙げられます。
特に、相続した土地の場合、所有者様の「この土地にはこれくらいの価値があるはずだ」との思い入れが、客観的な市場価格と乖離しているケースが少なくありません。
買い手は複数の物件を比較検討しているため、相場より高い物件は、内見などの候補から真っ先に外されてしまいます。
まずは、不動産会社の査定などを通して、ご自身の土地の適正な市場価値を冷静に把握する必要があります。
土地の境界が曖昧
隣地との境界がはっきりしていない土地も、売却が難航する原因になります。土地の境界には、個人の土地同士の境目である「民々境界」と、道路など公的な土地との境目である「官民境界」の2種類があります。
この境界が確定していないと、正確な土地の面積がわからず、買い手は安心して購入に踏み切れません。
「後から隣人と境界トラブルになるのではないか」「予定していた大きさの家が建てられないのではないか」といった不安を抱かせてしまうため、売買の大きな障害となります。
土地の状態が良くない
土地そのものの物理的な状態も、売れ行きに影響します。
例えば、正方形や長方形からかけ離れた不整形な土地(変形地)は、建物の設計に制約が多く、デッドスペースが生まれやすいため、買い手がつきにくいです。
また、敷地内に大きな石が埋まっていたり、古い建物の基礎が残っていたりすると、撤去に別途費用がかかるため敬遠されます。
さらに、過去に隣人トラブルがあったり、近隣に騒音や悪臭の原因となる施設があったりする場合も、売却を困難にする要因です。
災害のリスクがある
日本は自然災害の多い国であり、土地の安全性を重視する買い手は年々増えています。そのため、災害リスクの高い土地は売れにくくなるでしょう。
具体的には、自治体のハザードマップで「土砂災害警戒区域」や「浸水想定区域」に指定されている土地が該当します。
また、地盤が弱い軟弱地盤の土地や、がけの上や下に位置する土地(崖地)も、地震や大雨による災害リスクが高いと判断され、買い手を見つけるのが難しいです。
安全に暮らせるという安心感が得られない土地は、選ばれにくいのが現実です。
不動産会社が合っていない
土地そのものに大きな問題がなくても、売却活動を依頼している不動産会社の販売戦略が、その土地の特性と合っていないために、売却が長期化するケースも考えられます。
土地の売却には、その土地が持つ独自の魅力を的確に捉え、ターゲットとなる購入希望者へ効果的に情報を届ける販売戦略が欠かせません。
例えば、地域に密着した買い手を探すのが得意な会社もあれば、広域的な広告展開を得意とする会社もあります。
もし、販売活動の報告内容や提案される戦略に疑問を感じる、あるいはコミュニケーションが円滑でないと感じる場合は、自社の土地の売却を得意とする、別の不動産会社へ相談してみるのも一つの方法です。
売れない土地はどうするのが正解?9個の対処法

土地が売れない理由がわかったら、次はいよいよ具体的な対策です。ここでは、状況を打開するための9つの対処法をご紹介します。
不動産会社を変える
現在の販売活動に疑問を感じる場合、思い切って依頼する不動産会社を変更するのが有効な場合があります。不動産会社によって、得意なエリアや物件種別、販売戦略はさまざまです。
ただし、注意したいのが「媒介契約」の種類です。不動産会社との契約には、複数の会社に依頼できる「一般媒介契約」と、1社にしか依頼できない「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」が存在します。
【出典】国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の規程による標準媒介契約約款」
後者の場合、契約期間中にご自身の都合で契約を解除すると、違約金が発生する可能性があるため、契約内容を事前にしっかり確認しましょう。
土地の境界を確定させる
土地の境界が曖昧な場合は、「確定測量」を行って境界をはっきりさせる作業が欠かせません。土地家屋調査士に依頼し、隣地の所有者や役所の担当者立ち会いのもとで境界を確認し、「確定測量図」を作成します。
費用は土地の状況によりますが、50万円〜100万円程度が目安です。費用はかかりますが、土地の正確な面積がわかり、境界トラブルのリスクがなくなるため、買い手は安心して購入を検討できるようになります。
その結果、売却の可能性が格段に高まるでしょう。
土壌汚染調査を行う
過去に工場やガソリンスタンドがあった土地など、土壌汚染の可能性がある場合は、専門の調査会社に依頼して土壌汚染調査を実施するのがおすすめです。
調査には、資料で土地の履歴を調べる「フェーズ1調査」と、実際に土壌を採取して分析する「フェーズ2調査」があります。
売却時に買い手の安心材料とするためには、フェーズ2調査が必要です。1ポイントあたり50〜100万円程度の費用はかかりますが、「この土地は安全です」と客観的な証明があれば、買い手の不安を払拭でき、スムーズな売却につながります。
土地の価格を値下げする
最も直接的で効果的な方法が、販売価格の見直し(値下げ)です。周辺の類似物件の取引事例や、現在の市場動向を参考に、不動産会社と相談しながら適正な価格に再設定しましょう。
いつまでも売れないまま固定資産税を払い続けるよりは、多少価格を下げてでも早期に売却した方が、結果的に損失を少なくできる場合があります。
ただやみくもに下げるのではなく、戦略的に価格を調整する姿勢が求められます。
隣人に相談する
隣地に相談して、自分の土地を買い取ってもらうのも一つの方法です。隣地を購入すれば、自分の敷地を広げられ、より大きな家を建てたり、庭や駐車場を確保したりできるためです。
一般の買い手には魅力的に映らない土地でも、隣人にとっては大きな価値を持つ可能性があります。
ただし、個人間での取引はトラブルが起きやすいため、必ず不動産会社を仲介するようにしましょう。
空き家・空き地バンクに登録する
各自治体が運営する「空き家・空き地バンク」に土地の情報を登録する方法も考えられます。空き家・空き地バンクとは、自治体が移住・定住を促進する目的で、空き家や空き地の情報を集約し、購入希望者に提供する仕組みです。
公的な制度であるため安心して利用でき、一般的な不動産市場とは異なるルートで購入希望者を見つけられる可能性があります。
特に、地方の土地で買い手が見つからない場合に有効な手段といえるでしょう。
【出典】国土交通省「全国版空き家・空き地バンク Q&A(自治体向け)」
相続土地国庫帰属精度を利用する
「どうしても買い手が見つからず、ただ手放したい」という場合は「相続土地国庫帰属制度」を利用して、土地を国に引き取ってもらう方法が考えられます。この制度は、相続した不要な土地の所有権を国に移す制度です。
ただし、引き取ってもらうためには、管理がしやすい更地であるなどの条件を満たす必要があり、審査手数料や10年分の土地管理費相当額の負担金も発生する点に注意が必要です。すべての土地が対象になるわけではないため、詳細は法務局にご確認ください。
【出典】法務省「相続土地国庫帰属制度について」
土地の引き取り業者に依頼する
近年では、売れない土地を専門に引き取ってくれる民間業者も存在します。有償での引き取りになりますが、国庫帰属制度より条件が緩やかで、スピーディーに手放せる場合があります。
しかし、中には「無料で引き取る」などと謳い、高額な測量費や手数料を請求する悪質な業者も存在するため、注意が欠かせません。
特に「原野商法」のような詐欺的な手口もあるため、業者選びは慎重に行い、複数の業者を比較検討しましょう。
土地活用を行う
「売る」という選択肢に固執せず、「活用する」という視点に切り替えるのも一つの有効な手といえます。売れない土地でも、その特性を活かせば、収益を生む資産に変えられる可能性があるからです。
例えば、初期投資を抑えられる駐車場経営やトランクルーム経営、あるいは自動販売機の設置など、土地の条件が悪くても始められる活用方法はさまざまです。
売却活動と並行して、土地活用の専門家に相談し、どのような可能性があるか検討してみるのがよいでしょう。
売れない土地をどうするべきかお悩みの方は専門家へご相談を

今回の記事では、土地が売れない理由と、その具体的な対処法について解説しました。
売れない土地を所有し続けるのは、精神的にも経済的にも大きな負担です。
しかし、見て見ぬふりをして放置すれば、状況は悪化する一方です。ご自身の土地がなぜ売れないのか、その原因を冷静に分析し、一つずつ対策を講じていく必要があります。
そして、「売る」だけが唯一の解決策ではありません。視点を変えれば、その土地は安定した収益を生む「宝の土地」に変わる可能性を秘めています。
もし、売れない土地の処分や活用方法にお悩みでしたら、土地活用の専門家にご相談ください。