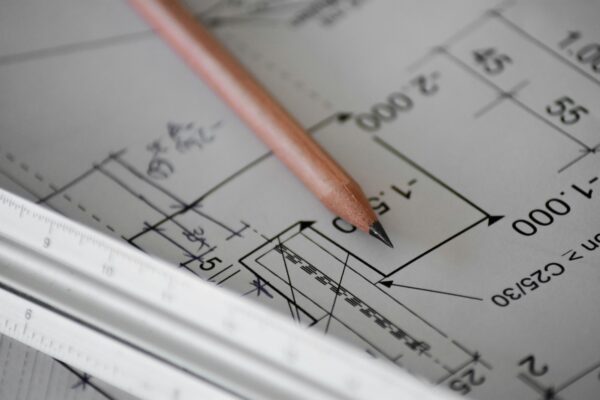農地とは?

土地活用を考える上で、まず「農地」の定義を理解しておきましょう。
農地とは、作物を育てるために使われる土地のことで、畑や田んぼがこれに該当します。
所有者の中には、もともと畑として利用していたものの、高齢化などを理由に現在は使えず放置している方や、相続で受け継いだものの、自分で耕作するのが難しいためそのままにしている、という方も少なくありません。
使われていない農地は「遊休農地」と定義されている
現在使われておらず、今後も利用される見込みのない農地は、農地法において「遊休農地」と定義されています。
具体的には、以下のいずれかに当てはまる土地が遊休農地と判断される可能性があります。
◯現在農地として使われておらず、今後も使われる見込みのない土地
◯周辺の他の農地と比べて、利用の程度が著しく劣っている土地
この遊休農地に認定されると、固定資産税の増加などのリスクが発生します。
遊休農地は今後社会問題となる可能性がある
日本の農地面積は、後継者不足による耕作放棄や、宅地・工場などへの転用を理由に年々減少し続けています。
農林水産省の資料によると、令和4年の農地面積は433万ヘクタールで、ピークだった昭和36年の約7割にまで落ち込んでいます。
今後も農地の減少が続けば、日本の食料自給率に深刻な影響を与える可能性もあるでしょう。
また、令和2年時点で遊休農地の面積は約28万ヘクタールにも及び、そのうち再生して再び農地として利用することが困難な土地が約19万ヘクタールを占めています。
【出典】農林水産省「農地法制をめぐる現状と課題」
そのため、国も再生が難しい遊休農地については、他の用途で活用する「非農地化」を推奨しているのが現状です。
畑(農地)の土地活用にあたって知っておくべき知識

畑を農地以外の目的で活用するには、必ず「農地法」と「都市計画法」という2つの法律の知識が必要になります。
これらの法律は、国の食料自給率を守るために、農地を勝手に他の用途へ変更できないように定めているものです。
それぞれの法律について詳しく解説します。
農地法
農地法は、優良な農地を確保するために、農地の売買や貸し借り、他の用途への変更(転用)を厳しく規制する法律です。
畑を農地以外の用途、例えば住宅地や駐車場として活用したい場合、原則として都道府県知事などから「農地転用許可」を得る必要があります。
ただし、すべての農地が転用できるわけではありません。農地は生産性の高さなどから区分されています。特に優良な農地である「農用地区域内農地」「甲種農地」「第1種農地」は、原則として転用が認められていません。
ご自身の畑がどの区分にあたるかわからない場合は、所在地の市町村にある農業委員会へ問い合わせて確認しましょう。
【出典】農林水産省「農地転用許可制度について」
都市計画法
都市計画法は、計画的な街づくりのために、土地を「市街化区域」と「市街化調整区域」などに区分する法律です。
この区分によって、農地転用のしやすさが大きく変わります。
「市街化区域」は、すでに市街地を形成している区域や、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
この区域内の農地は、事前に農業委員会へ届け出れば、比較的スムーズに転用が認められる傾向にあります。
一方で「市街化調整区域」は、市街化を抑制すべき区域とされており、原則として住宅や商業施設の建設は認められていません。
そのため、この区域にある畑の農地転用は、極めて難しいのが実情です。
また、都市計画法には「用途地域」が定められています。用途地域とは、土地を13種類のエリアに分類して、それぞれの用途地域で建てられる建物の種類に制限をかけるものです。住民の生活環境や利便性向上を目的に定められています。
土地活用を行う際には、これらのルールを守る必要があるのです。
畑を土地活用するメリット

手続きが必要な畑の土地活用ですが、成功すれば大きなメリットが得られます。
放置しているだけでは「負動産」になりかねない畑が、収益を生む優良な資産に生まれ変わる可能性を秘めているのです。
土地の資産価値が向上する
農地転用が許可されれば、その土地は「農地」から「宅地」などへと地目が変わり、さまざまな用途で利用できるようになります。
利用用途が住宅や商業施設、駐車場などに広がることで、土地の活用範囲が格段に広がります。
その結果、土地の評価額も農地としての評価から「宅地並評価」へと変わり、資産価値の向上が期待できるでしょう。
新たな収益源が発生する
農地のままでは農業以外での収益化は困難ですが、宅地などに転用すれば、アパート経営による家賃収入や、駐車場経営による利用料収入など、新たな収益源を生み出せます。
土地を売却するにしても、農地のままより宅地として売却するほうが、一般的に買い手が見つかりやすく、より高い価格での売却が可能です。
このように、土地活用は新たな収益機会の創出に直接つながります。
畑を土地活用せず放置する3つのリスク

使っていない畑をそのまま放置しておくことには、さまざまなリスクが伴います。
「何もしていないから損もない」と考えるのは間違いです。ここでは、放置することで生じる主な3つのリスクを解説します。
固定資産税が通常の農地より高くなる
遊休農地と判断された場合、固定資産税の負担が重くなる可能性があります。
通常の農地(畑)の固定資産税は、宅地などに比べて低く抑えられています。
しかし、耕作放棄され、市町村の農業委員会から「遊休農地」に関する勧告を受けると、税制上の優遇措置が受けられなくなり、固定資産税が約1.8倍に跳ね上がることがあるのです。
【出典】農林水産省「遊休農地の課税の強化」
農地としての価値が下がり再利用できなくなる
手入れされずに放置された畑は、雑草が生い茂り、土壌の状態が悪化していきます。害虫が発生したり、ゴミが不法投棄されたりするケースも少なくありません。
このような状態が長く続くと、再び農地として利用するのが困難になり、農地としての価値そのものが失われてしまいます。
元の状態に戻すには多額の費用がかかるため、放置は避けるべきです。
近隣の農家に迷惑がかかる可能性がある
放置された畑から発生した雑草の種が飛散したり、害虫が大量発生したりすると、隣接する農地にまで被害が及ぶ可能性があります。
また、野生動物の隠れ家となり、周辺の畑を荒らす鳥獣被害の原因となることもあります。近隣農家とのトラブルに発展する前に、適切な管理や活用を検討することが重要です。
畑を転用して土地活用するビジネスアイデア

農地転用の許可が得られた場合、その土地は一般的な土地と同じように、さまざまなビジネスに活用できます。
ここでは、代表的な5つのビジネスアイデアを紹介します。
アパート・マンション経営
畑が市街地や住宅街の近くにある場合、アパートやマンションを建てて家賃収入を得る方法が考えられます。
賃貸住宅経営は景気の影響を受けにくく、長期的に安定した収入源となるのが魅力です。
ただし、多額の建築費用が必要になるほか、入居者がいなければ収益にならない空室リスクも伴います。
駐車場経営
初期費用を抑えて手軽に始めたい場合、駐車場経営が選択肢となります。土地を舗装して区画線を引くだけで始められ、管理の手間も比較的少ないのが特徴です。
毎月定額の賃料を得る「月極駐車場」と、時間単位で貸し出す「コインパーキング」があり、立地や周辺のニーズに合わせて選べます。
トランクルーム経営
コンテナなどを設置し、収納スペースとして貸し出すトランクルーム経営も有効です。住宅街の近くでは、季節用品や趣味の道具などを保管したいという需要が期待できます。
運営方式には、自分で利用料を得る方法と、事業者に土地を貸して地代を得る方法があります。
ただし、屋外型のコンテナは気温や湿度の影響を受けやすいため、注意が必要です。
資材置き場
建設会社など、資材を置く場所を探している事業者に土地を貸す方法です。建物を建てる必要がなく、土地の広さや形、気候などが経営に影響しにくいのがメリットです。
大きな収益は期待しにくいですが、一度契約が決まれば長期的に安定した地代収入が見込めます。
周辺地域で資材置き場を探している事業者がいれば、有力な活用法となるでしょう。
太陽光発電
日当たりの良い広い土地であれば、太陽光パネルを設置して売電事業を行う選択肢もあります。
FIT制度(固定価格買取制度)を利用すれば、発電した電気を電力会社に一定期間、固定価格で買い取ってもらうことが可能です。
ただし、太陽光パネルの設置には数百万円単位の費用がかかるほか、自然災害による設備の故障リスクなども考慮する必要があります。
畑を農地転用できない場合のビジネスアイデア

「農用地区域内農地」に指定されているなど、農地転用が認められない場合でも、畑を活用する方法はあります。
「農地」として活用する、という視点でビジネスアイデアを探してみましょう。
農地を貸し出す
自分で耕作できない場合、農業をやりたいと考えている第三者へ農地を貸し出す方法があります。
その際におすすめなのが、農林水産省が推進する「農地中間管理機構(農地バンク)」の活用です。
農地バンクとは、都道府県、市町村、農業団体などが出資して組織された法人で、農地を貸したい人から農地を預かり、規模拡大を目指す農家や新規就農者など、農地を借りたい人へと貸し出す事業を行っています。
【出典】農林水産省「農地中間管理機構」
各都道府県に設置されており、安心して農地の貸し借りを行えます。
市民農園にする
農業に興味をもつ地域住民のために、畑を「市民農園」として活用する方法も人気です。
利用者に区画を貸して自由に作物を育ててもらう「貸付方式」と、園主の指導のもとで農作業を体験してもらう「農園利用方式」があります。
なお、貸付方式の場合は特定農地貸付法にもとづく手続きが必要となり、農業委員会への届け出が必要です。
都市部の住民には、土に触れ、自分で作物を育てる体験へのニーズが高まっています。地域の人々の憩いの場や交流の場にもなり、社会貢献にもつながる活用法です。
【出典】農林水産省「市民農園をはじめよう!!」
畑の土地活用でお困りなら専門家へご相談ください!

今回の記事では、畑の土地活用について、知っておくべき法律の知識から具体的なビジネスアイデアまで解説しました。畑は、一般的な土地活用でも関係してくる都市計画法以外にも、農地法が絡むため、複雑です。
しかし、農地転用が可能な場合はもちろん、転用が難しい場合でも、市民農園や農地バンクを活用するなど、収益化や社会貢献につなげられる可能性はあります。
大切なのは、ご自身の畑が持つ価値を正しく理解し、放置せずに最適な活用方法を見つけることです。そのためにも、まずは専門家に相談し、土地の状況を正確に把握することからはじめましょう。