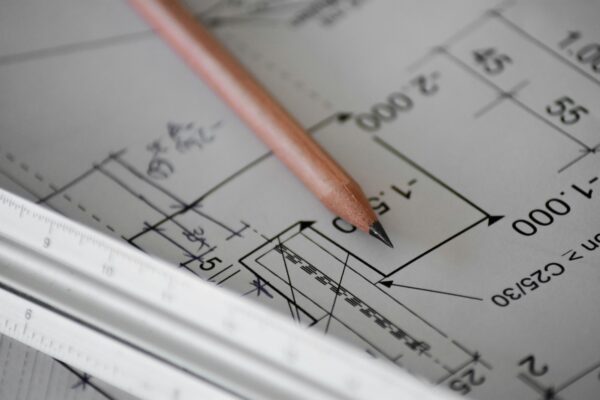クリニック誘致による土地活用とは?

クリニック誘致による土地活用とは、所有する土地にクリニック向けの建物を建てる、あるいは土地そのものを貸し出して、医師や医療法人に利用してもらい、賃料や地代を得る方法です。
地域住民の健康を支える医療施設は、景気の影響を受けにくく、一度開業すると長期間にわたって運営される傾向があります。
そのため、地主にとっては安定的かつ社会貢献にもつながる土地活用として、近年注目されています。
クリニックの定義と病院との違い
土地活用を検討する上で、まず「クリニック」と「病院」の違いを正しく理解しておく必要があります。
医療法において、病床(入院患者用のベッド)が19床以下の医療施設を「クリニック」、20床以上の医療施設を「病院」と明確に定義しています。
クリニックと病院の違いは、建築可能な「用途地域」にも大きく関わってくるため、非常に重要なポイントです。
また、クリニックを開業する主体は、医師個人が事業主となる「個人クリニック」と、理事が運営する「医療法人クリニック」の2種類に分けられます。地主として契約を結ぶ相手がどちらの形態なのかも、事前に把握しておくとよいでしょう。
土地活用でクリニック誘致する3つのメリット

土地活用でクリニックを誘致すると以下のメリットが得られます。
◯長期間の安定した収入が得られる
◯土地の有効活用かつ相続税対策にもなる
◯社会貢献につながる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
長期間の安定した収入が得られる
クリニックは、専門的な医療機器や内装設備に多額の初期投資が必要です。
そのため、一度開業すると頻繁に移転することは考えにくく、長期にわたって同じ場所で運営されるのが一般的です。
地主が土地を貸す「事業用定期借地契約」を結ぶ場合、契約期間は10年以上の長期にわたります。
また、建物を貸す場合でも、医師は投下した資本を回収するために、長期的な視点で事業計画を立てています。
このように、長期契約を前提としているため、地主は空室リスクを心配することなく、安定した収入を長期間にわたって確保できるのです。
土地の有効活用かつ相続税対策にもなる
クリニックとして土地活用を行うことは、有効な税金対策にもつながります。
土地の上に事業用の建物を建てて貸し出すと、その土地は「貸家建付地」として扱われ、更地の状態よりも相続税評価額が低くなります。
これにより、将来の相続時にかかる税金の負担を軽減可能です。
さらに、地主が建物を所有する「建て貸し方式」の場合、建物の建築費用は減価償却費として、毎年の不動産所得から経費として差し引けます。
これにより、所得税や住民税の節税も期待できるのです。
社会貢献につながる
日本は、いわゆる「2025年問題」に直面しており、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になることで、医療や介護の需要がますます増大すると予測されています。
地域にかかりつけ医となるクリニックが存在することは、住民の安心な暮らしに不可欠です。
特に、高齢者が多い地域や、特定の診療科が不足しているエリアでは、新しいクリニックの存在は非常に大きな意味をもちます。
土地を医療施設として提供することは、単なる収益事業にとどまらず、地域の医療インフラを支えるという高い社会貢献につながる、意義のある土地活用といえるでしょう。
土地活用でクリニック誘致する際の3つのデメリット

土地活用でクリニック誘致すると長期的に安定した収益が得られたり、社会貢献につながったりするなど多くのメリットがありますが、以下のデメリットも存在します。
◯借り手探しに苦労する可能性がある
◯病床を設置する際には届け出が必要になる
◯初期費用や運用コストの負担が大きくなる可能性がある
それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
借り手探しに苦労する可能性がある
クリニック誘致の最大のハードルは、借り手となる医師や医療法人を見つけることです。
借り手の候補が「開業や移転を考えている医師」に限られるため、母数が少ないのが実情です。
個人のネットワークだけで適切な医師を探し出すのは簡単ではありません。
そのため、医療機関や福祉施設とのつながりをもつ、土地活用の専門家に相談するのが成功への近道となります。
病床を設置する際には届け出が必要になる
クリニックに病床を設置する場合、さまざまな届け出が必要となり、手続きに手間がかかります。
入院用のベッドを有する医療施設は、建築基準法上の「特殊建築物」として扱われるため、建築前に建築確認申請を行い、厳しい耐火・防火措置などを講じる必要があるのです。
また、開業時には管轄の保健所に「診療所開設届」を、地方厚生局に「保険医療機関指定申請書」を提出するなど、多くの行政手続きが求められます。
初期費用や運用コストの負担が大きくなる可能性がある
クリニック誘致の際の契約方法のうち、後述する「建て貸し方式」を選ぶ場合、建物の建設費用は地主が負担するため、初期投資は数千万円からと高額になります。
また、建物のオーナーとして、将来のメンテナンス費用や毎年の固定資産税も負担しなければなりません。
ただし、「建設協力金方式」を利用すれば、開業する医師や医療法人から資金の一部を提供してもらえる可能性があります。
一方で、「土地貸し方式」なら初期費用はかかりませんが、地代収入しか得られないため収益性は低くなります。
クリニック誘致の3つの契約方式

クリニックを誘致する際には主に以下の3つの契約方式が存在します。
◯建て貸し方式
◯事業用定期借地(土地貸し)方式
◯テナント貸し方式
誰が建物を建てるのか、初期費用を誰が負担するのかによって、収益性やリスクが大きく変わります。それぞれの契約方式の特徴について詳しく解説します。
建て貸し方式
建て貸し方式は、地主が自己資金やローンでクリニック用の建物を建築し、完成した建物を医師や医療法人にテナントとして貸し出す方式です。
地主が建築費を負担するため初期費用は高額になりますが、その分、土地だけを貸すより高い賃料を設定でき、収益性は高くなります。
ただし、万が一テナントが退去した場合の空室リスクは、地主が負うことになります。
建築会社によっては、空室時の賃料を保証してくれる「一括借上システム」を用意している場合もあるため、検討してみるのもよいでしょう。
事業用定期借地(土地貸し)方式
事業用定期借地方式は、土地を更地のまま貸し出し、借主である医師や医療法人が自らの費用で建物を建てる方式です。
地主は建物の建築費用を負担する必要がなく、初期費用をほとんどかけずに始められるのが最大のメリットといえます。
契約期間は借地借家法に基づき10年以上50年以下で設定でき、契約終了後は更地で土地が返還されるため、将来的な計画も立てやすいです。
ただし、得られる収益は地代収入のみとなるため、建て貸し方式に比べると収益性は劣ります。
テナント貸し方式
すでに所有している建物を改装し、クリニック用に貸し出す方式です。
建物を新築する必要がないため、初期費用は内装のリフォーム代程度で済み、建て貸し方式と比べるとハードルも低いです。
ただし、医師にとっても開業や移転のハードルが低い分、より良い条件の物件が見つかれば移転してしまう「撤退リスク」が他の方式より高い点には注意しましょう。
クリニック誘致による土地活用を成功させる3つのポイント

クリニック誘致を成功させ、長期的に安定した事業として成り立たせるためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
◯土地の条件やニーズを把握しておく
◯法規制について理解する
◯土地活用のプロに相談する
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
土地の条件やニーズを把握しておく
土地活用を始める前に、まずは自分の土地がクリニック経営に向いているかを見極める必要があります。
土地の広さや形状、駅からの距離や駐車場の確保のしやすさといった物理的な条件が重要です。
同時に、その地域にどのような医療ニーズがあるのかを調査しましょう。
例えば、周辺にどのような医療施設がすでにあるのか、住民の年齢層から考えて、小児科や内科、整形外科など、どの診療科が不足しているのか、といった視点です。
近隣に同じような診療科の大規模な病院がある場合、患者の集客が難しく、誘致が成功しない可能性もあります。
法規制について理解する
クリニックの建築には、さまざまな法規制が関わってきます。
特に重要なのが、前述した「病院」との違いによる用途地域の制限です。
病床が19床以下のクリニックは、基本的にどの用途地域でも建築可能です。(各自治体の条例で定めがある場合を除く)
しかし、病床が20床以上の「病院」となると、第一種低層住居専用地域や工業専用地域などでは建築できません。
なぜなら、第一種低層住居専用地域は、低層向けの静かで良好な住宅環境を守るための用途地域だからです。お店など一部の施設は建てられますが、建物の高さに制限がかかります。
また、工業専用地域は、工場のために用意された用途地域です。どんな工場でも建てられますが、工場以外の多くの施設建築は建築できません。
病院を建てられる用途地域は、主に以下の8つに定められています。
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
【出典】東京都市整備局「用途地域による建築物の用途制限の概要」
その他にも、消防法やバリアフリー法、各自治体が定める条例など、遵守すべき規制は多岐にわたります。
土地活用のプロに相談する
クリニック誘致は、一般的な土地活用以上に専門的な知識が求められます。
法規制のチェックや地域の医療ニーズの分析、そして何より重要な開業医探しなど、個人で全てを行うのは非常に困難です。
土地活用のプロに相談すれば、これらの複雑な問題を解決し、事業計画の立案からサポートしてもらえます。
特に、地域の医療事情に精通し、開業を希望する医師とのネットワークをもつ専門家は、成功に不可欠なパートナーとなるでしょう。
クリニック誘致による土地活用を成功させるなら専門家へご相談してみてはいかがでしょうか

今回の記事では、クリニック誘致による土地活用の方法について解説しました。
クリニック誘致による土地活用は、事業用定期借地契約を結ぶのが一般的であるため、非常に長期にわたって安定した収入が得られたり、高齢化社会に突入していく今後の日本において、社会貢献につながったりもします。
しかし一方で、誘致先が見つかりにくい、建て貸し方式の場合は莫大な建築コストが発生するなどのデメリットもあります。
さらに、用途地域や建築基準法などの法規制について理解しておくことも必要です。
クリニック誘致を成功させるためには、専門知識や信頼できるパートナーとの出会いが欠かせません。
土地活用で失敗したくない、クリニック誘致について適切なサポートを受けたいといった方は、ぜひ一度専門家にご相談ください。