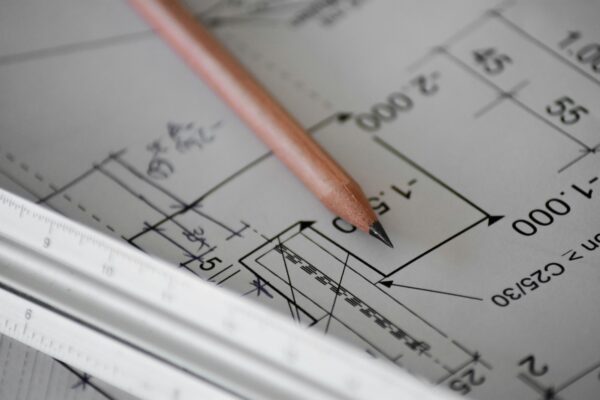再建築不可物件とは?

まず、ご自身が所有する物件がなぜ「再建築不可」なのか、その理由と特徴を正しく理解しましょう。理由や特徴についてそれぞれ解説します。
土地の立地や形状の問題で建て直しができない物件
「再建築不可物件」とは、現在建っている建物を取り壊して更地にした後、新たに建物を建てることが法律で認められない物件を指します。その主な原因は、建築基準法で定められた「接道義務」を満たしていないことにあります。
接道義務とは、建物を建てる敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」ルールです。
これは、火災時の消防活動や救急車の乗り入れなど、安全確保のために定められています。この条件を満たせない土地に建っている家は、一度取り壊すと二度と建て替えができません。
昔は適法に建てられた建物でも、その後の法改正や周辺環境の変化により、現在の建築基準法に適合しなくなった「既存不適格建築物」が、再建築不可物件となっているケースが多く見られます。
再建築不可物件の特徴
活用が難しいとされる再建築不可物件ですが、その特性からくる意外な特徴もあります。
一つは、固定資産税や相続税評価額が低く抑えられる傾向にある点です。不動産の資産価値は、建て替えが可能かどうかに大きく左右されます。
再建築不可物件は、一般的な不動産に比べて市場価値が低く評価されるため、それに連動して固定資産税評価額も低くなります。
相続税は、固定資産税評価額を基に計算されるため、結果的に相続税の負担も軽くなる可能性があるのです。
これは、所有し続ける上での数少ないメリットといえるかもしれません。
再建築不可物件を活用せず放置する4つのリスク

活用が難しいからといって、再建築不可物件をそのまま放置し続けると、多くのリスクが伴います。問題から目をそらさず、どのようなリスクがあるのかを理解しましょう。
建て替えできない
最も直接的で大きなリスクは「建て替えができない」事実そのものです。
「古くなったからデザインを一新して住みやすくしたい」「家族構成が変わったから間取りを変えたい」と思っても、新築に建て替えできません。
さらに深刻なのは、火災や地震、台風といった自然災害で建物が倒壊・半壊してしまった場合です。たとえ被災して住めなくなったとしても、原則として同じ場所に家を建て直すのは許可されません。
大切な資産がある日突然、ただの「建物を建てられない土地」になってしまうリスクを常に抱えているのです。
老朽化が原因で倒壊の可能性がある
再建築不可物件の多くは、建築基準法が現在のように厳しくなる1950年以前に建てられた古い建物です。そのため、建物の老朽化が著しく進んでいるケースが少なくありません。
耐震基準も現在のものとは異なるため、地震などの自然災害によって倒壊する危険性が非常に高い状態です。
万が一、所有する建物が倒壊し、隣家を損壊させたり、通行人に怪我を負わせたりした場合、その責任はすべて所有者が負います。(民法第717条第1項)
多額の損害賠償を請求される可能性もあり、放置は極めて危険な行為といえます。
【出典】e-Gov法令検索「民法」
固定資産税がかかり続ける
再建築不可物件は資産価値が低いとはいえ、不動産である以上、所有している限り毎年固定資産税と都市計画税の支払い義務が発生します。
「建物が古くて危ないから、いっそ解体して更地にしてしまおう」と考えるのは早計です。土地の上に住宅が建っている場合、「住宅用地の特例」によって固定資産税が最大で6分の1に軽減されています。
しかし、建物を解体して更地にすると、この特例が適用されなくなり、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がってしまうのです。活用計画がないまま更地にすると、税金の負担だけが重くのしかかります。
売却しにくくなる
活用もできず、所有し続けるのも困難だからと売却を考えても、一筋縄ではいきません。
前述のとおり、再建築不可物件は倒壊のリスクを抱え、活用方法も限られるため、一般の買い手を見つけるのは困難です。
さらに、金融機関は不動産を担保にして住宅ローンを融資しますが、担保価値が著しく低い再建築不可物件は、住宅ローンの審査が通りにくいです。
これにより、買い手が現金での購入者に限定されてしまうため、売却のハードルはさらに高くなります。
再建築不可物件を活用するための4つの裏ワザ

絶望的に思える再建築不可物件ですが、状況を打開し、建て替え可能な土地として再生させるための「裏ワザ」ともいえる方法がいくつか存在します。
隣地の一部を買い取る
再建築不可となる最も多い原因は、敷地が道路に接する幅が2m未満だからです。
この場合、隣地の所有者に交渉し、間口が2m以上になるように隣地の一部を買い取らせてもらえば、接道義務を満たし、再建築が可能になります。
もちろん、隣地の所有者が売却に必ず応じてくれるとは限りませんし、価格交渉も必要です。個人間の不動産売買はトラブルの原因になりやすいため、必ず不動産会社などの専門家を仲介させ、慎重に話を進めましょう。
旗竿地の場合は隣地と等価交換する
ご自身の土地が、道路に接する間口が狭く、奥に敷地が広がっている「旗竿地」の場合、隣地の土地とご自身の土地の一部を等価交換する方法も有効です。
例えば、ご自身の土地の奥まった部分と、隣地の道路に面した部分を同じ価値(面積)で交換すれば、費用をかけずに接道義務を満たせる可能性があります。
土地と土地など、同じ種類の固定資産を交換した場合は「固定資産の交換の特例」が適用され、譲渡所得税がかからない税制上のメリットもあります。
【出典】国税庁「No.3502 土地建物の交換をしたときの特例」
セットバックする
敷地は道路に面しているものの、その道路の幅員が4m未満であるために再建築不可となっているケースもあります。この場合は「セットバック」を行えば再建築が可能になります。
セットバックとは、道路の中心線から2mの位置まで、ご自身の敷地を後退させることです。後退させた部分は道路とみなされるため、その分敷地面積は小さくなりますが、残った敷地部分で建築基準法に適合した建物を建てられます。
ただし、敷地面積が狭くなるデメリットは受け入れなければなりません。
43条ただし書許可を申請する
上記の方法が取れない場合でも、最後の手段として「43条ただし書許可」という制度があります。
これは、建築基準法第43条の規定により、接道義務を満たさない土地でも「周辺に広い空き地があるなど、安全上・防火上問題がない」と特定行政庁(都道府県や市など)が認め、建築審査会の同意を得られれば、例外的に建築を許可するものです。
申請には詳細な図面や書類が必要で、必ず許可が下りる保証はありませんが、検討する価値のある制度です。
【出典】国土技術政策総合研究所「5. 43条ただし書許可」
再建築不可物件の活用方法

「裏ワザ」が使えず、建て替えができない場合でも、既存の建物を活かしたり、土地の状態を変えたりして、収益化を図る方法があります。
リフォームして自分が住む
最もシンプルでコストを抑えられるのが、大規模なリフォームやリノベーションを行い、ご自身が居住する方法です。
建て替えはできませんが、建物の基礎部分を残したままであれば、内装や外装、設備を新しくするのは可能です。
人に貸すわけではないので、ご自身が快適に暮らせる範囲での工事で済みますし、何より住むことで建物の状態を常に把握でき、老朽化によるリスクを管理しやすくなります。
固定資産税が安いメリットを享受しながら、コストを抑えて住まいを確保できます。
戸建賃貸住宅経営
ご自身が住む予定がない場合は、リフォームして戸建賃貸住宅として貸し出せば、毎月安定した家賃収入を得られます。
入居者に快適に住んでもらうため、水回りなどを含めたフルリフォームが必要になる場合が多く、初期投資はかかりますが、古民家の雰囲気を活かしたお洒落なリノベーションは若い世代からも人気があります。
駐車場経営
建物を取り壊して更地にし、駐車場として活用する方法です。初期投資が少なく、管理の手間も比較的かからないのがメリットです。
ただし、前述のとおり更地にすると固定資産税が大幅に上がるリスクがあるため、駐車料金の収入で税金や維持費を十分に賄えるか、事前の収支計算が欠かせません。
また、接道している道路が狭い場合は、停められる車種が軽自動車などに限定される場合もあります。
売却する
どうしても活用方法が見つからない、管理する手間や費用を負担し続けられないなどの場合は、売却するのも一つの賢明な判断です。
一般の買い手を見つけるのは困難ですが、再建築不可物件を専門に扱う不動産買取業者であれば、適正な価格で買い取ってくれる可能性があります。
そのまま放置して資産価値がさらに下がる前に、専門家への相談をおすすめします。複数の業者に査定を依頼し、納得のいく条件で手放しましょう。
再建築不可物件を活用する前の注意点

再建築不可物件の活用に踏み出す前に、いくつか注意すべき点があります。焦って行動すると、取り返しのつかない失敗につながる可能性があります。
更地にする場合は活用方法が決まってから
絶対に覚えておかなければならないのは、一度更地にしてしまうと、原則として二度と建物は建てられない点です。
駐車場経営やコンテナハウスの設置など、更地にすることを前提とした活用法を検討する場合は、その計画が本当に実現可能で採算が取れるのかを徹底的に調査してください。専門家とも相談したうえで最終的なプランが固まってから解体工事に着手しましょう。
安易に更地にすると、固定資産税が6倍に跳ね上がり、後悔する原因になります。
すでに更地の場合は再建築不可の原因を取り除く
相続した時点ですでに更地だったケースもあるでしょう。この場合は、まず「なぜその土地が再建築不可なのか」を正確に突き止めるのが最優先です。
法務局で公図や登記事項証明書を取得したり、役所で道路の状況を確認したりして、接道義務を満たしていないのか、道路の幅員が足りないのかを把握します。
そのうえで、隣地の買収やセットバックといった、原因を取り除くための対策を検討するのが、活用の第一歩です。
土地活用の専門家に相談する
再建築不可物件の活用は、建築基準法や民法、税法といった専門的な知識が複雑に絡み合います。個人の判断だけで最適な解決策を見つけ出すのは非常に困難です。
「この土地は本当に再建築できないのか」「どんな活用方法がベストなのか」といった悩みは、一人で抱え込まず、早い段階で土地活用の専門家である建設会社や不動産会社に相談するのが、成功への最短ルートです。
豊富な経験を持つプロならではの視点で、思いもよらない解決策が見つかるかもしれません。
まとめ:再建築不可物件の活用にお困りの方は専門家へご相談ください!

今回の記事では、再建築不可物件の定義から、放置するリスク、そして具体的な活用方法までを詳しく解説しました。
再建築不可物件は、多くの制約を抱えている一方で、正しい知識とアプローチによって、価値ある資産へと生まれ変わらせられます。
「建てられないから価値がない」と諦めてしまう前に、その土地に秘められた可能性を探ってみることが重要です。
「自分の土地が再建築不可物件だがどうすればよいかわからない」
「活用したいが、何から手をつければいいのか見当もつかない」
もしこのようにお困りでしたら、一度土地活用の専門家に相談することをおすすめします。土地活用の専門家であれば、再建築不可物件についてのノウハウを持っているため、ご自身の土地に合った活用方法をサポートしてくれます。
活用が難しい再建築不可物件ですが、価値ある資産として活かすためにも、本記事を参考にして前向きに計画を進めていきましょう。