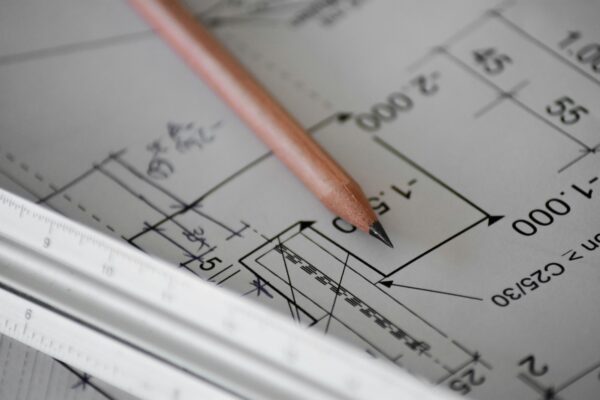遊休地とは?定義や遊休土地との違いを解説

地主の方にとって「遊休地」という言葉はよく耳にしても、その正確な意味や似た言葉である「遊休土地」との違いについては、あまり知られていないかもしれません。
土地活用を検討する第一歩として、まずはこれらの言葉の定義を正しく理解しましょう。
遊休地とは「所有しているが使用していない土地」を指す
遊休地とは、一般的に「所有はしているものの、長期間にわたって活用されることなく放置されている土地」を指す不動産用語です。
例えば、親から相続したものの遠方に住んでいるため管理できない実家の土地や、将来家を建てるつもりで購入したが計画が変わって長らく更地のままになっている土地などが該当します。
土地だけでなく、誰も住んでいない空き家などの建物が含まれる場合は「遊休不動産」とよばれることもあります。
遊休地と遊休土地の違い
遊休地とよく似た言葉に「遊休土地」があります。このふたつは混同されがちですが、実は明確な違いがあります。
「遊休土地」は、国土利用計画法で定められた法律用語です。
具体的には、取得後2年以上活用されていない一定規模以上(市街化区域内で1,000㎡以上など)の土地のうち、都道府県知事から活用の勧告を受けた土地を指します。
通知を受けた所有者は、6週間以内にその土地の活用計画や売却計画を知事に届け出る義務が生じます。
つまり、一般的な「遊休地」の状態を放置し続けると、法律に基づく「遊休土地」として行政指導の対象になる可能性があるのです。
【出典】国土交通省「遊休土地制度」
遊休地が社会問題になっている
活用されていない遊休地は、個人の資産の問題だけでなく、日本全体が抱える社会問題にもなっています。
国土交通省の資料によると、地方や郊外を中心に空き家や空き地が増加し続けており、世帯が所有する空き地は2008年から2018年までの10年間で約2倍に増加しているデータも出ています。
なお、空き地の所有者については、世帯主の年齢別にみると、65歳以上の世帯が保有する割合は1993年には25%だったのが、2018年には60%まで増加しており、今後も増加していくことが予想されます。
【出典】国土交通省「増加する空き地の現状について」
放置された遊休地は、雑草の繁茂や害虫の発生、ゴミの不法投棄などを招き、周辺の景観や生活環境を悪化させてしまうのです。
また、管理不全の空き家は、地震や台風による倒壊、不審火や放火といった防災・防犯上のリスクも高まります。
このような理由から、国や自治体は遊休地の活用を重要な政策課題として位置づけているのです。
【出典】国土交通省不動産・建設経済局土地政策課「空き地等の新たな活用」
遊休地活用による4つのメリット

遊休地を放置することには多くのリスクがありますが、逆に活用すれば以下のメリットが得られます。
継続的な収入源を確保できる
税金面の負担が減る
社会貢献につながる
将来的に転用もできる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
継続的な収入源を確保できる
遊休地を土地活用すれば、継続的な収入源の確保が可能です。
例えば、アパートやマンションを建てて家賃収入を得たり、駐車場として貸し出して利用料を得たりと、その土地に合った事業を行えば、長期にわたって安定した収入が得られます。
税金の支払いなど、これまで支出の原因でしかなかった土地が、家計を支える頼もしい資産に変わる可能性があるのです。
税金面の負担が減る
土地は所有しているだけで、毎年固定資産税や都市計画税がかかります。
しかし、土地活用を行うことで、税金の負担を軽減可能です。
例えば、更地にアパートなどの住宅を建てると「住宅用地の特例」が適用され、土地の固定資産税が最大で6分の1まで減額されます。
また、相続税対策としても有効で、更地のまま相続するよりも、上に建物を建てて貸し出している「貸家建付地」として相続するほうが、土地の評価額を下げられます。
社会貢献につながる
遊休地の活用は、個人の利益だけでなく、地域社会への貢献にもつながります。
例えば、地域に不足している駐車場や、高齢化社会を支える福祉施設を建設すれば、住民の生活の利便性や安全性を高められるでしょう。
また、放置されて荒れていた土地を整備して活用すれば、街の景観を美しく保ち、地域の活性化にも貢献できます。
所有する土地を通じて地域に貢献できる点は、大きなやりがいのひとつです。
将来的に転用もできる
土地活用は、一度始めたら他の用途に変更できないわけではありません。
特に、初期投資が少なく、建物を建てない活用方法を選べば、将来の選択肢を広く残しておけます。
例えば、最初は転用しやすい駐車場として活用し、数年後、自分の子どもが家を建てるための土地として利用する、といった柔軟な計画が可能です。
将来のライフプランの変化に対応しやすい点も、遊休地活用のメリットといえるでしょう。
遊休地活用事例には主に4つのパターンがある

遊休地の活用方法、いわゆる「活用事例」は数多くありますが、そのビジネスモデルは以下の4つに分類されます。
借家ビジネス
自営ビジネス
借地ビジネス
暫定利用ビジネス
それぞれのパターンがどのような特徴をもつのかを理解できれば、ご自身の目的やリスク許容度に合った方法が見つけやすくなります。
なお、具体的な活用アイデアについては以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
【関連記事】
遊休地のおすすめ活用方法!お金を生むために知っておきたい事前知識
借家ビジネス
土地の上にアパートやマンション、戸建て住宅などを建て、入居者に貸し出して家賃収入を得るパターンです。土地活用と聞いて、多くの方が最初にイメージする方法かもしれません。
高い収益性が期待できる一方で、多額の建築費用がかかるため、金融機関からの借り入れが必要になるケースがほとんどです。
空室リスクや建物の維持管理コストも考慮する必要がある、ハイリスク・ハイリターンな活用法といえます。
自営ビジネス
自分で建物を建て、自ら事業を運営するパターンです。
例えば、コインランドリーやトランクルーム、高齢者向け施設などを自分で経営します。
事業が軌道に乗れば大きな収益が期待できますが、借家ビジネス以上に経営に関する知識やノウハウが求められます。
設備の導入費用や運営コストも全て自己負担となるため、相応の覚悟が必要な上級者向けの活用法です。
借地ビジネス
建物を建てずに、土地そのものを事業者に貸し出して地代を得るパターンです。
「事業用定期借地権」という契約を結ぶのが一般的で、契約期間が終了すれば、土地は更地になって戻ってきます。
土地の所有者は初期費用をほとんどかける必要がなく、管理の手間もかからないのが最大のメリットです。
収益性は他の方法より低いですが、リスクを抑えて堅実に収入を得たい方に向いています。
暫定利用ビジネス
土地に大規模な投資をせず、ほぼそのままの形で「暫定的に」活用するパターンです。駐車場経営や、建設会社などへの資材置き場としての貸し出しがこれにあたります。
少ない初期費用でスピーディーに始められ、他の用途への転用がしやすいのが特徴です。
将来的にその土地を自分で使いたい、あるいは売却したいといった計画がある場合に適した、柔軟性の高い活用法です。
遊休地活用事例を参考にするうえでの注意点

インターネットなどでさまざまな遊休地活用事例を目にすると「自分の土地でも同じように成功できるのでは」と期待が膨らむかもしれません。
しかし、他人の成功事例を参考にする際には、失敗を避けるためにも以下の注意点を押さえておく必要があります。
用途地域などの法規制について理解する
土地の広さや形状も考慮する
周辺環境のニーズ調査も行う
それぞれの注意点について詳しく解説します。
用途地域などの法規制について理解する
土地活用を考える上で、最も重要なのが法律による規制です。
土地には「都市計画法」によって、建てられる建物の種類や規模が厳しく定められた「用途地域」という区分があります。
例えば、閑静な住宅街である「第一種低層住居専用地域」では、原則として店舗や事務所を建てることはできません。
また、市街化を抑制する「市街化調整区域」では、そもそも建物の建築自体が困難です。どのような活用事例であっても、この法規制をクリアしなければ実現は不可能です。
土地の広さや形状も考慮する
当然ながら、土地の広さや形によって、適した活用方法は異なります。
例えば、アパート経営や福祉施設の運営には、ある程度のまとまった広さの土地が必要です。
一方で、狭かったり、形がいびつだったりする「狭小地」や「変形地」では、大規模な建物を建てるのは難しいでしょう。
その場合は、駐車場やトランクルームといった、土地の形状に柔軟に対応できる活用法が選択肢となります。
周辺環境のニーズ調査も行う
どのようなビジネスであっても、そこに需要がなければ成り立ちません。土地活用を始める前に、必ず周辺環境のニーズ調査を行いましょう。
例えば、学生や単身者が多いエリアであればアパート経営に勝機があるかもしれません。
一方で、商業施設が近くにあれば、駐車場や店舗の需要が高いと考えられます。
成功事例を鵜呑みにせず、ご自身の土地がもつ独自のポテンシャルと、地域のニーズを客観的に分析することが重要です。
遊休地活用事例をもとに土地活用を進めるなら専門家へご相談を!

遊休地の活用事例にはさまざまなパターンがありますが、どの方法を選ぶにしても、専門的な知識と客観的な視点が不可欠です。
「自分の土地に合った活用事例が知りたい」
「法規制や周辺のニーズを、どうやって調べればいいかわからない」
そのようなお悩みをお持ちでしたら、土地活用の専門家にご相談ください。専門家に相談すれば、資金シミュレーションや事業計画の立案、土地周辺のニーズ調査など、土地活用に関するさまざまなサポートを受けられます。
今回の記事をぜひ参考にしていただき、第二の収益源を作ったり、税金対策や社会貢献をしたり、ご自身の所有している遊休地を価値ある資産として活用しましょう。