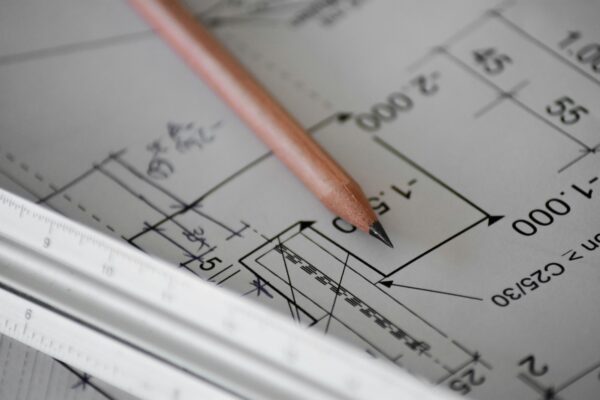借地による土地活用とは?

借地による土地活用とは、自分の土地を第三者に貸して地代収入を得る方法です。
借地による土地活用の方法はいくつかありますが、例えば、更地をそのまま貸す場合は建物の建設や運営管理も借主が担当するため、地主の負担が少ない点が特徴です。
借地としての土地活用は、大切な土地をを手放さずに活用したい方や、将来の相続を見据えて資産を維持したい方にとっても有効な方法となります。
土地貸しをする際に重要なのが「借地権の種類」です。
借地権には「普通借地権」と「定期借地権」があり、定期借地権はさらに3つの種類に分類されます。
まずは、それぞれの借地権の違いについて以下で解説していきます。
普通借地権と定期借地権の違い
借地による土地活用を行う前に、借地権について知っておく必要があります。
以下の表で、普通借地権と3つの定期借地権の主な違いを簡潔にまとめました。
【それぞれの借地権の違い】
| 借地権の種類 | 契約期間 | 利用目的 | 更新の有無 | 契約方法 | 特徴 |
| 普通借地権 | 30年以上 | 用途制限なし | あり | 制約なし(口頭OK) | ①法定更新される ②更新拒否には相当の理由が必要 ③建物買取請求権がある ④建物買取請求権が行使されれば建物はそのまま土地は返還されるが借家関係は継続する |
| 一般定期借地権 | 50年以上 | 用途制限なし | なし | 書面(公正証書等) | 契約終了時に土地が更地で返還される |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | 事業用建物(居住用は不可) | なし | 書面(公正証書) | 契約終了時に土地が更地で返還される 事業用建物に用途が限定される |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 用途制限なし | 建物買取で契約終了 | 書面推奨(口頭OK) | ①建物は地主が買い取る ②建物はそのままで土地を返還する ③借地人または借家人は継続して借家として住める |
【出典】国土交通省 定期借地権の解説(2)定期借地権の種類
普通借地権と3つの定期借地権についてそれぞれの特徴を解説します。
普通借地権
普通借地権とは、契約の更新を前提とした借地権です。契約期間満了後も借主が更新を希望すれば、原則として契約は自動的に更新されます。
貸主が契約の更新を拒否するには「正当な理由」が必要とされ、その条件を満たさなければ契約は継続されます。
結果として、土地が半永久的に返ってこないリスクがある点が最大のデメリットです。
普通借地権には「建物買取請求権」も認められています。建物買取請求権とは、契約終了時に借主が地主に建物の買取を請求できる権利であり、貸主側は原則拒否できません。
そのため、最終的に地主側に大きな金銭的負担が発生する可能性もあります。
一般定期借地権
一般定期借地権とは、契約期間が50年以上と定められた借地契約です。契約時に「契約の更新をしない」「存続期間の延長をしない」「建物の買取請求をしない」の三つの特約を公正証書等の書面で交わす必要があります。
原則として土地が必ず返還されるため、将来の相続や売却を見据えた土地活用に向いています。
事業用定期借地権
事業用定期借地権とは、契約期間が10年以上50年未満で、店舗やオフィスなど事業用の建物を建てることを目的とした借地契約です。契約には「契約の更新をしない」「存続期間の延長をしない」「建物の買取請求をしない」の特約を盛り込み、公正証書での契約が必要です。
事業用定期借地権を利用すれば、土地の返還時期が明確になり、更地で返還されるため、将来的な活用計画も立てやすくなります。
例えば、将来的に売却や相続を予定している土地を、一時的に安定収入源として活用したいときに適しています。
建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権とは、契約時に建物を30年以上利用した後、相当の対価で地主へ譲渡することを約束する借地契約です。建物を解体せずに土地を明け渡せるため、借主・貸主の双方にとって柔軟な対応が可能になります。
例えば、店舗として30年間活用した建物を地主へ譲渡し、その後も賃貸借契約を結んで使用し続けることも可能です。
契約は口頭でも有効とされていますが、将来のトラブルを防ぐためにも書面で明文化するのが望ましいです。
借地による土地活用は定期借地権がおすすめ
借地での土地活用を考える際は、定期借地権の利用がおすすめです。
理由としては、契約期間満了と同時に土地が確実に返ってくるからです。
また、普通借地権と違い、借主から建物を買い取る義務が発生せず、将来的なトラブルを回避しやすくなります。
具体的には、以下のような特徴があります。
更新がなく、契約終了後に土地が更地で戻る
建物買取請求が発生しないため、借主とのトラブルを避けられる
再活用や売却、相続時の柔軟性が高い
将来的に土地を別の用途に使いたい、子世代に継承したいと考えている地主には、とても相性のよい活用方法です。
借地で土地活用する7つのメリット

借地を活用することで、以下の7つのメリットが得られます。
◯初期投資がかからない
◯長期的に安定した収入が得られる
◯リスクが少ない
◯地代を前払いで受け取れる
◯管理の手間が少ない
◯固定資産税を抑えられる
◯相続税対策になる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
初期投資がかからない
借地による土地活用の魅力は、大きな自己投資をかけずに始められる点です。
建物の建設や管理は借主が対応するため、地主は自己資金や融資の手続きをせずに済みます。アパート経営のように数千万円単位の資金が必要になるケースと比べても、経済的負担は大幅に抑えられます。
そのため借地での土地活用は、まとまった資金が手元にない方でも取り組みやすく、ハードルの低い方法です。
長期的に安定した収入が得られる
借地契約は、長期にわたり安定した収入を見込める点が強みです。
定期借地権の契約は基本的に30年、50年といった長期間にわたるため、期間中は毎年安定した地代が入ります。契約が定期であるため、急な中途解約のリスクも少なく、将来的なトラブルも回避しやすいです。
中途解約は借主と貸主のどちらかが一方的に行うことはできず、当事者間での合意が必要になったり、あらかじめ契約に中途解約条項を盛り込んでおく必要があったりします。
使っていない土地を放置するよりも借地として貸し出すほうが、第二の収入源にもつながり、安定した収入を得られるためおすすめです。
リスクが少ない
借地は、手間や金銭的なリスクを最小限に抑えて土地活用したい方に向いています。
例えば、建物に関する費用や管理は借主側の責任となるため、地主自身がトラブルに巻き込まれる可能性は低いです。
万が一、借主の事業が失敗しても、地主が建物の運営リスクを負うこと自体はありません。
そのため、リスクを最小限にしつつ、なんらかの方法で土地活用したい方は借地として土地を貸し出すことをおすすめします。
地代を前払いで受け取れる
資金を早めに確保したい方には「前払地代方式」という方法があります。
前払地代方式とは、定期借地権の契約時に契約期間分の賃料を一括で受け取る仕組みです。
例えば50年契約の場合、その50年分の地代を最初にまとめて受け取ることが可能です。
実際の会計処理では、受け取った地代を毎年均等に収益として計上することで、年度ごとの課税額を分散できます。
その結果、税負担の集中を避けつつ、手元資金を早期に活用できる点が利点です。
管理の手間が少ない
借地契約では、建物や設備の維持管理を借主が担当するため、地主の管理負担は少ないです。
例えば、修繕の対応や入居者とのトラブル処理といった日常の管理業務も借主側で対応するため、地主は関与する必要がありません。
また、建物が借主の所有物となることで、管理責任も明確になり、地主側に余計なリスクが及ぶことも少なくなります。
本業が忙しい方や遠方に土地を所有している方にとって、借地は非常に効率的な土地活用手段といえます。
固定資産税を抑えられる
借地として土地を住宅用に貸すと、借主が住宅を建てた際に「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税の評価額が軽減されます。
| 区分 | 固定資産税 | 都市計画税 | |
| 空き地(更地) | 建物がない状態 | 課税標準の1.4% | 課税標準の0.3% |
| 小規模住宅用地 | 住宅1戸につき200㎡まで | 課税標準の6分の1 | 課税標準の3分の1 |
| 一般住宅用地 | 住宅1戸につき200㎡まで | 課税標準の3分の1 | 課税標準の3分の2 |
【出典】NPO法人 空家・空地管理センター「空き家と住宅用地の特例措置」
空き地として所有している場合に比べ、税額が低く抑えられるため、毎年の固定資産税が重荷となっている土地でも費用負担を軽減できます。
相続税対策になる
借地による土地活用は、相続税対策としても効果的です。
土地を第三者に貸していると、その土地は「貸宅地」として評価されます。貸宅地は通常の自用地に比べて評価額が低く見積もられるため、相続発生時に課税対象となる資産額が抑えられるのです。
相続税の減額割合は、定期借地権の残存期間によって変動します。
| 残存期間が5年以下のもの | 5% |
| 残存期間が5年を超え10年以下のもの | 10% |
| 残存期間が10年を超え15年以下のもの | 15% |
| 残存期間が15年を超えるもの | 20% |
【出典】国税庁「No.4613 貸宅地の評価」
※上記は全国一律でなく地域によって異なる場合があります。
借地による活用を検討すれば、資産維持と税負担軽減の両立を目指せます。
借地による土地活用の3つのデメリット

借地による土地活用には多くのメリットがありますが、以下のようなデメリットも存在します。
家賃収入などと比べると収益性が低い
契約期間中は他の用途で土地を使えない
普通借地契約にすると土地が返ってこないリスクがある
それぞれのデメリットについて詳しく解説します。
家賃収入などと比べると収益性が低い
借地による土地活用は、運用の手間や初期投資のコストをかけずに安定した収入を得られる点が強みです。
一方で、建物を自分で所有・運用するアパート経営で得られる家賃収入に比べて、地代収入は控えめになります。
そのため、毎月の高収益を期待する方にとっては、物足りなさを感じるかもしれません。
同じ土地を活用する場合を比較してみましょう。
| アパート経営の場合(家賃収入) ご自身でアパートを建てて運営すれば、複数の部屋からの家賃が収入となります。仮に家賃6万円の部屋が8戸あれば、年間の総収入は576万円(6万円×8戸×12ヶ月)です。 |
| 借地の場合(地代収入) 同じ土地を事業者に貸した場合の地代は、一般的にその土地の固定資産税の3〜5倍程度が目安と言われています。仮に年間の固定資産税が30万円であれば、地代収入は年間90〜150万円程度です。 ※土地の立地や形状などにより相場が変動する可能性があります。 |
しかし、自己投資が不要で、管理の負担がない点を踏まえると、土地活用は堅実でリスクの少ない選択肢として十分な価値があります。
契約期間中は他の用途で土地を使えない
借地契約には一定の制約も存在します。
例えば、契約期間が長期に及ぶため、その間は原則として他の用途で土地を使うことができません。
また、子世代に別の活用方法で引き継ぎたいと考えていても、契約期間が終わるまで待つ必要があるなど、柔軟な土地運用が難しくなる側面があります。
こうしたリスクを避けるには、契約前に期間や借主の利用目的と、自身が考える将来的な土地計画との整合性を確認することが大切です。
普通借地契約にすると土地が返ってこないリスクがある
普通借地権を使った契約では、契約終了後も借主が更新を希望すれば原則として契約が継続されます。貸主が更新を拒否するには「正当な理由」が必要とされ、これを満たさない限り契約終了はできません。
そのため、貸主側が土地を手放したくても、半永久的に返還されないリスクが生じます。さらに、契約終了時点で借主が建物を所有している場合には「建物買取請求権」が発生する可能性があります。
建物買取請求権とは、借主が地主に対して建物の時価での買い取りを請求できる制度であり、貸主は原則としてその請求に応じなければなりません。
結果として、土地の返還と同時に多額の資金が必要となる場合があるため、普通借地権での土地貸しは注意が必要です。
借地での土地活用でお困りの方は専門家へご相談されてみてはいかがでしょうか

今回の記事では、借地による土地活用のメリットや借地権の種類について解説しました。借地での土地活用は、自己投資をかけずに長期的に安定した収入を得られる有効な手段です。
特に、契約期間満了後に必ず土地が返還される「定期借地権」は、将来的に土地の利用用途を変更したい場合にも安心です。
しかし、最適な契約方法の選択や、優良な借主を見つけるには、不動産や法律に関する知識が欠かせません。ご自身の土地の可能性を最大限に引き出すためにも、まずは土地活用の専門家に相談し、客観的なアドバイスを受けることから始めてみてはいかがでしょうか。