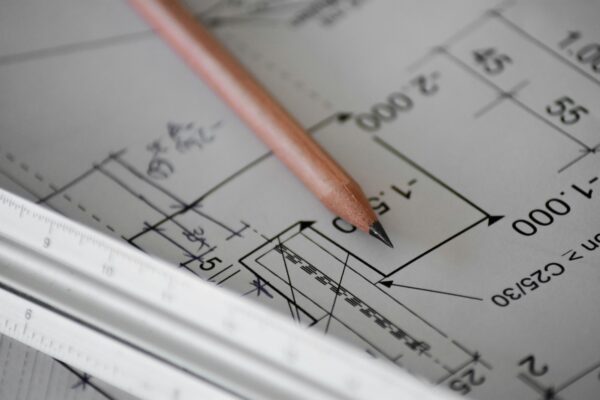相続した土地、活用せずに放置している遊休地を持っていることに負担を感じていませんか?この記事では遊休地についての基本的な情報を整理し、節税、収益を生むための土地活用法、リスクの少ない選択肢と実例を紹介します。遊休地をお持ちの方はご自身に合った活用方法を検討してみてはいかがでしょうか。
遊休地を放置するリスクとは?

まず、遊休地を放置することでどのようなリスクがあるかみていきましょう。まず、費用面では毎年の固定資産税など税負担が発生します。また、敷地内の草木が伸びることで景観が悪くなるだけではなく害虫が発生し、ゴミを不法投棄されることもあります。その結果、近隣住民とのトラブルに発展することもあり得ます。草刈りや害虫の駆除、ゴミの撤去など金銭的な負担が増えるなど様々なリスクが考えられます。
遊休地とは?
「遊休地」とは活用されずに放置されている土地のことを指します。似ている言葉で「遊休土地」というものがあります。「遊休土地」は土地の取得後2年を経過し、適正な利用が図られていないなど一定の要件に当てはまる土地のことを指し、都道府県知事から遊休土地の所有者へ土地活用を促す通知が送られます。「通知が届いて遊休土地の存在を知った」という方もいらっしゃるかもしれません。遊休土地の要件は下表の通りです。

固定資産税の負担増
前述の通り、土地を所有していることで土地所有者には固定資産税の支払い義務が発生します。例として、2,500万円の宅地を取得した場合には年間5万8,000円の固定資産税の納付が必要です。
〈計算式〉
2,500万円(宅地) × 1.4% × ※6分の1 = 5万8,000円
※小規模住宅用地の特例を適用した場合(200㎡以下の土地の固定資産税は6分の1に軽減される)で計算しています。
国土交通省が第213回通常国会に提出した資料によると「土地は預貯金や株式と比べて有利な資産か?」という問いに対し「そう思わない」と回答した国民の割合が23.2%となっており「そう思わない」理由としては「土地は預貯金と比べて、維持管理にかかるコストが大きいから」が最も多く、約4割の方が維持管理に掛かるコストを懸念していることが分かります。

出典:令和5年度土地に関する動向、令和6年度土地に関する基本的施策(国土交通省)P.34
土地の維持管理に必要なコストは?
土地の維持管理に必要なコストは税金だけではありません。人の手が入らなくなることで以下のようなリスクが発生し、その対応にも費用が掛かります。さらに建物がある場合には、老朽化に対して修繕が必要になるケースも考えられます。
| 敷地内に草木が生い茂る | 業者に刈り取りを依頼 |
| 敷地内の木が折れ隣の家の外壁が損傷 | 業者に折れた木の処分、隣家の外壁の修繕を依頼 |
| 敷地にゴミが持ち込まれる | 業者にゴミの撤去を依頼 |
| 建物の老朽化が進み壁の一部が破損 | 業者に修繕を依頼 |
| シロアリにより床にたわみ | 業者にシロアリ駆除を依頼 |
また、土地、建物の状態が悪化することで資産価値が低下することも懸念点に挙げられます。
近隣住民とのトラブル
上記の通り、意図せず隣家や周辺住民に対して迷惑を掛ける可能性があります。トラブルを未然に防ぐために一定の費用を掛けて維持管理を行う必要がありますが、他にも土地活用や相続放棄、売却など様々な選択肢の中から最適なものを検討する必要があるかもしれません。
遊休地の土地活用で注意する点は?

遊休地の土地活用を行う際に注意が必要な点を3つに分けて解説します。ご自身の土地の特徴を把握することによって適切な活用方法を絞り込むことができます。
土地の法規制を確認する
土地の所在地によって様々な法規制が適用されます。代表的なものとして都市計画法の用途地域について解説します。
用途地域とは?
例えば、多くの人が住む住宅地の近くには学校や病院を設置する、というように都市計画では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に分類しこれを「用途地域」として定めています。
用途地域の種類は13種類
用途地域は住宅地、商業地、工業地など市街地の大枠として土地利用を定めるもので、13種類に分類されています。用途地域が指定されるとそれぞれの目的に応じて、建築できる建物の種類が決められます。

出典:用途地域(国土交通省)
土地の広さを確認する
土地の広さによって活用方法が変わります。狭い土地でも駅前など人が集まる場所であれば駐車場や賃貸物件の需要があるため、収益を見込むことができるでしょう。一方で、駅から離れていたとしても広い土地であれば高齢者施設やホームセンターなど土地の広さを活かした土地活用が可能になります。尚、土地の所有者が複数人いるケースでは一つの土地を細かく分けて所有していることもありますので、事前に相続人への確認が必要です。
需要が見込める立地かどうかを確認する
用途地域など法規制を守り、広さが十分だとしても需要の低い場所では収益を見込むことは難しくなります。長期的に安定した収益を得るためには、地域の需要を正しく把握する事が重要です。市場調査を得意とする専門家に相談し、アドバイスを受けることも検討してみましょう。
初心者でも取り組みやすい遊休地活用の具体例

「そうは言っても、何から始めればいいか分からない…」という方に、初期投資額が少ない土地活用方法として駐車場経営、貸し農園、太陽光発電をご紹介します。それぞれのメリット、デメリットを表にまとめていますのでご参照ください。
駐車場経営
駅前や住宅地などに遊休地をお持ちの方の選択肢の一つになります。駐車場経営は初期費用が少なく、建物が建てにくい変形地でも運営することはできます。また原状回復もしやすい点もメリットと言えます。 ただし、更地と同様の固定資産税が掛かるため、節税対策としては効果が薄い点がデメリットになります。
| メリット | デメリット |
| 初期費用が抑えられる | 節税対策にならない |
| 狭小地、変形地でも活用可能 | 収益性が低い |
| 更地に戻しやすく、暫定的な利用ができる |
貸し農園
貸し農園は初期費用が少なく、農地を維持管理する方法として注目されています。畑をそのまま利用できるため転用の費用が掛からず、土地が荒れることを防ぐ利点もあります。最近では「農地バンク」を利用して借り手を集める仕組みもあります。地域貢献にもつながるため社会的にも評価される活用方法です。一方、貸し手と賃貸契約を結ぶ必要があり、契約上のトラブルが発生するリスクがあります。
| メリット | デメリット |
| 初期費用が抑えられる | 収益性が低い |
| 農地を維持管理しやすい | 農地を維持管理しやすい |
| 賃料収入を得られる | 土地の転用が難しい |
| 農地のため、固定資産税が抑えられる |


出典:農地中間管理機構
太陽光発電を活用した土地活用
郊外で広い土地がある場合には、太陽光発電という活用法も検討できます。太陽光発電は固定価格買取制度(FIT制度)により安定した収益を得られる点がメリットになります。郊外でも運営ができ、補助金制度を利用することで初期費用を抑えられることも嬉しい点です。一方で駐車場経営に比べるとソーラーパネルの設置費用(数百万円)が掛かること、発電量に不安定さがあるなどデメリットもあります。
| メリット | デメリット |
| 売電で収益を得られる | ソーラーパネルの設置費用が掛かる |
| 郊外でも運営ができる | 発電量が不安定 |
| 補助金制度がある | 初期費用の回収に10年程度かかる |
出典:再生可能エネルギー - FIT・FIP制度 ガイドブック(資源エネルギー庁)P.3
自分に合った土地活用方法を選ぶためのポイントまとめ

土地活用を成功させるためには、ご自身の土地の特徴に合った方法を選ぶことが大切です。立地条件や広さなど土地の条件に応じて最適な方法を選びましょう。ここまで説明した内容を簡潔にまとめます。
土地の立地条件を考慮する
土地の状況によって最適な活用方法は異なります。 都市部では駐車場や賃貸住宅、郊外や農村部では貸し農園、太陽光発電などその土地に最適な方法を選ぶことが成功の鍵です。
長期的な視点で土地活用を選ぶ
土地活用を考えるときは、将来的に需要が見込まれるかどうか長期的な視点が重要になります。その地域の人口動態や年齢構成、競合他社の経営状況など多角的な視点で分析を行いましょう。 また、土地の利用目的や将来の可能性を考慮して活用方法を選ぶことも大切です。
土地活用の目的に合った方法を選ぶ
用途地域や土地の広さが変化することはありませんので、活用方法はある程度絞られることになります。ご自身が選べる選択肢の中で最適なものを選ぶ必要があります。一方で土地活用をしないことも選択肢の一つになります。相続放棄や売却など手元に残さない方法も含めて検討することをお勧めします。
税理士・司法書士など専門家の協力で土地活用を成功させる

土地活用を成功させるためには、資金繰り(融資)、設計、施工、メンテナンス、さらに税金対策など長期にわたって様々な専門家のサポートが必要になります。専門家のアドバイスを受けることで税金面や管理面の問題を解決し、リスクを極力抑えることができます。
資金面(融資、税金)の相談
資金面(融資、税金)の相談に関しては、以下のような専門家へ相談しましょう。
・金融機関
・ファイナンシャルプランナー(FP)
・税理士
活用する予定の土地が相続で取得したものである場合、相続税の対応が必要になります。はじめに税理士へ相談し、相続に係る税金の額を明確にした上で活用方法を検討すると安心です。
法的な問題の相談
法的な問題の解決、手続きには弁護士、司法書士へサポートを依頼しましょう。
・弁護士
・司法書士
相続時に所有権など権利関係で問題が発生しそうな場合は弁護士に、相続登記の手続きについては司法書士への相談をお勧めします。
専門家へ相談する前の準備について
専門家へ相談するにあたり、相談者として最低限の準備は必要です。以下3点について準備をしておくとスムーズに話を進められますので、ご参照ください。
自分たちの希望をまとめておく
最終的な判断は不動産会社や金融機関、税理士など各専門家に相談した上で決めることになりますが、土地活用をするのか、売却をするのかなどある程度の方向性は家族で話し合っておきましょう。土地活用を希望する場合には、初期費用の額や期待する収益などもある程度まとめておくと良いでしょう。
資料を準備しておく
登記簿謄本、土地・建物の権利書、測量図などご自身で取得が可能な資料を用意しておくと相談がスムーズに進められます。余裕があれば、相談に行く前に必要な書類を確認しておくと良いでしょう。
相談料について確認しておく
基本的には初回の相談が無料であることが多いですが、念のため、相談料についても確認しておきましょう。土地活用のプランニングは複数社に相談することで様々な視点で提案を受けることができます。相談料が有料の場合は準備段階で費用が発生することになりかねませんので、ご注意ください。
まとめ

遊休地を放置せずに活用することで、節税や収益化の可能性があります。土地の活用方法にはさまざまな方法があります。専門家と連携することでリスクを管理しながらご自身の土地の特徴にあった土地活用を検討してみましょう。