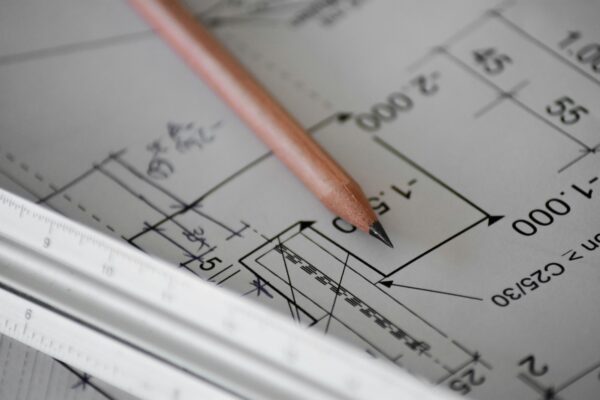ケアハウスとサ高住の違い

高齢者向け住宅事業を検討する上で、ケアハウスとサ高住の基本的な定義を理解することが第一歩です。両者の違いについて詳しく解説します。
ケアハウスとは
ケアハウスとは、老人福祉法に定められた「軽費老人ホーム」の一種(C型)であり、その設置は社会福祉事業と位置づけられています。主な運営主体が地方自治体や社会福祉法人であることからもわかるように、公的な福祉施設としての性格が非常に強いのが最大の特徴です。
その主な目的は、セーフティーネットとして無料または低額な料金で、安全な住まいと基本的な生活支援サービス(食事の提供や入浴等の準備など)を提供することにあります。
身体機能の低下や頼れる家族がいないといった家庭環境、あるいは住宅事情により、自宅での独立した生活を続けることに不安がある60歳以上の高齢者(介護型は65歳以上)の方に対して、安心して生き生きと生活できるよう目指しています。
あくまで「施設」として、地域福祉の中核を担う役割が期待されており、民間事業のような利益追求を第一の目的とはしていません。
【出典】厚生労働省「養護老人ホーム・経費老人ホームについて」
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは、「高齢者住まい法」に基づき、民間企業などが主体となって都道府県に登録する「賃貸住宅」です。
法律で義務付けられているのは、あくまで「安否確認」と「生活相談」といった基本的な見守りサービスのみです。
それ以外の食事や介護、娯楽などのサービスは事業者が任意で提供するものであり、その内容や料金は自由に設定できます。
そのため、入居者は一般的な賃貸住宅と同じように、自身のニーズに合わせてサービスを選択でき、プライバシーが尊重された自由度の高い生活を送れます。
市場のニーズに応じて民間事業者が供給する、ビジネスとしての側面が強い住まいといえるでしょう。
ケアハウスとサ高住の制度・運営上の違い

事業者として参入を検討する際、最も重要なのが制度上の違いです。運営できる主体や入居できる対象者が法律で厳密に定められています。
運営主体と参入要件の違い
ケアハウスとサ高住では、事業に参入できる法人格が根本的に異なります。この違いが、民間企業にとっての参入障壁を大きく左右します。
| ケアハウス | サ高住 | |
| 事業区分 | 第一種社会福祉事業 | (規定なし) |
| 主な運営主体 | 地方公共団体、社会福祉法人 | 民間企業、社会福祉法人、医療法人など |
| 民間企業の参入 | 原則不可(PFI法で例外的に可能だがハードル高め) | 可能(登録制) |
ケアハウスの運営は、社会福祉法で「第一種社会福祉事業」と定められています。
これは、事業の安定性や公共性が特に強く求められるため、運営主体が原則として地方公共団体や社会福祉法人に限定されていることを意味します。
株式会社などの民間企業が単独で参入することは、法律上できません。
近年、PFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)により、民間企業が公共施設の整備や運営に参画する道も開かれましたが、これはあくまで例外的な措置です。
民間企業がケアハウス事業を始める場合は「純資産が直前期末で3億円以上、単体でプラス」「最近1年間において1億円以上」の利益を上げていることなどが条件となっており、ハードルが高いのです。
【出典】厚生労働省「今後のケアハウスの整備の在り方等について」
一方、サ高住には運営主体の法的な制限がなく、株式会社でも医療法人でも、定められた基準を満たして都道府県に登録すれば事業を開始できます。
入居対象者の違い
提供する住まいが、どのような方を対象とするのかも明確な違いがあり、これは事業のターゲット設定に直結します。
| ケアハウス | サ高住 |
主な対象者 | 自立した生活に不安があり、家族の援助を受けるのが困難な高齢者 一般型:60歳以上 | 以下のいずれかに該当する単身・夫婦世帯 ①60歳以上の者 ②要介護/要支援認定を受けている60歳未満の者 |
| 介護の必要度 | 一般型:自立 介護型:要介護1以上 | 施設により異なる |
ケアハウスの大きな特徴は、公的な施設として、利用料が国の基準に基づいて定められ、入居者の収入に応じて変動する点です。
そのため、低所得の方でも負担の少ない料金で利用できる一方、所得の高い方も入居できます。
ただし、事業者の視点で見れば、料金設定の自由度が低く、一人当たりの売上単価に上限がある点は考慮すべきです。
一方で、サ高住は民間の賃貸住宅であるため、入居にあたっての所得要件は基本的にありません。
これにより、事業者は幅広い所得層の高齢者をターゲットに設定できます。
例えば、基本的なプランに加えて、コンシェルジュサービスや高級な食事といった付加価値の高いオプションを用意すれば、経済的に余裕のある層を取り込み、収益性を高める、といった柔軟な事業戦略を描くことが可能です。
ケアハウスとサ高住の収益性や補助金・優遇制度の違い

事業として成立するかを判断する上で、収益性や優遇措置などの違いは重要な比較ポイントです。それぞれの収益性と補助金・優遇制度の違いについて解説します。
収益性の違い
ケアハウスとサ高住では、収益構造と利益を追求できる範囲が大きく異なります。事業者としてどちらを選択するかは、利益に対する考え方そのものを問われることになります。
| 項目 | ケアハウス | サ高住 |
| 収益の目的 | 社会福祉の提供(利益追求が目的でない) | 事業としての利益確保 |
| 主な収益源 | ・入居一時金 ・利用料 ・介護報酬 | ・家賃 ・共益費 ・生活支援サービス費 ・介護報酬(介護サービス利用時) |
| 料金設定 | 自由度が低い(国の基準や入居者の所得に応じて変動) | 自由度が高い(サービス内容に応じて価格設定が可能) |
| 収益性 | 低い(赤字施設の割合が拡大傾向※) | 方法によっては高収益を追求可能 |
※【出典】独立行政法人福祉医療機構「2021 年度 軽費老人ホーム(ケアハウス)の経営状況について」
上記のとおり、ケアハウスは公的福祉施設としての役割から、収益性を高く設定することが制度上困難です。
利用料は国の基準で上限が定められ、物価が高騰しても柔軟な価格改定が難しく、経営を圧迫しやすい構造にあります。
対してサ高住は、提供するサービスの質と価格を事業者が自由に決められます。そのため、他社との差別化や付加価値の高いサービスを提供することで、高い収益性を目指すことが可能です。
事業としての成長や利益を重視する場合、サ高住に大きなアドバンテージがあるといえます。
補助金・優遇制度の違い
ケアハウスとサ高住ともに、建設や運営にあたって公的な支援制度が用意されています。
しかし、その性質と目的は異なります。
| 項目 | ケアハウス | サ高住 |
| 建設費補助 | 国や自治体からの手厚い補助あり | 国からの補助あり(新築の場合、費用の10分の1など) |
| 税制優遇 | 固定資産税・不動産取得税などの減免措置あり | 固定資産税・不動産取得税の軽減措置あり |
| 運営費補助 | 自治体から運営費に対する補助が受けられる可能性あり | なし |
【出典】
スマートウェルネス住宅等推進事業「サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の概要」
J-Net21「業種別開業ガイド ケアハウス」
ケアハウスへの補助金は、福祉インフラ整備の一環として、特に社会福祉法人が運営する場合に手厚く交付されます。
建設費だけでなく、施設の運営にかかる費用など、ランニングコストの一部も補助の対象となるのが特徴です。
これは、事業の採算性よりも、福祉サービスの安定供給を優先する制度設計の表れです。
一方、サ高住への補助金は、あくまで民間事業者による高齢者向け住宅の供給を促進するための「インセンティブ」という位置づけとなっています。
建設費の一部や税制優遇によって初期投資のハードルを下げる支援はありますが、運営費の補助は原則ありません。
つまり、事業開始後の経営は、完全に事業者の自己責任に委ねられており、持続可能な収益モデルを自ら構築する必要があります。
ケアハウスとサ高住の参入しやすさの違い

これまでの違いを踏まえると、民間企業にとっての参入のしやすさは明確です。
結論として、民間企業が新たに高齢者向け住宅事業に参入する場合、サ高住の方が圧倒的に参入しやすいといえます。
ケアハウスは「第一種社会福祉事業」に位置づけられており、民間企業が単独で開設・運営するには、社会福祉法という法律上の高いハードルが存在します。
仮にPFI方式などで参入の道を探るとしても、都道府県知事の許可を得るための複雑な手続きや、行政との長期にわたる折衝が必要となり、時間的・人的コストは計り知れません。
対してサ高住は、運営主体の制限がなく、定められた基準(居室面積、バリアフリー構造、サービスの提供体制など)を満たせば、登録制で事業を開始できます。
事業の成否は、法的な参入障壁の高さではなく、立地選定の的確さ、建物やサービスの品質による他社との差別化、そして効果的なマーケティング戦略といった、純粋な企業の経営努力に委ねられています。
自由な市場で、自社が持つ介護のノウハウや理念を活かした独自の事業展開を目指す民間企業にとって、サ高住は非常に挑戦しがいのある、魅力的な選択肢なのです。
ケアハウスとサ高住の違いを知り適した方法で事業スタートしよう

この記事では、福祉事業者様の視点から、ケアハウスとサ高住の違いについて、制度、収益性、参入障壁の観点から詳しく解説しました。
両者の違いをまとめると、以下のようになります。
| ケアハウス:公的な福祉施設としての性格が強く、社会福祉法人などが運営主体。収益性は低いが、安定した需要と手厚い公的補助がある。民間企業の参入障壁は非常に高い。 |
| サ高住:民間の賃貸住宅としての性格が強く、株式会社などの民間企業が自由に参入可能。収益性を追求でき、市場競争の中で独自のサービスを展開できる。 |
それぞれの特性を理解し、自社の理念や事業戦略、資金計画と照らし合わせれば、どちらの事業モデルがより適しているかが見えてくるはずです。
また、これからケアハウスやサ高住などの福祉施設経営に参入しようとしている方は、福祉施設の設計・施工に強い専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談すれば、事業計画や土地探し、資金調達のご相談など、あらゆる面でサポートしてもらえます。
専門家のバックアップのもと、自身に適した方法を見つけて、事業を成功させましょう。