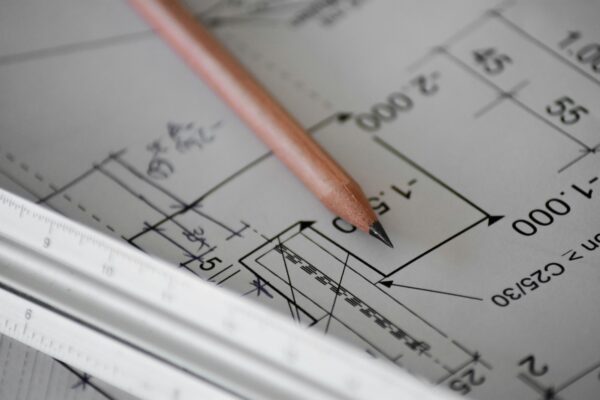サ高住と特養の違いとは?サービス内容や収益モデルについて解説

福祉事業として参入を検討する上で、サ高住と特養、それぞれの施設がどのような法的枠組みで運営され、どのような特徴を持つのかを正確に把握するのが第一歩です。
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは
サ高住は、「高齢者住まい法」に基づき、主に民間事業者が都道府県に登録して運営する「賃貸住宅」です。法的な位置づけが「施設」ではなく「住宅」である点が、特養との根本的な違いとなります。
サ高住のサービス内容
法律で義務付けられているサービスは、「安否確認」と「生活相談」の2つです。これにより、入居者は自立した生活を送りながらも、万が一の際には専門スタッフによるサポートを受けられる安心感を確保します。
食事の提供や身体介護、清掃・洗濯といった生活支援サービスは、事業者が任意で提供するオプションです。
入居者は、自身の心身の状態や希望に合わせて、必要なサービスを自由に選択できます。近年では、介護の必要度が高い入居者に対応するため、訪問介護事業所やデイサービスを併設し、特養に近い手厚い介護サービスを提供する「特養化」したサ高住も増えています。
サ高住の収益モデル
サ高住の主な収入源は、入居者から得る「家賃」「共益費」、そして必須サービスである「状況把握・生活相談サービス費」です。
これらの料金は、近隣の相場や提供するサービスの質に応じて事業者が自由に設定できるため、ビジネスとしての収益性を追求しやすいのが特徴です。
また、食事や娯楽などのオプションサービスを提供すれば、さらなる収益の上乗せもできます。建設時には、国から建設費の一部を補助する制度も用意されており、初期投資を抑えられます。
サ高住の運営主体
サ高住の運営主体には、法律上の制限がありません。そのため、株式会社などの民間企業をはじめ、社会福祉法人、医療法人、NPO法人など、さまざまな法人が事業に参入しています。民間企業が福祉事業に新規参入する場合、この門戸の広さが大きな魅力となります。
サ高住に必要な人員や設備
サ高住には、人員と設備の両面で法律上の基準が定められています。
人員については、日中に社会福祉法人等の職員や、ケアの専門家(社会福祉士、介護福祉士など)が少なくとも1名常駐し、安否確認と生活相談サービスを提供する必要があります。
設備面では、各専用部分(居室)の床面積は25㎡以上が原則です。
また、手すりの設置や段差の解消といったバリアフリー構造であるのはもちろん、各戸に便所と洗面設備を設けるのが必須です。
【出典】
サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム「制度についての基本的な質問」
厚生労働省「サービス付き高齢者向け住宅について」
特養(特別養護老人ホーム)とは
特養は、「老人福祉法」に基づいて設立される公的な「介護保険施設」です。正式名称を「介護老人福祉施設」といい、常に介護が必要な状態(原則要介護3以上)で、在宅での生活が困難な高齢者が入所します。
特養のサービス内容
特養の目的は、入所者に「終の棲家」として、日常生活の介護から看取りまで、24時間体制で包括的なケアを提供するところにあります。
食事、入浴、排泄といった身体介護はもちろん、機能訓練や健康管理、レクリエーションなど、生活全般にわたる手厚いサービスが特徴です。
サ高住のようにサービスを選択する形式ではなく、施設サービス計画に基づいて必要なケアが一体的に提供されます。
特養の収益モデル
特養の主な収入源は、介護保険制度から給付される「介護報酬」です。
利用料は、入居者の要介護度や所得段階に応じて国が定めた基準に基づいて算出されるため、事業者が自由に設定できません。居住費や食費も、低所得者への負担軽減措置が設けられています。
公的な施設であるため、建設費や運営費には国や自治体から手厚い補助金が交付されます。
しかし、収益構造そのものが利益追求を目的としていないため、高い収益性を確保するのは難しい事業モデルです。
特養の運営主体
特養の運営は、社会福祉法で定める「第一種社会福祉事業」に該当します。
この事業は、利用者の生活に与える影響が大きく、極めて高い公共性と安定性が求められるため、運営主体が原則として国、地方公共団体、または非営利の「社会福祉法人」に限定されています。
そのため、株式会社などの民間企業が単独で特養を設立・運営するのは、法律上原則として認められていません。
ただし、一定の要件を満たせば、民間企業も運営に参画する道が開かれています。
この場合でも、都道府県知事の許可が必要であり、経営主体には「経営に必要な経済的基礎がある」「経営者が社会的信望を有する」といった、社会福祉法人に準ずる厳しい要件が課せられます。
民間企業にとって、特養の運営に参入するハードルは依然として非常に高いのが実情です。
特養に必要な人員や設備
特養は、24時間体制で手厚い介護を提供するため、人員・設備ともに法律で厳格な基準が定められています。
人員については、多職種の専門スタッフの配置が義務付けられています。必要になる人員の数や職種を以下にまとめました。
| 職種 | 配置基準の例 |
| 医師 | 健康管理や療養上の指導を行うために必要な人数を配置(非常勤可) |
| 生活相談員 | 100人またはその端数を増すごとに1人以上 |
| 介護・看護職員 | 【介護職員】 3人またはその端数を増すごとに1人以上 【看護職員について】 入所者の数が30人以下の場合常勤換算で1人 入所者の数が30人以上50人以下の場合は常勤換算で2人以上 入所者の数が50人以上130人以下の場合は常勤換算で3人 それ以上の場合は50人またはその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 |
| 機能訓練指導員 | 1人以上 |
| 栄養士または管理栄養士 | 1人以上 |
| 介護支援専門員 | 100人またはその端数を増すごとに1人以上(常勤) |
特に、介護・看護職員は「入所者3人に対して1人以上」という基準があり、手厚い体制が求められます。
設備面では、入所者一人当たりの床面積は10.65㎡以上と定められ、居室、食堂、機能訓練室、浴室といった基本的な設備が必要です。
それに加え、入所者の健康管理を行うための医務室や、看取りにも対応できる静養室、衛生管理のための汚物処理室などの設置も義務付けられています。
【出典】
e-gov法令検索「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」
厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」
サ高住と特養以外の介護施設の種類

高齢者向けの住まいには、サ高住と特養以外にもさまざまな種類があります。
例えば、民間企業が運営する「有料老人ホーム」や、認知症の方が共同生活を送る「グループホーム」、在宅介護を支える「デイサービス」などです。
これらの施設は、対象となる方の状態や、提供するサービス内容、契約形態などが異なります。
どの施設を運営するかによって、事業の方向性や求められるノウハウも大きく変わります。
各介護施設の種類や、それぞれに必要な設備の違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
【関連記事】介護施設に必要な設備とは?他の介護施設と差別化するポイントについても解説
新たな介護施設運営を始めるならサ高住がおすすめの理由

これまで見てきた違いを踏まえると、民間企業が新たに高齢者向け住宅事業に参入する場合、特養よりもサ高住の方が現実的で、かつ事業として成功しやすい選択肢といえます。
その主な理由を2つ解説します。
サ高住は特養と違い参入ハードルが低い
最大の理由は、事業参入のしやすさです。前述のとおり、特養の運営は「第一種社会福祉事業」にあたるため、株式会社などの民間企業が参入できません。
参入するには、まず非営利団体である「社会福祉法人」を設立する必要がありますが、その設立要件は非常に厳しく、多額の資産や評議員の確保など、極めて高いハードルが存在します。
一方で、サ高住の運営主体に法的な制限はなく、株式会社でも医療法人でも、定められた基準を満たして都道府県に登録すれば事業を開始できます。
福祉事業への新規参入を目指す民間企業にとって、この参入障壁の低さは、サ高住を選ぶ決定的な理由となるでしょう。
【出典】 e-GOV法令検索「社会福祉法(社会福祉施設の設置)」
特養は収益を伸ばしにくい
二つ目の理由は、収益性の違いです。特養を運営する社会福祉法人は、利益の分配を目的としない「非営利法人」です。
事業の目的は、あくまで社会福祉の提供であり、利益の最大化ではありません。
対して、サ高住を運営する株式会社(民間企業)は、もちろん利益を追求可能です。良質なサービスを提供し、多くの入居者から支持を得られれば、その成果は企業の利益として還元されます。
事業の成長と収益性の向上を目指すのであれば、民間事業であるサ高住の方が、経営の自由度が高く、魅力的な事業モデルといえます。
サ高住と特養の違いを理解して自分に合った方法で参入しよう

今回の記事では、福祉事業者の視点から、サ高住と特養の違いについて詳しく比較・解説しました。
両者の違いをまとめると、以下のようになります。
| 特養:公的な「介護施設」であり、社会福祉法人などが運営。手厚い介護を提供するが、収益性は低く、民間企業の参入は極めて困難。 |
| サ高住:民間の「賃貸住宅」であり、株式会社でも自由に参入可能。サービス内容や料金設定の自由度が高く、事業としての収益性を追求できる。 |
これらの特性を理解すれば、自社の理念や事業戦略に合った施設はどちらなのか、おのずと見えてくるはずです。
もし、サ高住の開業を通じて、地域社会への貢献と事業の成長を両立させたいとお考えでしたら、福祉施設の設計・施工に強い専門家にご相談ください。
専門家に相談すれば、具体的な事業計画や資金シミュレーション、市場調査など、事業スタートへのサポートをしてくれます。
サ高住と特養の違いを正しく理解して、自社がどちらに参入するべきか検討し、安定した事業スタートを目指しましょう。