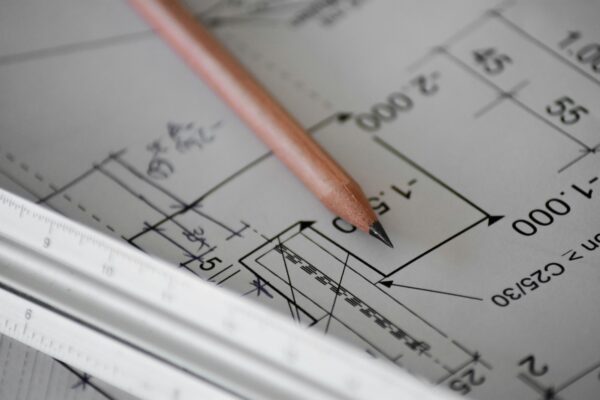福祉施設の開業を始める前に覚えておきたい前提知識

福祉施設の開業を目指す上で、まず押さえておくべき法律上の区分や、施設の種類に関する基本的な知識があります。これらの理解が、事業計画の第一歩となります。
福祉事業には「第一種」と「第二種」がある
社会福祉法では、福祉事業をその公共性の高さから「第一種社会福祉事業」と「第二種社会福祉事業」の2つに分類しています。この区分は、事業に参入できる主体を定める、極めて重要なルールです。
| 第一種社会福祉事業 | 第二種社会福祉事業 | |
| 概要 | 利用者の生活に与える影響が大きく、安定した運営が強く求められる事業 | 第一種よりも比較的利用者への影響が小さいため公的規制の必要性が低い事業 |
| 主な運営主体 | 国、地方公共団体、社会福祉法人 | 制限なし |
| 民間企業の参入 | 原則不可 | 可能 |
【出典】厚生労働省「生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業」
第一種社会福祉事業は、特別養護老人ホームなどの入所施設が代表例で、利用者の保護という側面が非常に強いため、運営主体が原則として国、地方公共団体、または非営利の社会福祉法人に限定されています。
安定性と継続性が最優先されるため、株式会社などの民間企業が単独で参入するのは、法律上極めて困難です。
一方で、第二種社会福祉事業は、訪問介護やデイサービスといった在宅サービスが中心で、利用者の選択によって成り立つ事業です。
そのため運営主体の制限がなく、株式会社やNPO法人なども自由に参入できます。
したがって、民間企業が新たに福祉事業を始める場合は、この第二種社会福祉事業から参入するのが一般的です。
【出典】厚生労働省「社会福祉事業及び社会福祉法人について(参考資料)」
福祉施設にも種類がある
「福祉施設」と一口にいっても、その対象者やサービス内容によって多くの種類に分かれます。事業を始めるには、どの分野で、誰を対象にサービスを提供したいのかを明確にする必要があるのです。
法律上、福祉施設は老人福祉施設、障害者支援施設、児童福祉施設などに大別されます。そして、それぞれの施設が提供する事業内容によって、前述の第一種、第二種のどちらに該当するかが決まっています。
入所型の「特別養護老人ホーム」は第一種ですが、在宅サービスの「訪問介護(老人居宅介護等事業)」や「通所介護(老人デイサービス事業)」は第二種に分類される、といった例です。
民間企業が参入しやすい第二種の介護事業の例としては、「老人居宅介護等事業(訪問介護)」や老人デイサービス事業(通所介護)」が挙げられます。
また、有料老人ホームやサ高住(サービス付き高齢者向け住宅)のように、社会福祉法ではなく、それぞれ老人福祉法や高齢者住まい法といった別の法律に基づいて運営される施設もあります。
どの事業を始めるかによって、遵守すべき法律や基準が異なるため、最初の事業選択が重要です。
【出典】
厚生労働省「社会福祉施設の概要」
鳥取県社会福祉協議会「社会福祉法第2条に規定する「社会福祉事業」とは」
介護事業を例に福祉施設を開業する流れを解説

福祉施設の開業は、一般的な起業とは異なり、行政への申請や指定といった専門的な手続きが欠かせません。
介護事業を例に取ると、その大まかな流れは、事業計画の策定から始まり、法人設立、人員・設備の確保、そして行政への指定申請のステップで進んでいきます。
それぞれの段階で満たすべき基準が細かく定められており、綿密な準備が求められます。
特に、事業の根幹に関わる人員基準や設備基準は、計画段階で入念に確認しておくべき重要なポイントです。
介護施設の開業準備や具体的な流れについては、以下の記事でさらに詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
【関連記事】介護施設開業に必要な準備とは?具体的な流れや収益構造も徹底解説!
介護系の福祉施設を開業するための費用

福祉施設の開業にかかる費用は、施設の規模や種類、立地、そして建物を賃貸するか自己所有するかによって大きく変動します。
例えば、デイサービスを賃貸物件で始める場合、物件の取得費や内装工事費、送迎用車両の購入費、備品代、そして当面の運転資金などを含めると、1,000万円程度の初期投資が必要になる場合があります。
入所型の施設を土地の取得から始める場合は、土地購入費、建物の建築費、医療・介護設備の導入費など、総額で数千万〜数億円規模の資金が必要になるケースも珍しくありません。
事業計画を立てる際には、これらの費用を正確に見積もり、自己資金でどれだけを賄い、どれだけを外部から調達するのかを明確にする必要があります。
福祉施設開業時の資金調達方法

多額の初期費用が必要となる福祉施設の開業では、適切な資金調達計画が事業の成否を分けます。主な資金調達の方法として、以下の3つが挙げられます。
助成金や補助金の活用
福祉事業は社会貢献性が高いことから、国や自治体がさまざまな助成金・補助金制度を用意しています。
これらの制度は、事業者の負担を軽減し、福祉サービスの安定供給を支えるための重要な仕組みとなります。
金融機関からの融資とは異なり、原則として返済の義務がないのが最大のメリットです。
例えば、厚生労働省が管轄する「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、仕事の生産性を向上させることで、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得などに取り組む中小企業を支援する制度です。
【出典】厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」
その他にも、各自治体が独自に設けている施設整備に関する補助金制度もあります。
どのような支援が受けられるか、開業を計画している地域の自治体窓口や、社会保険労務士などの専門家に相談するのがよいでしょう。介護施設の開業時に利用できる助成金については以下の記事でも解説しているので、併せてご覧ください。
【関連記事】介護施設を開業するときに利用できる助成金!有効活用して資金繰りを楽にしよう
日本政策金融公庫や信用保証協会、銀行からの融資
自己資金や補助金だけでは資金が不足する場合、金融機関からの融資を検討します。
特に、創業期の事業者にとって心強い味方となるのが、政府系金融機関である「日本政策金融公庫」です。
民間の銀行に比べて、新規開業への融資に積極的で、無担保・無保証で借り入れできる制度もあり、比較的低い金利で借り入れできる可能性があります。
また、各都道府県にある「信用保証協会」の保証を得ることで、民間の銀行からの融資が受けやすくなる制度もあります。
信用保証協会が公的な保証人となることで、金融機関のリスクが低減されるためです。
いずれの融資を受けるにも、事業の将来性や収益性を客観的なデータで示した、説得力のある事業計画書の提出が欠かせません。
ファクタリング
ファクタリングとは、事業者が保有する「売掛債権(将来入金される予定のお金)」を、ファクタリング会社に手数料を支払って買い取ってもらい、早期に資金化するサービスです。
介護事業の場合、収入の柱である介護報酬は、毎月1日〜10日までに国保連合会に請求し、その翌々月に入金されるため、実際に現金を手にするまでには2ヶ月程度のタイムラグが生じます。
この間の人件費や家賃などの運転資金が不足しがちな開業当初に、ファクタリングを利用してキャッシュフローを安定させるのは有効な手段です。
ただし、手数料がかかるため、利用は計画的に行う必要があります。
福祉施設開業において注意すべき失敗例

福祉施設の開業には、特有のリスクや注意点が存在します。ここでは、特に注意すべき失敗例を3つご紹介します。
関連法規への認識不足
福祉施設の運営は、介護保険法だけでなく、建物の安全に関わる建築基準法や消防法など、多くの法律によって厳しく規制されています。これらの法規に対する認識が不足していると、事業計画そのものが頓挫しかねません。
例えば、デイサービス施設では、利用者が安全に過ごせるよう、施設の面積に応じてスプリンクラーなどの消防用設備の設置が義務付けられています。
また、施設の用途や規模によっては、防火壁の設置や避難経路の確保など、専門的な建築知識が求められます。
最も注意すべきは、これらの要件は計画段階でクリアしておく必要がある点です。
法規制を満たさない設計では、そもそも行政から建築許可が下りず、工事に着手すらできません。
多額の費用をかけて設計を終えた後で、法規制に適合しないことが判明する、といった事態は絶対に避ける必要があります。
有資格者の離職
福祉事業の多くは、そのサービスを提供するために、管理者や介護福祉士、看護師といった有資格者の配置が法律で義務付けられています。これは「人員配置基準」とよばれる、事業運営の根幹をなすルールです。
開業時には基準を満たすスタッフを確保できていたとしても、その有資格者が一人でも離職してしまうと、基準を満たせなくなり、事業の運営が続けられなくなるリスクがあります。
特に、小規模な施設でギリギリの人員で運営している場合は、一人の離職が事業の存続を直接的に揺るがしかねません。
単に人材を集めるだけでなく、働きやすい職場環境を整え、スタッフの定着を図る経営努力が常に求められます。
ニーズの調査不足
「介護施設はどこも足りないはずだ」と漠然とした思い込みだけで事業を始めてしまうのも、よくある失敗の一つです。
確かに、日本全体で高齢化は進んでいますが、地域によってその進行度や、求められるサービスの種類は大きく異なります。
すでに近隣に多くのデイサービスがある地域に、同じような施設を開業しても、激しい利用者獲得競争に巻き込まれるだけです。
開業を計画しているエリアの人口構成(高齢者率、要介護認定者の数など)や、競合となる施設のサービス内容と稼働状況、そして地域住民が本当に求めているサービスは何か、といった事前の市場調査を徹底的に行う姿勢が、事業の成功には欠かせません。
まとめ

今回の記事では、福祉施設の開業を目指す事業者様に向けて、知っておくべき前提知識や資金調達の方法、そして注意すべき失敗例などを解説しました。
福祉施設の開業は、社会に貢献できる非常にやりがいのある事業ですが、その実現には、法規制の遵守、綿密な事業計画、そして安定した資金計画が求められます。
特に、事業の器となる建物の設計や建築は、その後の運営の成否を左右する重要な要素です。
もし、事業計画や資金調達、行政への届け出など、専門的な知識が必要な場面で不安を感じる場合は、一人で悩まず、福祉施設の開業に精通した専門家へ相談することをおすすめします。