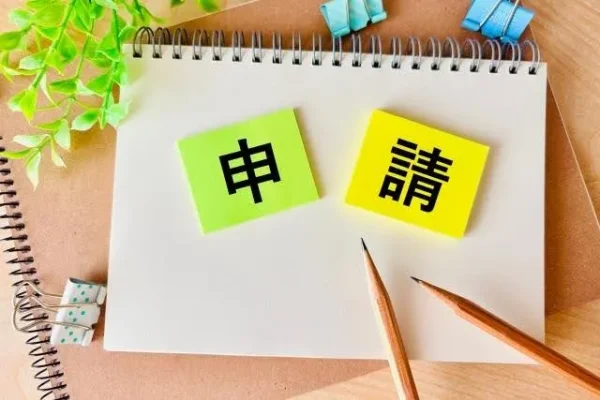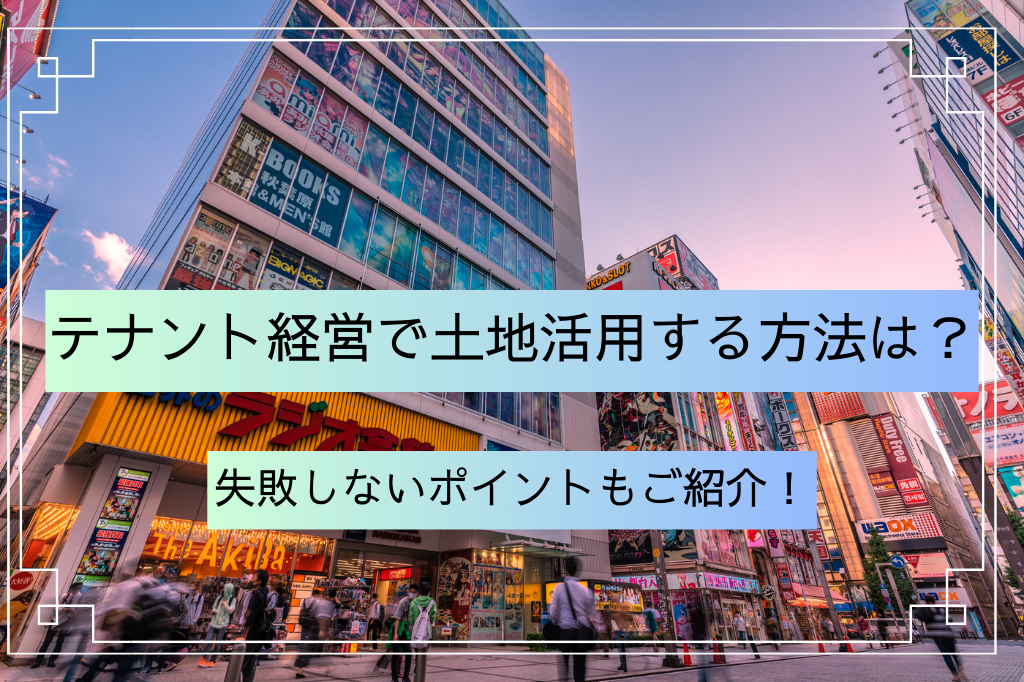相続税対策のために、賃貸アパートなどを建てて土地活用をするという話はよく聞きます。
土地活用をすることで、どのような仕組みで、どれくらい相続税を節税できるのでしょうか。
この記事では、まず相続税の基礎知識と代表的な相続税対策を解説します。
次に、土地活用が相続税対策になる理由と減額割合、相続税対策におすすめの土地活用法を紹介。
相続税対策で土地活用をする場合に、注意すべきポイントについても説明しますので、ぜひご覧ください。
土地活用は相続税対策になる!
相続税対策としての土地活用についてお話する前に、まず相続税とは何か、相続税の計算方法、代表的な相続税対策について説明します。
相続税の概要
相続税とは、親や配偶者が亡くなって財産を相続した場合に、その財産に課せられる税金。
亡くなった人を「被相続人」、財産を相続する人を「相続人」と呼びます。
土地や建物などの不動産だけでなく、預貯金や有価証券などすべての財産に課税されます。
ただし、以下のような財産は非課税となります。
- 墓
- 相続によって取得した生命保険の一部
- 相続によって取得した退職手当金の一部
- 相続によって取得した財産で国や自治体に寄付したもの
相続税の計算方法
相続税の計算方法を簡略化して説明すると、相続財産の評価額から「債務や葬式費用」や「基礎控除額」を引いた額に、税率を乗じて相続税額を算出します。
| (相続財産の評価額 – 債務や葬式費用 – 基礎控除額) × 税率 |
より具体的な計算方法を、以下で解説します。
相続財産の評価額
相続財産の評価額の算出方法は、財産の種類によって異なります。
現金や預貯金の評価額は額面通りで、株式の評価額は時価。
不動産の評価額は相続税路線価または固定資産税評価額を基に計算され、一般的に時価より低い水準になります。
<土地の評価額>
土地の評価額は、国税庁によって道路ごとに定められた「路線価」(1平方メートル当たりの価額)を、土地の形状等に応じて補正した後、土地の面積を乗じて計算します。
| 土地の評価額 = 路線価 × 補正率 × 土地の面積 |
各地域の路線価が記載された「路線価図」は、国税庁のホームページで閲覧可能です。
なお、路線価が定められていない地域では、土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
<建物の評価額>
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同じ額です。
| 建物の相続税評価額 = 建物の固定資産税評価額 |
土地や建物の固定資産税評価額は、毎年4~6月頃に市町村から送られる「固定資産税納税通知書」に記載されています。
債務控除
すべての相続財産の評価額の合計が求められたら、債務や葬式費用を引いて「課税価格」を求めます。
| 相続財産の評価額合計 – 債務や葬式費用 = 課税価格 |
基礎控除
「課税価格」から「基礎控除額」を引くことで、「課税遺産総額」を計算します。
| 課税価格 – 基礎控除額 = 課税遺産総額 |
「基礎控除額」は以下の式で求められます。
| 基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) |
「法定相続人」とは民法で定められ、遺産を相続する権利を有する人のこと。
法定相続人の中に相続放棄をした人がいても、基礎控除額を計算する上では法定相続人の数に含めます。
「課税価格」が「基礎控除額」以下であれば、相続税は課税されず相続税申告も不要。
たとえば、相続人が配偶者1人、子供2人の場合、基礎控除額は以下の式より4,800円になります。
| 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円 |
「課税価格」が4,800円以下であれば、相続税は課税されません。
一方「課税価格」が4,800円を超える場合、超えた部分について相続税が課されます。
相続税額の計算
次に、「課税遺産総額」を、民法の法定相続分に応じて各相続人に按分し、各遺産額に応じた税率を乗じて、各相続人の相続税額を計算します。
| 各相続人の法定相続分に応じた取得金額 × 税率 = 各相続人の相続税額 |
各相続人の相続税額を合計したものが、相続税の総額となります。
代表的な相続税対策
上記のように求められる相続税は、課税対象となる相続財産を減らすまたは相続財産の評価額を下げることで節税できます。
代表的な相続税対策の方法を、以下で3つ説明します。
| 相続税対策 | 節税方法 |
|---|---|
| 生前贈与 | 被相続人が生前に資産を贈与することで、相続財産が減る |
| 生命保険 | 生命保険に加入することで、課税対象となる相続財産が減る |
| 土地活用 | 資産を現金や預貯金でなく不動産で持つことで、相続財産評価額が下がる |
<生前贈与>
生前贈与とは、被相続人が生前に無償で贈与すること。
贈与した分だけ、相続税の対象となる財産を減らすことができます。
一定額以上の財産を無償で贈与した場合は「贈与税」がかかります。
ただ、「暦年贈与」という仕組みを利用すれば、贈与税がかかりません。
暦年贈与は、親が子や孫に対して贈与する額が1人当たり年間110万円以下の場合に適用されます。
なお、暦年贈与の制度は将来的に見直される可能性があることに注意が必要です。
<生命保険>
生命保険などで支給される死亡保険金は、一定額までは相続税の対象となりません。
財産の一部を保険金に変えることで、課税対象となる相続財産を減らすことができます。
相続税がかからない「非課税限度額」は、500万円に法定相続人の数を乗じた額です。
| 非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人 |
生命保険に加入する場合は、相続税の非課税限度額を考慮して保険金の額を検討しましょう。
<不動産>
現金や預貯金でなく、不動産で資産を持つことで相続財産評価額を下げることができます。
相続税計算上、現金や預貯金は額面通りの評価額ですが、不動産の評価額は実際の取引価格(「時価」)や建築費よりも低くなる傾向があるためです。
また、土地や建物をただ持っているだけでなく、土地活用をすることで、さらに相続税評価額を下げることができます。
相続、保険やもの整理など終活のことならすべて、みんなが選んだシリーズで安心して探すことができます。
土地活用でどれくらい相続税対策できる?
相続税対策の中でも特に効果が高い土地活用ですが、具体的にどれくらい節税効果があるのでしょうか。
土地の相続税評価額は、上述した様に路線価を基に計算されますが、路線価は時価の8割程度と言われています。
たとえば、1億円の現金を持っている場合相続税評価額は1億円ですが、時価1億円の土地を保有している場合の相続税評価額は8千万円程度。
現金で持っているより土地で持っている方が、2千万円分も相続税評価額が低いことになります。
さらに、土地を更地のまま所有しているのではなく以下のように土地活用することで、さらに評価額を下げることができるのです。
| 土地の形態等 | 評価額の減額割合 |
|---|---|
| 土地を賃貸した場合 | 土地:30~90% |
| 土地活用で建物を建てた場合 | 建物:40%程度 |
| 土地活用で建物を賃貸した場合 | 土地:10~30% 建物:最大30% |
| 小規模宅地等の特例が適用できる場合 | 土地:20~50% |
土地を賃貸した場合
土地を賃貸した場合、土地の評価額は借地権割合の分だけ下がります。
「借地権割合」は、国税庁が地域ごとに30~90%の間で設定しているもので、「路線価図」で確認できます。
たとえば借地権割合が70%の地域では、土地を賃貸した場合の評価額は更地価額より70%減額され、更地価格の30%となります。
| 賃貸中の土地の評価額 = 更地の評価額 × (1 - 70%) |
評価額が1億円の土地であれば、土地賃貸後の評価額は3千万円になります。
土地活用で建物を建てた場合
土地の上に建物を建てた場合、建物評価額は一般的に建築費相当額の60%程度になります。
たとえば、1億円を預貯金で持っている場合、相続税評価額も1億円です。
一方、1億円の建築費をかけて建物を建てると、建物相続税評価額はその60%程度の6千万円。
建物を建てることで、預貯金で保有していた場合と比べて、相続財産評価額が40%程度下がることになります。
土地活用で建物を賃貸した場合
建物を賃貸した場合、土地と建物両方の評価額が下がります。
<土地の評価額>
土地は「貸家建付地」として評価され、評価額が10~30%程度下がります。
| 「貸家建付地」の評価額 = 自用地の土地の評価額 × (1 – 借地権割合 ×借家権割合) |
「借地権割合」は地域によって異なりますが、「借家権割合」は全国一律30%と定められています。
<建物の評価額>
建物は「貸家」として評価され、評価額が最大30%下がります。
| 「貸家」の評価額 = 建物固定資産税評価額 × (1 – 借家権割合 × 賃貸割合) |
「賃貸割合」とは、賃貸に供する面積の内、実際に賃貸されている面積の割合のこと。
満室の場合は賃貸割合が100%となり、建物の評価額は30%下がります。
小規模宅地等の特例が適用できる場合
「小規模宅地等の特例」が適用されると、土地の評価額はさらに大きく減額されます。
対象となる宅地は、被相続人が事業に使っていたまたは居住していた土地で、大きく3つに分けられます。
条件に合う場合、土地の一定面積部分の評価額が、50~80%も減額可能です。
詳細は以下の表をご覧ください。
| 相続開始の直前における宅地等の利用区分 | 要件 | 限度 面積 | 減額 割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 | ① | 特定事業用宅地等に該当する宅地等 | 400㎡ | 80% | |
| 貸付事業用の宅地等 | 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く。)用の宅地等 | ② | 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 | 400㎡ | 80% | |
| ③ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | |||
| 一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 | ④ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | ||
| 被相続人等の貸付事業用の宅地等 | ⑤ | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200㎡ | 50% | ||
| 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | ⑥ | 特定居住用宅地等に該当する宅地等 | 330㎡ | 80% | ||
出典:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁ホームページ
「貸付事業用宅地」には、アパート経営などで土地活用している土地も含まれます。
「小規模宅地等の特例」は、土地活用による相続税対策として一番大きな効果が期待できます。
土地活用を考える場合は、適用できるかぜひ検討してみましょう。
土地活用にローンを利用した場合
借入金相当額は相続財産の評価額から控除できるため、土地活用にローンを利用すると、相続税計算の基となる「課税価格」の圧縮につながります。
ただ、ローンを利用すると節税効果がある一方で、金利支払いが発生します。
土地活用による収支を予測した上で、無理のない返済計画を立てることが重要です。
相続税対策に有効なおすすめの土地活用法
ここからは、相続税対策におすすめの土地活用法を紹介します。
- 土地を賃貸する
- オフィスビル
- アパート・マンション経営
- 高齢者施設
土地を賃貸する
前述のように、土地を賃貸すると、土地の評価額が借地権割合相当額だけ低くなります。
土地を賃貸するには、「事業用定期借地権」を設定する方法があります。
「事業用定期借地権」とは、土地を事業用の建物(居住用は不可)を所有する目的で一定期間借りる権利のこと。
土地を借りた事業者は建物を建て、オフィスビルや商業施設などを経営します。
契約期間は10~50年の間で設定され、契約期間終了後、事業者は原則として土地を更地にして返還します。
「事業用定期借地権方式」は初期費用がほとんどかからず、管理の手間がいらない土地活用法。
ただ、地代は一般的に建物賃料より低い水準であり、収益性は低い傾向にあります。
オフィスビル
オフィスビルを建てた場合、建物は「貸家」、土地は「貸家建付地」として扱われ、土地建物両方の評価額が下がります。
条件が合えば、小規模宅地等の特例を適用することも可能です。
オフィスの賃料は住宅より高水準であるため収益性は高い傾向にあります。
一方、立地を選ぶこと、景気変動の影響を受けやすいというデメリットがあります。
最寄駅から徒歩3~5分以内にありオフィスの需要がある場合は、オフィスビルを検討してみましょう。
▼関連記事
アパート・マンション経営
アパートや賃貸マンションを建てるとオフィスビル同様、建物は「貸家」、土地は「貸家建付地」として扱われ、土地建物の評価額が下がります。
条件を満たせば、小規模宅地等の特例も適用されます。
アパート・マンション経営は、相続税だけでなく固定資産税等の節税効果も高く、節税目的の土地活用法として代表的なものです。
オフィスビルに比べて、収益の安定性が高いのもメリット。
ただ、アパート・マンション経営は、最寄駅からの距離など立地が重要。
最寄駅から徒歩圏内になくバス便の場合は、需要が乏しいのが一般的です。
マーケット分析を十分に行い、アパートやマンションの需要がある地域なのか調べましょう。
▼関連記事
高齢者施設
「サ高住」や「老人ホーム」などの高齢者施設も、相続税対策としておすすめです。
アパートやマンションと同様、土地および建物がそれぞれ「貸家建付地」「貸家」として扱われ、土地・建物の相続税評価額が下がります。
小規模宅地等の特例を適用することができれば、さらに大きく評価額を下げることができます。
条件に合えば固定資産税等の優遇も受けられるため、もっとも節税効果の高い土地活用法のひとつです。
さらに、高齢者施設の建築に当たっては、国や自治体から建築費に補助が出ることも期待できます。
高齢者施設は介護事業者への一棟貸しが一般的なので、安定した収益が得られ管理の手間がかかりません。
ある程度大きな土地が必要ですが、アパートやマンションと違って、駅から遠く賃貸アパートやマンションの需要が弱いところでも可能です。
▼関連記事
相続税対策で土地活用をする際の注意点
相続税対策に有効な土地活用ですが、いくつか注意したいポイントもあります。
現金よりも遺産分割が難しくなる
不動産は現金や預貯金に比べて分割が難しいため、遺産分割時に揉めてしまうことがあります。
たとえば、複数の相続人が不動産を共有財産として相続した場合、不動産の管理や処分に当たって意見がまとまらないことがよくあります。
将来さらなる相続が発生した場合に、さらに多くの人による共有になる可能性もあるでしょう。
一方、不動産を一人の相続人に相続させる場合は、その他の相続人に相続させる同等の財産を用意しておく必要があります。
賃貸収入等を将来の遺産分割のために確保していくことも、対策として考えられます。
遺産分割に関して、相続人を交えて事前に話し合っておくとよいでしょう。
相続税を支払うのに必要な現金は残しておく
相続税を支払うために現金が必要になるので、納税のために必要な現金は残しておきましょう。
土地活用による家賃収入を子供などの相続人が受け取る仕組みにして、将来の相続税支払いに充てることもできます。
ただこの場合、家賃収入が将来も安定的に入るとは限らないことに注意が必要です。
小規模宅地等の特例を適用する場合は要件を確認する
「小規模宅地等の特例」が適用されるためには、土地の上に建物が建っていること、被相続人と相続人が生計を共にしていたことなど、複数の条件があります。
事前に「小規模宅地等の特例」の適用要件を確認しておきましょう。
たとえば条件の1つに、アパート・マンションなど貸付事業用建物が建っている土地に相続人が貸付事業を引き継ぐ必要があります。
アパート・マンション経営にはスキルと経験が必要です。
適切な維持管理がなされなければ、空室が増えてしまうでしょう。
空室が増えると、相続税計算時に「貸家」として減額される割合も減ってしまい、節税効果が薄れます。
貸付事業を適切に引き継ぐために、事前に以下の対策をしておきましょう。
- 貸付事業を引き継ぐことができる相続人を探しておく
- 貸付事業を継承する予定の相続人に、経営の仕方を教えておく
土地活用法は相続税対策だけで決めない
土地活用法は相続税対策だけでなく、様々な観点から検討した上で決定しましょう。
特にマーケット分析や収支予測を十分に行わずに土地活用を始めてしまうと、次のような事態になる可能性があります。
- 事業開始後になかなか借り手が見つからない
- 急な修繕などで思わぬ支出が発生して収支を圧迫する
土地活用の採算が取れずにローン返済だけが重くのしかかり、節税どころではなくなってしまいます。
土地活用法を決めるに当たっては、地域のマーケット分析を十分行い、修繕費など将来必要となる突然の支出を予測し備えておくことが重要です。
土地活用による収益も相続財産になる
土地活用による節税効果は、建物を建てた時が最大です。
建物を賃貸し始めてから時が経つにつれて、家賃収入が相続財産に加算されていきます。
相続税対策のためには、土地活用開始後も相続財産の増減に注視することが重要です。
なお、なるべく相続財産を増やさないために、家賃収入等を相続人に生前贈与する方法もあります。
この場合、前述した「暦年贈与」を活用するなどして、贈与税がかからないような対策が別途必要です。
ローン利用による節税効果は場合により異なる
上述した様に、借入金は相続財産評価額から控除できるため、建築費などの初期費用をローンで賄うと、相続税の節税効果があります。
ただし、初期費用を賄えるほど自己資金を有している場合は、ローンを利用しても相続税対策にはならないので注意が必要です。
借入金相当額を相続財産評価額から控除できても、同額を預貯金で持っていれば、相続財産評価額の合計は変わらないからです。
土地活用を始めるに当たっては、ローンを利用することのメリットおよびデメリット、納税に必要な現金の額などを比較検討した上で、資金調達方法を考えましょう。
まとめ
子供などに残す資産がある場合、相続人が将来支払う相続税の負担をできるだけ軽減したいと考えている方は多いかと思います。
相続税対策には、土地活用が有効です。
この記事では、相続税対策に有効なおすすめの土地活用法として、以下の方法を紹介しました。
- 土地を賃貸する
- オフィスビル
- アパート・マンション経営
- 高齢者施設
土地活用により「小規模宅地等の特例」を受けられる場合、より節税効果が大きくなります。
中でも、立地を選ばず安定的な収益を期待できる高齢者施設の土地活用がおすすめです。
相続税対策のために土地活用する際に注意すべきポイントは、多岐にわたり複雑です。
『関連記事:所有者が死亡した車の廃車手続き方法は?』