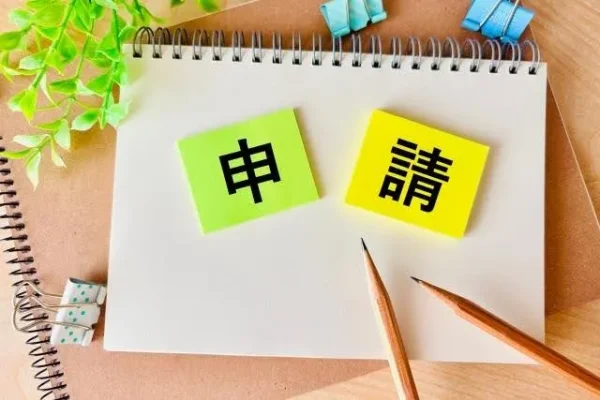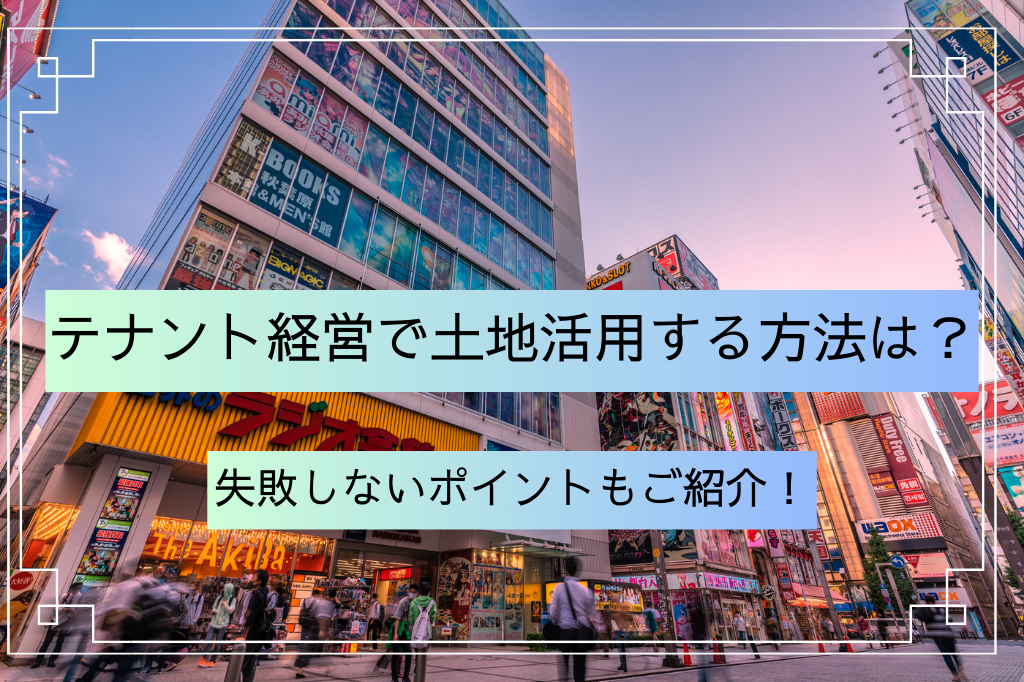土地活用をしたいと思っても、土地活用にはどんな方法があるのか、どれを選べばいいのか分からないという方は多いのではないでしょうか。
土地活用法は、一般的なアパート経営や駐車場運営の他にも、たくさんあります。
この記事では、土地活用の事例20選を紹介し、それぞれのメリット・デメリット、目的別に土地活用法の選び方も解説します。
土地活用に失敗しないために考えておくべきこともお伝えしますので、是非参考にしてください。
土地活用事例20選
以下で、土地活用事例20選を紹介します。
土地売却
遠方に住んでいて土地の管理が難しい、短期的にまとまった収入を得たいといった場合、土地を売却するのも土地活用事例のひとつ。
土地を売却すれば固定資産税等の税金がかからなくなり、すぐに収入を得られるというメリットがあります。
ただ、仲介手数料や譲渡所得税などの売却費用がかかること、他の土地活用事例のように継続的な収入を得ることはできなくなる点に留意が必要です。
駐車場
建物が建てられない市街化調整区域や、建物を建てても需要が見込めない地域では、駐車場を運営する土地活用の事例があります。
駐車場は、狭小地や変形地でも始められます。
駐車場には、月極駐車場とコインパーキングがあり、次の2点によってどちらが適しているかは異なります。
- 土地の大きさ
- 立地
月極駐車場よりもコインパーキングの方が、狭い土地でも始められます。
立地については、駅近のエリア、大型店舗の近く、観光地などでは短時間駐車できるコインパーキングの需要があります。そうでない場合は、月極駐車場がよいでしょう。
駐車場運営は、初期投資額が小さく、管理にあまり手間がかかりません。建物がないので、将来的に土地の用途を変更するのも容易。
ただ、収益性は低く、節税効果は小さいというデメリットもあります。
▼関連記事
資材置き場
建物が建てられないエリア、他の土地活用の需要がないエリアの土地活用事例として、資材置き場があります。
建設会社等が近くにある場合、資材置き場としての需要が見込めます。
ある程度整地されている土地であれば、初期投資なしで始められ、用途変更も容易でしょう。
短期間だけ土地活用したいといった場合にも適した土地活用です。
ただ、地代は建物賃料より低いのが一般的であり、高い収益性は期待できません。
太陽光発電
周りに太陽光を遮るものが少ない郊外や田舎でできる土地活用事例として、太陽光発電があります。
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)」という国の制度により、10年間固定価格で電力をエネルギー会社に買い取ってもらえます。
立地条件の劣るエリアでも、安定した収入を得られる土地活用法です。
太陽光発電は国が推奨していることから、補助金を得られる可能性もあります。
収益性が低く節税効果がないのがデメリットです。
また、10年間を過ぎると固定価格では買い取ってもらえなくなることに注意しましょう。
貸農園
貸農園は、所有する農地を自身で営農できない場合の土地活用事例。
貸農園の需要がある郊外や、観光農園としての需要が見込める地域の農地に適しています。
農地転用せずに土地活用できる方法ですが、収益性が低く、管理の手間がかかるのがデメリットです。
戸建て賃貸
30坪程度の小さな土地でも始められるのが、戸建て賃貸による土地活用事例です。
木造が一般的で、アパートやマンションより建築費を抑えられます。
住宅系の土地活用法は、土地の固定資産税・都市計画税や、相続税において優遇制度があるため、節税効果が高いのが大きなメリット。
既に中古の戸建てが建っている場合は、建築費の初期投資が不要になります。
戸建賃貸では、単独のファミリー世帯に貸し出すことになります。
ファミリー世帯は入居期間が長いことが多いですが、入居者が退去した場合はとたんに収入がゼロになる空室リスクもあります。
アパート・マンション
最寄り駅からの距離が近いエリアや住宅地では、アパートやマンションを経営する土地活用事例があります。
アパートは木造や鉄骨造りで、30坪程度の小規模土地でも検討可能。
マンションは鉄筋コンクリート造が多く、建築費がやや高めな分、賃料水準もアパートより高い傾向にあります。
駅近なら単身者向け、駅からやや遠いけれど住環境の良いところならファミリー向けのアパートやマンションが向いています。
アパートやマンション経営は、住宅需要があるエリアであれば安定的な収入が期待できるでしょう。
戸建賃貸と同様、節税効果が高いのも利点です。
一方、建築費などの初期投資がかかる、管理に手間がかかるなどのデメリットもあります。
▼関連記事
オフィスビル
駅近のエリアなどでは、オフィスビルを建てるのも土地活用事例の1つ。
賃貸住宅よりも、高い家賃を徴収できるのがメリットです。
オフィスビルは内装工事を施さずに貸す「スケルトン貸し」が多く、マンションに比べて建築費が安く済みます。
ただ、オフィスビルは立地を選び、景気に左右されやすいです。
ホテル
ターミナル駅や繁華街、観光地の近くなど集客力の高いエリアでの土地活用事例として、ホテルがあります。
ホテル経営は比較的小規模な土地でも始められ、高収益が期待できるでしょう。
一方、建築費用が高い、景気に左右される、転用が難しいなどのデメリットもあります。
店舗ビル
駅近のエリアや繁華街では、店舗ビル建設も土地活用事例の1つ。
オフィスビル同様、スケルトン貸しが一般的で、管理の手間も比較的少なく済むます。
店舗の賃料は、住宅やオフィスなど他の用途に比べて高水準です。
ただ、店舗は景気に左右され、住宅に比べて空室リスクが高いことに注意しましょう。
ロードサイド店舗
車両交通量が多い幹線道路沿いで、店舗の需要がある地域の土地活用事例は、ロードサイド店舗。
車での来店客がメインであるため、駐車場スペースの確保は重要です。
ロードサイド店舗は一般的に契約期間が長く、いったん契約したら安定的な収益を得られます。
賃貸住宅に比べて、管理の手間が少ないのがメリット。
店舗ビルと同様、景気に左右されやすく、契約終了後に次のテナントを見つけにくいことがデメリットです。
契約期間中の途中解約のリスクに関しては、契約時に違約金の設定をすることで対応できます。
▼関連記事
商業施設
幹線道路沿いにある大規模土地の土地活用事例として、ショッピングセンターなどの商業施設があります。
商業施設を建設することで、周辺エリアがにぎわうなど地域貢献ができます。
事業者と長期間の契約を結ぶため、安定的な収益が期待できる上、管理はテナント自身が行うことが一般的です。
商業施設は一般的な経済状況に左右されるため、テナントが撤退または契約期間終了後、次のテナントを見つけるのが困難な時もあります。
▼関連記事
シェアハウス
駅や大学の近くなど、若年世代の賃貸需要があるエリアであれば、シェアハウスという土地活用事例も選択肢のひとつ。
シェアハウスは単身者向けで、若年世代を中心に注目され、近年増えてきています。
シェアハウスは、リビング、キッチン、浴室、トイレなどが共用であることから、通常の共同住宅より建築費用を抑えることができます。
デメリットは、他人同士が共同生活を送ることから、住民同士のトラブルが多くなる傾向があることでしょう。
保育園
住宅街または駅の近くでは、保育園の土地活用事例があります。
日本では、地域によっていまだ保育園が不足している地域があり、保育園としての土地活用は、社会貢献につながります。
児童福祉施設のひとつである保育園は税制優遇があるため、節税効果の高い土地活用事例です。
契約期間は長期にわたることが多いため、安定的な収益が見込めます。
一方、自治体の審査などが必要であるため、開園まで長期間の準備が必要である点はデメリット。
また、建物は保育園特有の造りや設備であるため、転用は難しいでしょう。
▼関連記事
医療施設
医療施設には、「診療所」と「病院」の2種類があり、2つの区別は以下のとおりです。
- 「診療所」: 入院設備がないか、入院用のベッドが19床以内
- 「病院」: 入院用のベッドが20床以上
診療所は、賃貸マンションなどと比べて建築費が抑えられます。
一方、病院は用途地域によって建築できない場合もあるため、注意が必要です。
なお、同じ医療施設としての土地活用事例でも、複数の医療施設に貸し出すテナントビルを建てる方法もあります。
医療施設は一般的に安定的な収益を見込める一方、建物の用途が変更しづらいデメリットもあります。
高齢者施設
高齢化社会で需要が高まっているのが、高齢者施設。
高齢者施設には、老人ホーム、デイサービス、グループホームなどがあります。
施設にもよりますが、ある程度まとまった土地が必要です。
高齢者施設は周辺の環境の良さが重視され、一般的に立地条件が悪いとされる地域であっても、始められます。
建物を事業者が一括借上げして運営するケースが多く、長期間にわたって安定的な収益を期待できます。
また、賃貸住宅同様に節税効果があります。
デメリットとしては、特別な設備が必要であり建築費が高くなること、転用が難しいことが挙げられます。
▼関連記事
サ高住(サービス付高齢者住宅)
いわゆる「サ高住」(サービス付高齢者住宅)も、高齢化の進展で需要が高まっている土地活用事例。
サ高住は、一定の要件を満たせば補助金がもらえ、税制優遇もあります。
高齢者施設と同様に安定的な収益を期待できます。
一方、サ高住は床面積や設備に規定があるため、建築費が高くなるデメリットもあります。
トランクルーム
トランクルームは、住宅等の需要がない地域でもできる土地活用事例。
「コンテナ」という建物を建築し、収納スペースとして利用者に貸し出すことで賃料を得ます。
小規模な土地でも始められ、初期投資額はあまり大きくありません。
駐車場同様、将来的な用途変更も容易であるメリットもあります。
ただ、収益性は高くなく、節税効果は期待できません。
倉庫
幹線道路沿いや高速道路のインターチェンジ付近などの大規模土地では、倉庫の土地活用事例があります。
ネット通販市場が拡大している近年、倉庫の需要は増えています。
初期費用はあまりかからず、管理の手間も少ないのがメリット。
住宅、オフィス、店舗などの土地活用に比べて収益性は劣り、節税効果はありません。
▼関連記事
コインランドリー
狭い土地でも始めやすい土地活用事例が、コインランドリー。
利用者が洗濯ものを車で運ぶことが想定されるため、駐車場はあった方が良いでしょう。
コインランドリーは、管理者が常駐する必要がなく、手間がかからないのがメリット。
デメリットとして、設備の導入にコストがかかる、収益が安定しづらいなどがあります。
「参考:土地活用のアイデア18選!土地に合わせた活用方法とは? | 民泊・Airbnb運営管理代行の株式会社プレイズ」
目的別土地活用法の選び方
ここまで、様々な土地活用事例を紹介してきました。
最適な土地活用法は、土地活用をする目的によって変わります。
土地活用をする目的は、節税対策したい、安定的な収益を得たい等、人によってさまざまです。
以下で、主な土地活用の目的を6つ挙げ、それぞれの目的に合った土地活用事例を解説します。
土地活用の目的 | 土地活用事例 |
|---|---|
土地活用で節税対策したい | ・戸建て賃貸、アパート、マンション、高齢者施設、サ高住など |
初期投資額を抑えて土地活用したい | ・駐車場経営、資材置き場、貸農園など ・「事業用定期借地権」方式や「リースバック」方式を採用した土地活用事例(※) |
短期間だけ土地活用したい | ・駐車場、資材置き場、太陽光発電、トランクルームなど |
土地活用で高収益を得たい | ・オフィスビル、ホテル経営、店舗ビル、ロードサイド店舗、商業施設など |
土地活用で長期安定的な収益を得たい | ・アパート・マンションやサ高住などの住宅系、・保育園、医療施設、高齢者施設など |
手間をかけずに土地活用したい | ・資材置き場、駐車場など ・「事業用定期借地権」方式や「リースバック」方式を採用した土地活用事例(※) |
※ 「事業用定期借地権」方式や「リースバック」方式を採用した土地活用事例には、オフィスビル、店舗ビル、ロードサイド店舗、商業施設などがあります
土地活用で節税対策したい
建物が建っていて、建物の用途は住宅系であるほうが節税効果は高くなります。
具体的には、住宅系の賃貸アパート、マンション、高齢者施設、サ高住などが、節税効果の高い土地活用事例です。
賃貸住宅を建てると、「小規模住宅用地の特例」により固定資産税・都市計画税が軽減されます。
また、相続税計算上、土地は「貸家建付地」として評価されるため、更地の場合よりも約8割になります。
初期投資額を抑えて土地活用したい
土地活用で初期投資額を抑えるには、主に3つの方法があります。
- 建物を建てない
- 建物建築費をテナントが負担する
- 補助金制度を活用する
以下で詳しく説明します。
建物を建てない
初期投資額で一番大きいのは、建築費。
建物を建設しない土地活用事例である駐車場経営、資材置き場、貸農園の場合、初期投資額を抑えて土地活用することが可能です。
建物建築費をテナントが負担する
ロードサイド店舗を始めとした、建物建設を前提とする土地活用事例においても、「事業用定期借地権」や「リースバック方式」を採用すれば、初期投資額を抑えることができます。
事業用定期借地権では借地人が、リースバック方式ではテナントが建物建築費を負担します。
【事業用定期借地権】
事業用定期借地権とは、事業の用途のみに限定して、期間を定めて土地を賃貸するもの。
借地人が事業用の建物を建築するため、地代は建物賃料に比べて安く、収益性は低いのが一般的です。
一方、契約期間満了後は更地で返還されるため、用途変更がしやすい利点もあります。
【リースバック方式】
テナントが払う「建設協力金」を建築費に充当して、土地オーナー名義で建物を建築。
テナント入居後は、家賃から建設協力金の返済額を差し引いた差額を、土地オーナーが受けとります。
自己資金を抑えて始められますが、建物がテナントの要望に沿って建てられているため、テナント退去後の転用が難しいというデメリットもあります。
補助金制度を活用する
条件に合えば補助金が交付される保育園、高齢者施設、サ高住などの土地活用事例を選ぶことで、初期投資額を抑えて土地活用することが可能です。
短期間だけ土地活用したい
将来的にその土地を親族が使用する可能性がある場合などは、用途変更が容易な駐車場、資材置き場、太陽光発電、トランクルームなどがよいでしょう。
まとまった収入を得たい場合は、土地を売却するのもひとつの手段です。
ただし、土地の需要が弱い地域では売却までに時間がかかる場合があり、いったん売却したら、今後その土地から収入を得られる可能性はゼロになってしまいます。
土地活用で高収益を得たい
高収益を得られる土地活用事例には、オフィスビル、ホテル経営、店舗ビル、ロードサイド店舗、商業施設などがあります。
賃貸住宅よりも、高い賃料を設定できるのが一般的です。
ただ、土地活用に限った話ではありませんが、高収益の資産運用にはリスクが付きもの。
オフィス、ホテル、店舗などは立地条件や景気に左右されやすい、などリスクが高いのです。
高収益を得られる土地活用は、ハイリスク・ハイリターンであることを覚えておきましょう。
土地活用で長期安定的な収益を得たい
以下の活用事例であれば長期間入居してくれることが期待でき、長期安定的な収益を期待できます。
- 高齢者施設
- アパート・マンション、サ高住などの住宅系
- 保育園
- 医療施設
特に、高齢者施設、医療施設、保育園などは公共性が高く、長期契約を結ぶことが多いため、安定性は高いと言えるでしょう。
手間をかけずに土地活用したい
管理に手間がかからないのは、建物を建てない土地活用事例と、建物をテナントが管理する土地活用事例です。
たとえば、建物を建てない土地活用事例である資材置き場や月極駐車場は、いったん契約をした後は、管理業務はあまり多くありません。
駐車場専門業者が土地を一括借上げする方式では、管理を業者に任せることができます。
また、上述したように、「事業用定期借地権方式」や「リースバック方式」でできる土地活用事例は、テナントが建物を管理するのが一般的であり、あまり手間がかかりません。
土地活用で失敗しないために考えておくべきこと
土地活用の目的がはっきりしていれば、土地活用法の選択肢がいくつか絞り込めると思います。
では、土地活用を成功させるに当たって、あらかじめ考えておくべきことは何でしょうか。
土地活用法が土地の特徴に合っているか
土地活用の目的に照らして始めてみたい土地活用法があっても、土地の特徴に合っていなければ土地活用は成功しません。
土地の特徴に合った土地活用をするには、以下の3点に注意しましょう。
- 建築上の法規制
- 需要の有無
- 土地の規模・形状
建築上の法規制
土地活用法は、建築上の法規制の範囲内で選ぶのが大原則。
土地は、都市計画法や建築基準法により、建物の用途や規模などについての様々な規制を受けます。
建築規制は、市役所等で調べてみましょう。
たとえば、以下のような建築規制があります。
- 「市街化調整区域」では、原則として建物建築不可
- 「市街化区域」では、「用途地域」ごとに建てられる建物の用途や規模が規定されている
需要の有無
需要のない土地活用法を選ぶと、土地活用で失敗してしまいます。
たとえば、人口の少ない地域にある駅から遠い土地では、そもそも賃貸需要が見込めないことがあります。
そのような場所にアパートやマンションを建てても、土地活用は成功しません。
事前に十分なマーケット分析を行ってから、土地活用法を決めることが大事です。
土地の規模・形状
土地の規模や形状によっても、合う土地活用法は異なります。
ロードサイドの土地を例に取ってみましょう。
車での来店が多いロードサイド店舗は、駐車場スペースが十分取れることや、車の出入りが容易な土地の位置・形状であることが必須条件です。
これらの条件に当てはまらない土地は、たとえ店舗需要があるエリアであっても、ロードサイド店舗には向かないでしょう。
土地活用するに当たっての優先順位
土地活用するに当たって自身が何を優先するかによって、最適な土地活用法は変わります。
土地活用法を決める前に、自身が優先したい点を明確にしておきましょう。
人によって優先順位は異なるものですが、たとえば以下のようなものがあります。
- 収益性は低くてもよいので、管理に手間をかけたくない
- 初期投資額は大きくてもよいので、高収益を狙いたい
管理にかけられる時間
自身が管理にかけられる時間も、じっくり検討しておくべきポイントです。
土地活用法の多くは、建物の建築や契約締結が完了後にもすべきことがあります。
長期間にわたって管理業務を行ったり、契約期間満了後に新しいテナントを募集したりといった業務が発生し、時には現地に赴いて業務を行う必要もあるでしょう。
遠方に住んでいる場合は、特に慎重に判断すべきです。
以下の2点について、あらかじめ把握しておきましょう。
- 自分で管理を行う場合、どのくらい時間を割けるのか
- 管理を外部に委託する場合、委託費用はどれくらいか
他の用途に転用しやすい土地活用法か
土地活用においては、 相続などで状況が変わり、土地の用途を変更する必要が生じることもあります。
採用する土地活用法は、用途変更しやすいものかどうかも把握しておきましょう。
建物を建てない駐車場や資材置き場では、容易に用途変更できます。
一方、病院、ホテル、ロードサイド店舗などは特殊な建物であり、特別な設備が必要であるため、他の用途に転用しづらいという特徴があります。
土地活用法を決めるのに十分な時間をかけたか
土地活用は、プランを変更したり途中でやめたりしづらいものです。
じっくり時間をかけて活用方法を決めることが大切であるため、法規制や土地の特性など、自身でもできる範囲で調査を行ってください。
その上で、 信頼できる会社に相談しましょう。
調査結果を参考に最適な土地活用方法や必要な準備について教えてくれるはずです。
提示されたプランを検討する際には、初期投資額など短期的な収支だけでなく、長期的な収支も合わせて検討することが大切です。
まとめ
この記事では、土地活用事例20選を紹介しました。
土地の特徴や土地オーナーの優先順位によって、ベストな土地活用法は異なります。
土地やマーケット状況を分析し、複数の土地活用事例のメリット・デメリットを比較検討した上で、慎重に土地活用法を決めましょう。
なお、土地活用には、不動産に関する税制、マーケット分析など専門的な知識が必要です。
土地活用のプロで信頼できるパートナーを見つけ、相談することをおすすめします。
※参考|土地活用の方法31選!面白いアイディア・収益性・初期費用を徹底比較【おすすめランキング】GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]